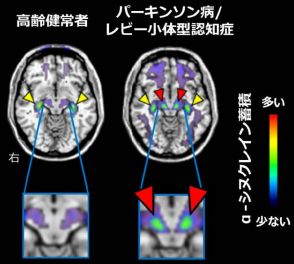国策が生んだハンセン病差別 補償請求をためらう元患者家族たち
ハンセン病の元患者の家族が補償を求める際に抱く複雑な思いや、身内に病歴を知られる恐れから請求をためらう事例が紹介されている。
補償金支給の件数が国の想定の3分の1にとどまる中、ハンセン病を巡る差別や偏見の根深さが浮き彫りになっている。
ハンセン病元患者家族が補償金を安心して請求できる環境整備が求められており、関係者はそのための取り組みを支持している。

ハンセン病の元患者の家族が味わった苦しみに対し、国が補償を決めてから5年になる。だが周囲に身内の病気を知られることを恐れて、請求をしない人も多い。
元患者らも複雑な思いで見つめている。
埼玉県に住むショウジさん(83)とケイコさん(74)夫婦(いずれも仮名)は、2人とも元患者だ。補償金の支給対象のきょうだいの中には、配偶者や子どもに身内の病歴を知られるのを恐れ、請求をしていない人がいる。
兄や弟がいるショウジさんは家族補償法が成立すると、離れて住む弟に電話で補償請求できることを伝えた。だが数日後、「兄と相談して申請はしないことにした」と告げられた。弟は妻にショウジさんの病歴を伏せており、「お金が振り込まれたら『この金は何か』と聞かれるから」というのが理由だった。
「この病気を思い出してほしくないという気持ちもある」。ショウジさんはそれ以上、兄弟に請求を勧めることはしなかった。「裁判で『国の施策が間違っていた』と示されても、すぐに『ハンセン病は普通の病気だ』とはならないんですよ」
ケイコさんには補償対象になるきょうだいが5人いるが、請求していない弟がいる。家族に伏せているケイコさんの病歴が、補償金の受け取りをきっかけに知られることを恐れているためだ。
患者隔離の根拠となった、らい予防法が1996年に廃止されてから28年。「偏見や差別を払拭(ふっしょく)するのは難しい」。ケイコさんは感じている。
◇補償金支給、想定の3分の1
国の誤った隔離政策によって差別や偏見に苦しんだハンセン病元患者の家族に国が補償する制度では、請求期限が迫る中、支給件数が国の想定の3分の1にとどまっている。
家族への賠償を国に命じた2019年6月の熊本地裁判決を踏まえ、同11月に家族補償法が成立した。同法は、元患者の家族が「望んでいた家族関係の形成が困難になるなど多大な苦痛を強いられてきた」とし、補償とともに、国会と政府による深いおわびや、偏見と差別を根絶する決意が盛り込まれている。
補償金を受け取るには、元患者の発病を証明する書類とともに請求する必要がある。制度を所管する厚生労働省は元患者家族を2万4000人と見込むが、支給に至ったのは5月17日までで8184件。請求期限は今年11月だが、5年間延長する改正法案が今国会中にも成立する見通しだ。
ハンセン病を巡る差別が続いていることは、国の調査で明らかになっている。厚労省が昨年12月、インターネットで実施したアンケートで、全国の約2万1000人のうち、元患者と家族に対する差別や偏見が「現在、世の中にあると思う」と答えた人は39・6%に上った。
ハンセン病家族訴訟弁護団の金丸哲大弁護士は「時間をかけて作られたハンセン病への差別意識は容易に変わるものではない。そのため、自身の家族への影響を恐れて補償金の請求をためらう元患者家族が今も多くいる」と指摘する。「請求期限の延長と合わせて、元患者家族が不安なく請求できる環境作りに国は取り組むべきだ。請求を迷っている方は一度弁護団に相談してほしい」と求めた。【添島香苗】