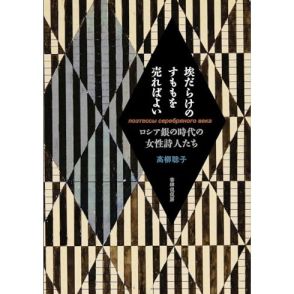悲嘆や逆境の連続だった紫式部が至った最後の境地 人生を見つめ、そして目覚めた先にあったものとは
紫式部は複数の逆境に直面し、人生の最晩年に自伝的な家集を編む。彼女の人生は会者定離というテーマを反映しており、悲しみや喪失を経験しつつも、最終的に心を取り戻す。
身代わりというテーマが紫式部の人生に根付いており、母や姉、友人の喪失から生じる哀しみが彼女の心を深く傷つける。しかし、それでも彼女は折れずに生き続けた。
夫を失った時に限界を感じた紫式部だが、その経験を通じて人とは何かという問いに目覚め、心と身の関係を理解する。『紫式部集』を通じて、彼女は「置かれた場所」で新たな人生を見つける。

父の失職や身内との死別、同僚からのいじめなど、多くの苦難を背負ってきた紫式部。『紫式部集』では、逆境に生きた紫式部が至った最後の境地が詠まれているという。平安文学研究者・山本淳子氏の著書『平安人の心で「源氏物語」を読む』(朝日選書)から一部を抜粋、再編集し紹介する。
* * *
■紫式部の気づき
修道女の渡辺和子さんに『置かれた場所で咲きなさい』という名著がある。「置かれたところこそが、今のあなたの居場所なのです」「咲けない日があります。その時は、根を下へ下へと降ろしましょう」。文中の慈愛に満ちたこの言葉に、私は紫式部に通じるものを感じてならない。渡辺さんは、軍人だった父を二・二六事件の青年将校たちによって目の前で射殺された体験を持つ。紫式部の人生も、悲嘆や逆境の連続だった。だが紫式部も、置かれたその場その場に自分なりの根を降ろしている。『源氏物語』という大輪の花さえも咲かせている。
「めぐりあひて見しやそれともわかぬ間に雲隠れにし夜半(よは)の月かな」。紫式部の私家集(しかしゅう)『紫式部集』の冒頭歌だ。小倉百人一首でご存じの方も多いだろう。紫式部自身が記す詞書(ことばがき)によれば、これは幼馴染みに詠んだ和歌だった。長く別れ別れになっていて、年を経てばったり再会。だが彼女は月と競うように家に帰ってしまった。「思いがけない巡り合い。『あなたね?』、そう見分けるだけの暇もなく、あなたは消えてしまったね。それはまるで、雲に隠れる月のように」。楽しい友情の一場面のようだが、そうではない。この友はやがて筑紫(つくし)に下り、その地で死んだ。天空で輝いていた月が突然雲に隠されて姿を消すように、二度と会えない人となったのだ。
紫式部が人生の最晩年に自伝ともいうべき家集を編んだ時、巻頭にこの和歌を置いたのは、ほかでもない、こうした「会者定離(えしゃじょうり)」こそ自分の人生だと感じていたからだ。紫式部は、おそらく幼い頃に母を亡くしている。姉がいたが、この姉も紫式部の思春期に亡くなった。そんな頃に出会ったのが、先の友である。偶然にも彼女の方は妹を亡くしており、二人は互いに「亡きが代はりに(喪った人の身代わりに)」慕い合った。『源氏物語』に幾度も現れる「身代わり」というテーマ。紫式部にとって幼馴染みを喪ったとは、母と姉と友自身の、三人分を喪ったことでもあったのだ。
それでも折れなかった心が、夫を喪った時、とうとう折れた。本来、人に身代わりなどないのだ。哀しみを慰める術の限界を突きつけられて、紫式部は泣くしかない。この時の心境は、『源氏物語』のなかで紫の上を喪った光源氏と大君(おおいぎみ)を喪った薫(かおる)各々の述懐に活かされていよう。自分に無常を思い知らせようとする仏の計らいだ、つまり降参するしかないと、彼らは言うのだ。光源氏はそれを機会に出家する。薫は魂の彷徨を続ける。では紫式部はどうしたか。人生を見つめ、そして目覚めたのである。
人とは何か。それは、時代や運命や世間という「世(現実)」に縛られた「身」である。身は決して心のままにならない。まずそれを、紫式部はつくづく思った。だが次には、心はやがて身の置かれた状況に従うものだと知る。胸の張り裂けるような嘆きが、いつしか収まったことに気づいたのだ。「数ならぬ心に身をば任せねど身にしたがふは心なりけり(ちっぽけな私、思い通りになる身のはずがないけれど、現実に慣れ従うのが心というものなのだ)」(『紫式部集』五十五番)。紫式部は「置かれた場所」で生き直し始めたといえよう。