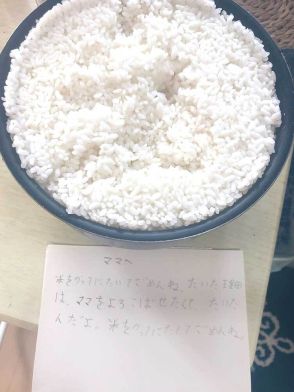相続不動産の名義変更は自分でできる? 費用や手間、必要書類を詳しく解説
不動産を相続した際の名義変更手続きについて解説しました。
相続登記を放置することで生じるデメリットについて詳細に説明しました。
相続登記の重要性と放置した場合のリスクを示しました。

不動産を相続した時に行う名義変更。どのような手続きが必要で、費用や手間はどのくらいかかるのでしょうか。自分で行う場合の注意点、専門家に依頼した場合の報酬などについて解説します。
不動産は、その所在地を管轄する法務局にそのデータが管理されており、その種類(用途)や面積、誰がどのような権利を有しているかが記録されています。その証明書を「登記事項証明書」といい、一般的には「登記簿謄本」と呼んでいます。
不動産の売買などで、この登記記録に変更があった際には登記記録を変更します。登記名義人が死亡した場合でも、不動産の権利は相続人に承継されますので、相続人を新たな名義人とする所有権移転登記を申請します。この相続を原因とする所有権移転登記のことを一般に「相続登記」と呼んでいます。
相続登記は、法改正によって2024年4月1日から義務化されました。申請期限は「所有権を取得したことを知った日から3年以内」で、正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料を科される可能性があります。また、2024年4月1日以前に発生していた相続にも適用されるため注意が必要です。
不動産を相続したにもかかわらず、相続登記をせずに放置していると、不測の損害を被る可能性があります。
以下に相続登記を放置した場合のデメリットをいくつか挙げます。
2-1. さらなる相続(数次相続)が発生するリスク
相続登記を放置していると、相続人であった人も亡くなり、話し合い(遺産分割協議)をしなければならない人数がどんどん増えていくことになります。
例えば、親が亡くなり、兄弟間での遺産分割協議を放置していたとします。その間に、兄弟のうちの一人が亡くなると、叔父と甥の関係性での話し合いや弟の奥さんとの話し合いが生じます。さらに放置すれば、最初の相続人全員が死亡し、それぞれの配偶者や子供同士(いとこ同士)が話し合いをしなければならない状況に陥ってしまいます。
こうなると、ほとんど話をしたことのないような関係性の相続人が登場することもありますから、話し合いに行き着くまでにもひと苦労です。仮に連絡がついたとしても、疎遠な親族間での協議では、合意が得られないことは多々あります。
2-2. 相続持分売却のリスク
民法には、相続人の順位やそれぞれの相続人の相続分が規定されています。これを「法定相続分」といいます。
不動産の登記名義人が亡くなると、遺産分割協議の結果にもとづいて相続登記をするケースが多いのですが、この法定相続分の割合で相続人全員の名義に登記することもできます。このような複数人が所有権を持つことを「共有」といいます。
ただ、「共有」はおすすめできません。共有者は自分の持分を第三者に売却することができます。こうなると、第三者と、ほかの相続人がその不動産を共有するという奇妙な状況になってしまいます。
現実的に共有持分だけを売却できるのか、また買い取る人が存在するのか、という疑問があるかと思いますが、理論上問題ありませんし、自分の持分だけを売却するのに他の共有者の同意は不要です。そのような買取業務を行う不動産業者もあります。
ここではリスクのお話ですので、実際には頻繁に起こるような事案ではありませんが、そのようなことも現実的には可能ですから、早めに遺産分割協議を行い相続人全員が納得した相続登記を完了させることが重要といえます。
2-3. 相続分の差押えのリスク
ここで、もう一つ相続登記を放置した場合のリスクをご紹介します。
相続人が被相続人の配偶者・長男・次男である場合に、次男の生活状況がよくなく、借金の返済もできないケースを想定します。お金を貸している側(債権者)としては、この次男に他に何も財産がないのであれば、相続したその不動産をなんとかしたいと考えます。
そこで、先ほどご紹介した法定相続登記が登場します。債権者などの利害関係があり、不動産の共有者の持分を差押えたい場合には、相続人の一人ではないにもかかわらず、代わりに法定相続登記をすることができます。これを「債権者代位登記」といいます。その後、債権者は次男の持分4分の1を差押えて、売却することによってその売買代金から次男に貸し付けた債権を回収します。
このような状況になってから、慌てて遺産分割協議をし、不動産の所有権を配偶者が単独で相続するという話し合いをまとめ、差押えをした債権者に対し「遺産分割協議で、配偶者が不動産全部の権利を取得しました」と主張しても、時すでに遅しです。