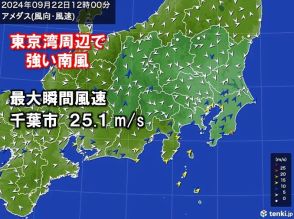ラジオはどう国民を戦争に向かわせたのか…NHKがこれまで向き合わなかった「戦争責任」の正体
ラジオ放送が日本で始まって来年でちょうど100年になります。1925(大正14)年に日本のラジオが産声をあげたのですが、実は初めから「日本放送協会」として始まったのではなく、 東京・大阪・名古屋に1つずつ、放送局が作られたんですね。そして、ラジオはその出発時から「無線電信法」という法律のもとに始まりました。その第1条には「政府之ヲ管掌ス」と謳われています。
本来、船の無線などを管理するための法律に、ラジオ放送の内容まで管理されることになってしまったわけです。そう言うと、ラジオっていうのは最初からいわゆる「御用放送」だったんだと思われるでしょうが、そうではないのです。たとえば東京放送局の講演放送のなかで、帆足理一郎が「国家予算があまりにも軍事に取られ過ぎで、もっと国民の文化や福利厚生に向けるべきだ」と主張したり、安部磯雄が民主主義というものは人間が生きていく上で最も大事な根本的な考え方だと主張したりしています。
彼ら「放送人」たちは、戦争協力について煩悶したり懊悩したりするのですが、結局は、どうすれば国民を戦争に動員できるかという一点に向かっていくことになります。軍部や政府に屈服していったその道を「戦争だから仕方がなかった」と一言で片づけてしまいがちですが、違うのではないかと思います。彼らは「仕方なく」ではなく、全身全霊をかけて戦争協力に邁進したのです。

1925 年に登場し、瞬く間に時代の寵児となったラジオ。そのラジオ放送に携わった人々は、ラジオの成長と軌を一にするかのように拡大した「戦争」をどう捉え、どう報じたのか、あるいは報じなかったのか。また、どう自らを鼓舞し、あるいは納得させてきたのか。そして敗戦後はどう変わり、あるいは変わらなかったのか――。
記者・ディレクター・アナウンサー…といった「放送人」たちが遺した証言と記録、NHKにある稀少な音源・資料などを渉猟し、丁寧にたどり、検証しながら、自省と内省の視点を欠くことなく多面的に「戦争とラジオ」の関係を追ったのがノンフィクション『ラジオと戦争 放送人たちの「報国」』だ。本作は7月18日に最終選考会が行われる第46回講談社本田靖春ノンフィクション賞の最終候補作となった。著者・大森淳郎氏によるスペシャルコメントをお届けする。
ラジオ放送が日本で始まって来年でちょうど100年になります。1925(大正14)年に日本のラジオが産声をあげたのですが、実は初めから「日本放送協会」として始まったのではなく、 東京・大阪・名古屋に1つずつ、放送局が作られたんですね。そして、ラジオはその出発時から「無線電信法」という法律のもとに始まりました。その第1条には「政府之ヲ管掌ス」 と謳われています。
本来、船の無線などを管理するための法律に、ラジオ放送の内容まで管理されることになってしまったわけです。そう言うと、ラジオっていうのは最初からいわゆる「御用放送」だったんだと思われるでしょうが、そうではないのです。たとえば東京放送局の講演放送のなかで、帆足理一郎が「国家予算があまりにも軍事に取られ過ぎで、もっと国民の文化や福利厚生に向けるべきだ」と主張したり、安部磯雄が民主主義というものは人間が生きていく上で最も大事な根本的な考え方だと主張したりしています。
あるいは、当時の国際連盟が「人身売買禁止条約」を作りそれを日本も批准するんですが、その批准にあたって植民地を適応除外にするなどの条件をつけていて、久布白落実は、「これで日本は、自ら進んで人道上、特殊国に陥りました」とラジオで批判しています。一方で、軍人の精神訓話のような講演もあったのですが、初期ラジオは多様性を保持していたということは確認しておいた方がいいかなと思うのです。
しかし、ラジオ放送が開始されて1年後、3つの放送局は逓信省の主導によって「日本放送協会」に統合されるのですが、その理事のほとんどが逓信省の出身者で占められていました 当時の逓信大臣・安達謙蔵は、日本放送協会の業務は「殆ど国務に準ずる」と述べていました。
しかしそれでいきなりすべての放送が御用放送になったわけでもないのです。日本放送協会には西本三十二や多田不二、あるいは奥屋熊郎といった元々はリベラルだった知識人もいました。彼らはその叡智を放送に振り向けていたわけですが、1931年(昭和6)の満州事変、37年の日中戦争、41年の太平洋戦争と、いわゆる「十五年戦争」の間に、才能豊かな先輩たちは、気付けば後戻り不能な、戦時体制の強化に呑み込まれていきます。
彼ら「放送人」たちは、戦争協力について煩悶したり懊悩したりするのですが、結局は、どうすれば国民を戦争に動員できるかという一点に向かっていくことになります。軍部や政府に屈服していったその道を「戦争だから仕方がなかった」と一言で片づけてしまいがちですが、違うのではないかと思います。彼らは「仕方なく」ではなく、全身全霊をかけて戦争協力に邁進したのです。