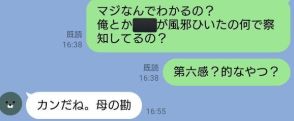乳幼児の血管炎「川崎病」 気を付けたい六つの症状は?…川崎富作博士が世界で初めて報告 新型コロナとの関連も議論
川崎病は乳幼児の全身の血管に炎症が起こる病気で、原因は不明だが治療法の進歩により後遺症の発症率は低下している。
主な症状や診断基準、川崎病とMIS-Cの関係、遺伝子との関係、治療方法や後遺症、通院の必要性について述べられている。
病気の来歴、発症年齢層、最近の罹患率の動向、新型コロナ禍への影響などが述べられている。
川崎病は、主に乳幼児の全身の血管に炎症が起こる病気です。日本人医師がこの病気を発見してから57年が過ぎました。今なお原因は不明ですが、治療法も進歩し、心臓の後遺症の発症率は低下しています。(中田智香子)
主な症状は〈1〉発熱〈2〉両目の白目の充血〈3〉唇が赤くなり舌にぶつぶつができる〈4〉発疹や結核予防ワクチン(BCG)接種痕が赤くなる〈5〉手足の先が腫れて赤くなる〈6〉首のリンパ節が腫れる――です。このうち「五つ以上当てはまる」か「四つ当てはまり、心臓の所見がある」で診断されます。それ以外で「不全型」と診断される場合があります。
病名は、1967年に小児科医の川崎富作博士(1925~2020年)が世界で初めて報告したことに由来します。1歳前後の発症が最多で、4歳以下の患者が9割近くを占めます。
何らかの感染症が引き金になっていると指摘されていますが、保育園などで広がることはないと考えられます。
1980年代頃の3度の大流行後、罹患(りかん)率は上がり続けました。
ただ、2020年は前年の3分の2程度に減りました。新型コロナウイルス対策の影響とみられています。
コロナ禍では、コロナ感染から2~6週間後に川崎病と似た症状が表れる「小児多系統炎症性症候群」(MIS―C)が欧米のアフリカ系やヒスパニック系の子どもに多く報告されました。一方、川崎病は日本など東アジアで患者が多く、関連が議論されています。
川崎病の発症のしやすさに遺伝子が関係していることも分かってきています。現状では「遺伝的な要因を持つ人に、感染や環境変化といったきっかけで、免疫が過剰に働いて血管炎を起こす」との説が有力です。
治療は、早く炎症を抑え、心臓を取り巻く冠動脈にこぶができる後遺症を防ぐことが目標です。治療法はかなり進歩し、後遺症が出る割合も2・3%(2021~22年)と、20年前から半減しました。
抗炎症薬のアスピリンを飲み、血液製剤である免疫グロブリンを1日で大量に点滴投与するのが標準治療です。
ただ、血液検査の結果などからこの治療が効きにくいと予測される場合は、免疫を抑えるシクロスポリンかステロイドを最初の治療から併用することが推奨されます。こうした患者は約3割いるとされます。
後遺症で冠動脈に大きなこぶが生じなければ、普通に生活できます。発症後5年間異常がなければ、通院も必要なくなります。
しかし、こぶが残ると、血栓ができやすくなり、心筋梗塞(こうそく)のリスクになります。定期的に通院し、血液をさらさらにする薬の治療を続ける場合もあります。大人になってもリスクに応じた生活の管理や経過観察のため、小児科から循環器内科への橋渡しが大事になります。
和歌山つくし医療・福祉センター(和歌山県岩出市)院長の鈴木啓之さんは、「治療成績はどんどん改善しています。発熱に加え、BCG接種痕や手のひらなどの赤みが見られたら、早めに受診してください」と話しています。