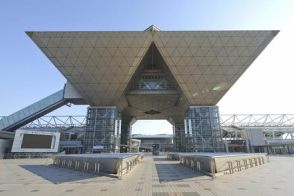僕がイタリアのコンパクトカーに乗る理由をお話します モータージャーナリストの島崎七生人がアバルト500e、フィアット500e、500 1.2に試乗
イタリア車に傾倒するモータージャーナリストが、アバルト500eとフィアット500eオープンの最新BEVと素の500についてレポートする。
500の魅力はタイムレスなデザインとイタリア車らしい走りの快活さ。アバルト500eはスペックが上がり、走りも刺激的で魅力的。一方、500eはEV化により機能や質感が向上し、日常での使い勝手も良い。
最終型のICE車、1.2リッター500も貴重でその乗り味に魅力がある。日本のコンパクトカーと比べても、イタリアの500にはQOLを高めたい思いが込められている。

フィアット500を都合2台乗り継いでいるモータージャーナリストの島崎七生人が、アバルト500e、フィアット500eオープンという最新のBEVの2台とかつて自身も乗っていた、いわば素の500についてリポートする。
◆イタリア車は空気のような存在
服装でよく選ぶのはアメリカン・トラッド、音楽はボサノヴァや“ベストヒットUSA世代”だから80年代のポップスも大好物で、それらを聴いている自宅のスピーカーは40年来愛用のアメリカのJBL。仕事で使うカメラはドイツのライカ(P社のOEM版だが発色はライカだと思う)、腕時計はスイスの旧ホイヤー、筆記具はドイツのラミー、バッグはアメリカのトゥミ、そして飼い犬は日本の柴犬……。改めて自分の身の回りを見渡すと、贔屓は必ずしもイタリア一辺倒という訳ではない。
が、クルマはある時からイタリア車にすっかり傾倒することとなった。これまで所有経験があるイタリア車はアルファ・ロメオが5台と、フィアットが3台。アルファ・ロメオは往年のヴィンテージ・モデルにお乗りの方の足元にも及ばないが、内訳は比較的近年の車種の164、GTV、156そして166で、いずれもあのジュゼッペ・ブッソのV6に惚れ込み新車で乗り継いだ。フィアットは最初はアルファGTVとの2台持ちで、成田への往復でスーツケースが載るように初代プントに乗り、次いで166との組み合わせで日本導入直後のボサノヴァ・ホワイトの500の1.2ラウンジへ。そして現在手元にあるのは、中古車で見つけ、乗り始めてかれこれ9年目となるツインエアで、限定車の500パンナだ。つまり今の500は2台目。話は少し逸れるが、気に入ると何度も乗るパターンは過去にもクラシック・ミニが2 台(加えてR50ミニも)、そしてアルファ166が2台という事例があった。
イタリア車以前の所有車はドイツ車と国産車だった(最初の愛車だったいすゞ117クーペからVW初代シロッコ、初代ピアッツァまでは強いて言えばG・ジウジアーロ、つまりイタリアン・デザインだった)。が、ある日突然イタリア車派に。ほんとうに何かの拍子で……といった感じで、明確なキッカケがあった訳ではなかったけれど、最初の164から数えて、かれこれ30年近く手元にある、空気のような存在だ。
そして乗るといつも五感を解ほぐしてくれる存在でもあるのが僕にとってのイタリア車でもある。ここ最近の本誌「大試乗会」でマセラティMC20チェロやフェラーリ・ローマなどの担当車に乗った際も、やはり運転席に座った瞬間からフウーッ! と温泉に浸ったオヤジのように気持ちが解されるのがわかった。そういうクルマとの距離感に加えて、デザインも走りも“冴えて”いる。溌剌としたスタイルや情感に溢れたエンジン・フィール、しなやかな足さばきが味わえるところが魅力なのだ……と思う。
◆自動車史に残るデザイン
ここでやっと本題のチンク(500)の話になるが、3代目モデルが日本市場に導入されたのは2008年3月。すでに16年も経った訳だが、まず何といってもチャーミングでタイムレスなこのクルマの姿形のよさは誰もが認めるところだろう。4代目のピュアEVの500eにもスタイルがほぼ受け継がれたことでも明らかだが、天が授けた唯一無二としか思えない愛着の持てるデザインは、登場以来、変わらずファンの心を掴んで離さない。
言ってみればAセグメントのただの実用車。けれどそこは欧州車らしく、小さくとも張りのあるボディ面はジドウシャとしてシッカリと見えるし、街中にポツンと停めておけば絵になる。それと老若男女の誰が乗ってもサマになるのも本物の実用車の証だろう。自分で乗っていながら言うのはいささか口幅ったいけれど、オリジンにあたるヌォーヴァ500と並び、自動車史に残るデザインになるはず、だ。
もちろんイタリア車らしい走りの快活さを楽しませてくれるのも500の魅力。とりわけ最新のアバルト500eはその最たる存在で、広告コピーのような言い回しだが、ピュアEVでありながら刺激に満ちた走りを堪能させてくれる。このモデルで「そう来たかぁ」と思わせられるのは“レコルド・モンツァ”を引用してきたこと。このレーシング・カーに由来し、ICE車の595コンペティツィオーネでは標準装着(もちろんリアルなマフラーだ)されたアバルトの象徴的なサウンドを、リア床下に仕込んだ耐水性のある200mmウーファーから鳴らしてみせるという仕掛けである。走行前にオン/オフが選択可能で、オンで走り出すと街中ではいささか気恥ずかしくもあるが、オープン・ロードで楽しむ分には加減速に音がリンクし気分を盛り上げてくれることは確か。
クルマそのものはベースの500eに対しスペックが上げられていて、57:43の前後重量配分ということもあり、運転の仕方次第でいくらでもクイックでヴィヴィッドな走りが楽しめる。しかも乗り心地は、初期のICE車のアバルト500の頃のハードさに較べたら、十分に実用的だ。
いっぽうの500eは、まさに500の新境地を拓いたといえるクルマだ。魅力なのは、それまでのガソリン車のチャーミングな世界観を大枠で守りつつ、ピュアEVになったと同時に実は機能も質感もより進化させた点。とくにADAS関連の機能が一気に充実したり、カーナビが標準となったりしたことは、従来のICE車のオーナーにとって羨ましい限り、だろう。もちろんEV化によりNVHなど走りの快適性も格段に高められた点も見逃せない。一充電走行距離335kmのスペックは、実際にはその7~8割としても、日常の中で乗ってみてもまずまず実用的で、ガソリン・タンク容量35リッターのツインエアを日常の足にする僕など、習慣的に残量が半分程度になると給油しており、ガソリン・スタンドに立ち寄る頻度は割と高いが、500eで自宅以外で充電をする使い方なら同程度といった感覚か。標準で備わるCHAdeMO用の充電アダプターがいかにもゴツくて重たく、スマートなイタリア車に似つかわしいとは思いにくいが、こればかりは致し方なしといったところ。それと車名が単に“500eオープン”となり、以前のように「チンクエチェント・チ」と呼べなくなったところがやや残念?
だが、いずれにしろロゴをちりばめたソフト・トップや撮影車のボディ色は、イタリア車ならではのセンスだ。
そしてもう1台の1.2は、ICE車の最終型となる貴重な1台(国内の在庫はまだ十分にあるとのことだが、ともかくなくなり次第終了という)。実は撮影車は直近のクルマではあったが、最終型では備わる運転席ハイト・アジャスターがなく、タイヤも最終型は15インチのようだが、500に最良と思われる14インチを装着していた。このため今回のロケでも変わらずホッコリとした乗り味が試せたほか、エンジン特性がピーキーなツインエアより遥かに穏やかな1.2リッターの味わいが再確認できた次第。パワーはそこそこだが、これはこれで乗りやすく、2ペダル・シングル・クラッチ式自動MTのデュアロジックへの負荷の小ささも安心材料であるはずだ(ツインエア+デュアロジックのトラブルを僕は何度となく経験してきた)。ピュアEVが登場した今でも、気安く乗れるコンパクトカーとしての価値は薄れていない。
軽自動車を含めた日本のコンパクトカーは優秀だ。が、それを承知の上でイタリアのコンパクトカーの500に食指を動かそうとする行為。そこにはやはり気持ちの上でのQOLを高めたい、充足させたい、朗らかに暮らしたいという思いがあるからにほかならないのだと思う。
文=島崎七生人 写真=神村 聖
(ENGINE2024年8月号)