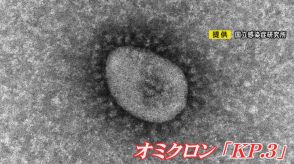いま、文学を「体験」することの可能性とは? 青春小説にして異色のロシア文学入門の一冊を読む。
奈倉有里さんの『ロシア文学の教室』は、戦争の時代を考えさせる青春小説であり、奇抜な授業を通じてロシア文学に触れる内容を描いている。
授業では、枚下先生が学生たちに作品を「体験」することを求め、作品に没入して主人公や環境になりきる体験を通じて文学の魔法を表現している。
読書を通じて作品の世界に没頭し、自分になりきる経験は、文学の持つ力を体現しており、本書はその魅力を読者に再体験させている。

戦争のさなかで文学を学ぶことになんの意味があるのか? 社会や愛をどう語れるというのか? 読者を作品世界にいざなう不思議な「体験型」授業を通じて、この戦争の時代を考えるよすがを教えてくれる青春小説にして異色のロシア文学入門。奈倉有里さん『 ロシア文学の教室 』を芥川賞作家で早稲田大学教授の小野正嗣さんが読み解く。
◆◆◆
文学を語るのは楽しいことだ。ところが授業や教科書という枠組みに入れられると、とたんにつまらなくなってしまう気がする。学問として教えることに向かないのではないか。文学の研究書・論文は、専門家たちの知見を広げ深めることには役立っていても、むしろ一般の読者を文学から遠ざけているのではないか。大学で文学を教えながら、そんな不安に駆られることがある。
そんなとき、興味深い授業が行なわれていることを知った。しかもロシア文学について。それが本書『ロシア文学の教室』である。どんな授業がなされているのか早速覗いてみた――。
ユニークな本だ。研究書とも文学エッセイとも違う。これは都内の大学でロシア文学を学ぶ学生たちの授業の様子を描いたフィクションである。授業では、主に十九世紀のロシア文学を対象に毎回一作品が取り上げられる。ゴーゴリの『ネフスキイ大通り』から始まって、トルストイの『復活』まで十二作品が扱われるラインナップ。授業は学生の積極的な参加が期待される少人数の演習形式である。
では授業を担当する二メートル近い巨漢の枚下先生は、学生たちに何を求めているのだろうか。課題作品を読んで内容をまとめ、関連する事実を調べて発表?
違うのだ。枚下先生が、湯浦、新名、入谷といったカタカナで表記すればロシア人の名前(ユーラ、ニーナ、イリヤ)に聞こえる学生たちに望むのは、作品を「体験」することなのだ。
では作品を「体験」するとはどういうことなのか。
たとえば、本作の主人公湯浦葵がチェーホフの短編を読むとき――「さて枚下先生が好きなのはどんな作品だろうとプリントを覗く。とたんにプリントの余白がすうっと陽の光に、文字が緑の葉になり、行間には川の清流が流れはじめる――」。湯浦は気づけばチェーホフの『コントラバス物語』の登場人物になっている。「僕はコントラバスを背負い、燕尾服にシルクハットをかぶって小川沿いの道を歩いている」。ゴーゴリの『ネフスキイ大通り』を開けば、夕暮れのネフスキイ大通り――「黄昏が家々や街路の上に降りてきて、点灯夫がはしごにのぼって街灯に火をともしていくころ、ネフスキイはふたたび活気づきはじめる」――に連れて行かれる。ネクラーソフの『ロシヤは誰に住みよいか』を読めば、すでにロシアの農民たちの暮らしのただなかにいる――「僕たちはだだっ広い田舎道にいた。踏み均された道沿いには距離を示す木の柱がぽつりぽつりと一定間隔で立っていて、道端にはごぼうのような草が茂っている」。
この「体験」とは、そう読書に夢中になっているときに私たちの誰もが経験していることだ。現実が遠景に退いていき、作品のなかに吸い込まれる。主人公に、あるいは脇役だろうが心惹かれる人物に感情移入し、その視点から世界を眺め、気づけばその人になりきっている。いや人だけではない。動物や植物や石にだってなりうる――ガルシンの植物たちが主人公となる短編を読んだときに、つる草として物語を「体験」した湯浦のように。物語を通じて、私たちは自分にあらざるものになる。本書は物語の持つこの魔法を、湯浦を通して私たちに追体験させてくれる。