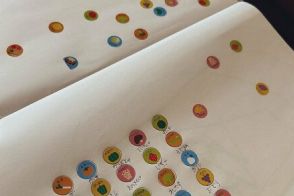沙に囲まれた残酷な世界が私たちの社会を浮かび上がらせる。期待の作家が令和の世に送り出す、新たな青春のバイブル!
鯨井あめさんの最新作『沙を噛め、肺魚』はディストピア小説であり、安定を求める世界に生きる若者たちの物語を描いている。
物語は、音楽が好きな少女と将来に悩む少年の二人の視点から展開され、生命の源としての水や魚の象徴が重要な役割を果たす。
著者の独自の表現力とストーリーテリングによって、読者は水の重要性や生きる意味について考えさせられる作品となっている。

『晴れ、時々くらげを呼ぶ』で第14回小説現代長編新人賞を受賞し、文芸の最前線に立つ若手作家としていま最も注目を集めている鯨井あめさん。
そんな鯨井さんが1年ぶりに世へと送り出す待望の新作『沙を噛め、肺魚』が、5月29日に発売されました。
鯨井さんにとって初めてのディストピア小説でもある本作を、書店員歴30年、「POP王」としても名高い内田剛さんはどう読み解くのか?
今回はその書評を公開します。
----------
鯨井あめ『沙を噛め、肺魚』
沙に覆われてしまった世界。人々は何よりも安定を目指すようになっていた。
安定した仕事で稼いで、機械で娯楽を享受して、どこに遠出することもなく、安全で、快適な、この街で、ささやかな幸せが至上。
それでも音楽が好きな少女・ロピは第9オアシスでパパと二人で暮らしている。親友のエーナや周りの大人に反対されながら、自分の音楽を追い求める。
特にやりたいこともない少年・ルウシュは、母と同じ気象予報士になるため日々勉強していた。いっぽうで好きなことに一生懸命な友人に劣等感は強まり、夢中になれることを探しはじめ……
青春小説の旗手が将来に悩むZ世代に捧ぐ、傑作のディストピア長編。
----------
読み終えてしばらく放心状態となった。いや、「読む」というよりは「感じる」文学だ。これほどまでに書き手の肉声が、直接に聞こえる物語は稀有なのではないだろうか。そして、この物語に込められた「想い」は尋常ではない。気鋭の著者・鯨井あめが辿ってきた文学世界を凝縮させた、集大成的な作品であると同時に、表現者としての並々ならぬ決意と覚悟が伝わる一冊なのである。
まずは、印象深く力強いタイトルから引きこまれる。「砂」ではなく「沙」であることにも注目したい。敢えて「さんずい」の「すな」。そこには紛れもなく「水分」がある。いうまでもなく人間の身体の大部分は水でできている。ただ直向きに生きるために流される「汗」、喪失の哀しみや孤独の苦しみに流される「涙」、そして世代を超えて受け継がれる「血」。とにかくこの物語は水分の量が実に豊富なのである。
さらにその水の存在を際立たせているのが、圧倒的な「沙」なのだ。強烈な乾きがあるからこそ、より尊く感じられる瑞々しい潤い。貴重な水をミストのように全身に浴びることによって、世界を覆いつくす沙を洗い流す。まさに比類なき読書体験ができるのだ。
水に関する話題で、もうひとつ重要な点は、生命の源が「母なる海」にあることだ。作中では「白い沙、石英の粒は海から現れた」とあり、無機質な沙までをも生みだす場所として描かれている。海は穏やかな表情を見せれば、荒々しく怒り狂うこともある。命を呑みこむような恐ろしい存在でもあるのだ。しかしそんな危険な面も、輪廻転生の中では必要だ。優しくあれば厳しくもある。それが自然の摂理でもあるのだろう。
この物語は生きることの「原点」、そして生きていくうえでの「原動力」を感じさせるのだが、それらを紐解けば、大地から湧き上がり、また天空から降り注ぐ「水」に行き着くのである。そして水を得た「魚」が登場するのも必然の成り行きであろう。それも「肺魚」とは、よくぞ見つけてきたものだ。その意味するところは作品の中で知っていただきたいが、著者の比類なき才能とセンスには驚かされるばかりだ。