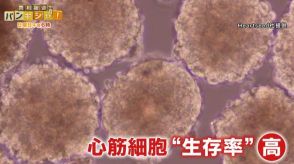「余命半年だったけれど、2年も生きている」腫瘍内科医が語る、医師宣告の余命宣告が当たる驚愕の確率
がんに関する誤解と緩和ケアの重要性
緩和ケアは治療と並行して行うべき重要な治療の一つ
緩和ケアはQOL向上や延命効果が期待できる
■最後までがんと闘うから最期に苦しんでしまう
がんに関して誤解をしていたり正しい知識がないせいで、必要以上に恐怖を感じたり絶望的になったりする人が多いように思います。そのようながんに関する誤解の一つに「緩和ケア」への誤解があります。
緩和ケアというと、治療が行き詰まった患者に対して行われる最後のケアのように受け取る人がまだまだ多くいます。しかし、緩和ケアは「治療か緩和ケアか」という二者択一のようなものではありませんし、もちろん死の宣告のようなものでもありません。
そうではなく、本来ならば積極的な治療(手術、放射線治療、抗がん剤治療)と並行して行うべきものです。このことは、がん対策推進基本計画にも「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が明記されています。
実際に、2010年には早期から緩和ケアを受けることが延命にもつながると「ニューイングランド/ジャーナル・オブ・メディシン」という世界で最も権威ある医学雑誌の一つで発表されました。手術が難しい進行性の肺がん患者に対して、抗がん剤治療のみを受けていたグループと、抗がん剤治療に加えて月に一度、外来で緩和ケアを受けたグループを比較したところ、緩和ケアを受けていたグループのほうが、生存期間が2.7カ月も延びたのです。
たった2.7カ月と思う人もいるかもしれませんが、世界初の免疫治療薬として承認され、「夢の新薬」と言われたオプジーボの肺がんに対する生存期間の延長が2.8カ月とされています。単純比較はできませんが、緩和ケアが抗がん剤と同じような治療効果をもたらす可能性があると示されたのは、非常に画期的なことです。この結果から考えれば、緩和ケアは手術、放射線治療、抗がん剤治療に続く第4の標準治療と言っても過言ではないのです。
では緩和ケアとは具体的に何をするか。もちろん、「症状を緩和すること」も大切ですが、がん治療と並行して行う緩和ケアでは、「信頼関係の構築」から始まり、「病状の理解」「治療の意思決定支援」「終末期の話し合い」なども大切とされています。これらのことは、「人生会議」と言って、人生の最後をどのように過ごしたいかを元気なうちに考えておこうというのが目的です。つまり、患者が自分の病状を適切に理解できるようサポートして、抗がん剤治療や緩和ケアなどの選択肢から適切に選べるように支援することが緩和ケアの役割なのです。
どこで亡くなるのが最もQOL(生活の質)が高かったかを遺族にアンケートした調査では、最もQOLが高いのは自宅、次が緩和ケア病棟、最も低いのが病院死という結果になりました。緩和ケア病棟に行くというともう何もしてもらえないと感じる人がいますが、苦痛を取り除いてQOLを大切にして過ごせる場所が緩和ケア病棟です。それにもかかわらず、日本ではいまだに病院死が最も多くなっています。これはがんの病状や緩和ケアに関する正しい知識が知られていないからです。
ほかにも知っておいてほしいこととして、脳卒中や心不全などの慢性疾患や認知症、老衰が右肩下がりで徐々に体の自由が利かなくなっていくのに対して、がんの患者は亡くなる直前までは普段とあまり変わらず過ごせるということが多いです。個人差はありますが、亡くなる1カ月くらい前までは比較的元気で、一旦症状が出ると、階段を転げ落ちるように全身状態が悪化していきます。それを知らないと、抗がん剤治療などの積極的治療で効果が得られなくなった時期が来た後も体は元気だから、治療の終了をなかなか受け入れられない。ゆえに、死ぬギリギリまで抗がん剤を使って非常に辛い思いをすることになるのです。医師から標準治療の終了を告げられても「自分はこんなに元気なのに、治療できないはずはない」と納得できず、最後の最後まで抗がん剤を使ってしまうのです。
標準治療が終了した後に抗がん剤を使用しても延命効果は期待できません。この時期に無理に抗がん剤を使うことは過剰医療につながり、不要な苦しみが増すだけです。標準治療が終了した後は、むしろ緩和ケアを受けたほうがQOLの向上や場合によっては延命効果が期待できます。この点を知らない患者が非常に多いのです。