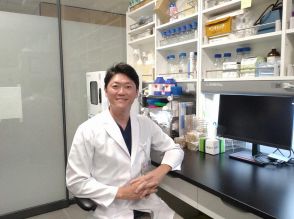「iPS創薬」ALS進行抑制の鍵に、遺伝子情報利用で病気再現 試薬の効果高まる
京都大などの研究チームがALSの治療法として白血病の薬を使用し、病状の進行抑制を確認した臨床試験の結果が発表された。
病気を再現したiPS細胞を用いたiPS創薬の手法により、既存の薬の中から有望な薬を発見し、治験を進めている。
ALS治療薬としての承認を目指し最終段階の治験を検討する一方、ALSの社会認知度向上と治験参加患者の確保が課題となっている。
難病「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」の新たな治療法を巡り、京都大などの研究チームが12日、白血病の薬を患者に投与し病状の進行抑制を確認したとする臨床試験(治験)の結果を発表した。鍵になったのは、人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使って既存薬の中から有望な薬を見つける「iPS創薬」という手法。既存薬は安全性が検証済みで実用化までのハードルが比較的低く、患者の治療への迅速な活用が期待されている。
iPS創薬は、患者から提供を受けた血液や皮膚の細胞からiPS細胞をつくり、神経などの細胞に成長させて病気を再現。薬剤を投与して効果があるものがないか網羅的に調べる手法だ。患者の負担も小さく、一度にさまざまな化合物を試すことが可能になる。
京都大の井上治久教授らの研究チームは、ALS患者の細胞から作製したiPS細胞を使い、病気を起こす神経細胞を体外で再現した。既存薬の投与などを通じ、慢性骨髄性白血病の治療薬「ボスチニブ」に効果があることを発見し、将来的な治療薬候補として治験を進めてきた。
井上氏によると、iPS創薬の最大の利点は、患者の細胞由来のため本人の遺伝情報を利用できること。本人の病態により近い形で薬の作用を試すことが可能となり、今回の研究でも症状の個人差を忠実に反映させた。目的の細胞は、ほぼ無限に作れるため、多種多様な薬を試すこともできたと説明した。
今後、ALS治療薬としての承認を目指し、最終段階の治験を検討する研究チーム。一方で、国内のALS患者数は約1万人とされ、治験に参加できる患者を確保することが急務となる。
日本ALS協会の伊藤道哉副会長は「iPS細胞をはじめとしたさまざまな先進的な研究が創薬に結びつくことを患者は切に願っており、期待は大きい」と述べた。
ただ、ALSそのものの社会認知度が低いことに関係者は危機感を持つ。研究チームのメンバーで徳島大の和泉唯信(いずみ・ゆいしん)教授は「ALSという病気を知っていただき、治験を速やかに実施することが課題だ」と話した。(木下倫太朗)