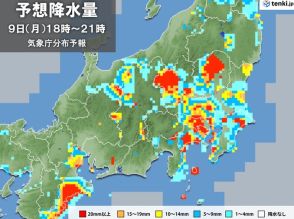判事の前でストリップショー!?「わいせつか芸術か」踊り子の芸をめぐる論争に終止符を打つ驚きの秘策
1960年代ストリップの世界で頂点に君臨した伝説のストリッパー、一条さゆり。彼女の人生や昭和の時代の流れを探る。
公然わいせつ控訴審裁判で、一条さゆりの芸が芸術かわいせつかの論争が展開された。芸術性と社会的価値が問われた。
裁判では、他の文学や映画作品の問題点も取り上げられ、芸術とわいせつの狭間で議論が行われた。

1960年代ストリップの世界で頂点に君臨した女性がいた。やさしさと厳しさを兼ねそろえ、どこか不幸さを感じさせながらも昭和の男社会を狂気的に魅了した伝説のストリッパー、“一条さゆり”。しかし栄華を極めたあと、生活保護を受けるに至る。川口生まれの平凡な少女が送った波乱万丈な人生。その背後にはどんな時代の流れがあったのか。
「一条さゆり」という昭和が生んだ伝説の踊り子の生き様を記録した『踊る菩薩』(小倉孝保著)から、彼女の生涯と昭和の日本社会の“変化”を紐解いていく。
『踊る菩薩』連載第55回
『まさしく芸能界の「闇」...警察が伝説の踊り子を“狙い撃ち”した裏にあるヤバすぎる理由』より続く
裁判のもう一つの争点は、「わいせつか芸術か」だった。性を表現した文学や演劇、映画を巡っては、しばしばこの論争が起きてきた。
英作家、D・H・ローレンスの小説『チャタレー夫人の恋人』、武智鉄二監督の映画『黒い雪』、永井荷風の小説『四畳半襖の下張』。それらの出版や上映では、責任者が罪に問われてきた。一条の公然わいせつ控訴審裁判で、弁護側は『悪徳の栄え』事件を紹介している。
これは18世紀に生まれた仏作家、マルキ・ド・サドの長編小説『ジュリエット物語又は悪徳の栄え』の翻訳を巡る事件だった。この作品には虐待シーンも多く、彼の名から「サディズム」の言葉が生まれた。近親相姦などのタブーについても描かれ、サドはナポレオンの命令で逮捕されている。
日本で翻訳出版されたのは1959(昭和34)年。激しい性描写が問題になり、翻訳者と出版者がわいせつ物頒布罪に問われた。最高裁は69年、「芸術的・思想的価値のある文書であっても、わいせつ性を有すると考えることはできる」として有罪(罰金刑)を言い渡した。
注目されたのは5人もの判事が反対意見を表明したことだ。わいせつ性と芸術性を巡り最高裁内にも、意見の相違があった。反対意見の一つは、「思想性、芸術性での社会的価値が、わいせつ性という反社会的価値を上回る場合、可罰性がない」とする考えだった。一条の弁護団もこの意見を取り上げながら、彼女の芸に罪はないと主張した。杉浦はこう説明する。
「一条さんは閉じられた空間で裸になり、客はカネを払って、それを見るわけです。公園や道ばたで裸になっているわけではない。観客は彼女の艶やかな、磨きのかかった演技を見て、日々の雑事を一時忘れる。社会的価値が大きいと考えるべきです」
一条の舞台は、社会的価値と反社会的価値のどちらが大きいか。わいせつかどうかを決めるには、その点を確認する必要がある。
弁護側は、「照明や音響、舞台と客席の距離など同じ条件で一条の芸を見てもらい、わいせつではないと知ってほしい」と裁判官に求めた。確かに、小説のわいせつ性を判断する場合、その作品を読んだうえで議論されるだろう。同じように一条の「芸」を裁くなら、その実態を知る必要がある。検察側も実演を了承した。