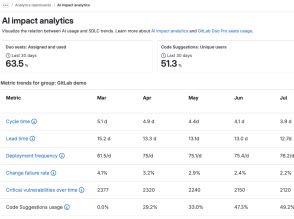「デザインの技術がAIに奪われる世の中がもうすぐやってくる」デザイナー片山正通の頭の中
デザイナー・片山正通のデザインの源泉や原動力について語られる。
片山のアプローチやクライアントとの関係性について紹介される。
将来の展望やデザインに対する姿勢、今後挑戦してみたい分野について語られる。

世界中のクライアントから厚い信頼を得ているデザイナー・片山正通。そのデザインの源泉や原動力となるものを探る。片山が愛してやまないものやこと、そして今後の展望について話を聞いた
片山は“遊びの誘いに乗る”と表現したが、クライアントからは、リサーチの段階から非常に丁寧な対話を重ね、詳細な模型をつくって最適な解決方法を見いだしてくれるデザイナーとして評価が高い。
「実は僕自身にはやりたいことがないんです。それよりクライアントと方向性について話をしながら謎解きするのが好き。僕が欲しいものではなく、クライアントの将来に向けた経営資源をつくるのが仕事ですから。リサーチし考え抜いてコンセプトをつくり、そのアウトプットとしてのデザイン検証を繰り返す。その一連のプロセスが僕にとって遊びなのです。相手を理解したいから、時には一緒にライブや美術館にも行くし、わからないことは調べる。単純に自分が出す回答が正しいのかどうか、不安だから検証する。曖昧な情報ではクライアントとシェイクハンドできないから、目に見える形を綿密な模型で示すのは当たり前のこと」
片山がつくる空間はクライアントごとの世界観を表現して、ひとつとして似たようなものがないのも特徴だ。その引き出しの多さを支えるのは、2017年に東京オペラシティ アートギャラリーで開催された展覧会『片山正通的百科全書 Life is hard... Let’s go shopping.』で披露した膨大なコレクションかもしれない。オフィスにあるのはそのほんのごく一部だとか。
「仕事のためではなく、モノや知識との出会いを大事にしています。面白そうと思ったら足を運び、手に入れて、その背景をちょっと調べてみる。骨董、ヴィンテージ家具、現代アートなど、好奇心と欲望に忠実に、借金してでも買う時期もありました。無駄なものだらけですが、膨大な無駄の蓄積が、あるときデザインを奏でてくれることがある。あまりのレンジの広さに我ながら節操ないと思うけれど、開き直っています。自分の中で趣味嗜好をまとめず、研ぎ澄まさず、ぐちゃぐちゃのままでいたい。それは子どもの頃のデパート好きもひとつの理由かもしれません。あそこには食品から洋服、インテリア、ペットショップ、食堂、屋上遊園地までなんでもあるでしょ」
フットワーク軽くライブに行き、人と出会い、時間を見つけては映画館へ通う(一人で!)。アート、音楽、ファッションと業界を分断せずに、それぞれの分野の人をつなげる架け橋のような役回りも好きだという。
「きっと、『Wonderwall®みたいな仕事』とパソコンに入力すれば、AIがそれらしいデザインを簡単にはじき出す世の中がもうすぐやってくると思うのです。デザイナーの仕事自体がなくなるのではないかという危惧もあります。だから僕はプロジェクトの初期段階から関わり、対話をし、人と人をつなげ、必要な配役を集めて面白いものにしていくのが役目だと思っている。その部分さえAIが肩代わりできるかもしれないけれど、AIではバグは起きない。デザインにとってバグやノイズは絶対必要なものだと思っているので、そういうものを残せるデザイナーでありたいですね」
最後に、今後デザインしてみたいものを聞いてみた。
「学校や病院などの公共施設ですね。単に見た目を格好よくしたいのではなく、よりよく機能させるための正しい答えをデザインの力で導き出したい。渋谷区の公共トイレをデザインする『The Tokyo Toilet』のプロジェクトに参加したのは、その足がかりになったかもしれません。インテリアデザインがクリエイティブな形で社会問題を解決し、人々の役に立つこともできるということを、若手デザイナーやデザインを学ぶ学生たちに見てもらいたいと思うのです」
片山正通(かたやま・まさみち)
1966年岡山県生まれ。2000年Wonderwall®を設立。ファッションなどのブティックからブランディング・スペース、大型商業施設の全体計画まで、世界各国で多彩なプロジェクトを手がける。コンセプトを具現化する際の自由な発想、また伝統や様式に敬意を払いつつ現代的要素を取り入れるバランス感覚が国際的に高く評価されている。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科でゼミを担当。各界の多彩なゲストを招いた特別講義の内容は書籍にもまとめられている。www.wonder-wall.com
TEXT BY MARI MATSUBARA, EDITED BY MICHINO OGURA