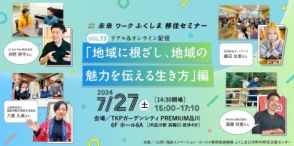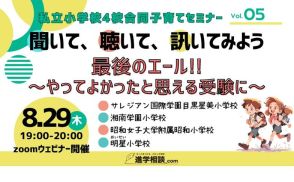「岩にしみ入る蝉の音」はどんな鳴き声だったのか…松尾芭蕉の有名な俳句を巡っておきた大論争の結末
芭蕉の俳句「閑さや岩にしみ入る蝉の声」で詠まれたセミの種類について、アブラゼミとされていたが、現在はニイニイゼミとされている経緯が述べられている。
ニイニイゼミはこの俳句で詠まれたセミの種類であり、アブラゼミとの議論があったが、現地調査や季節の観察からニイニイゼミであると結論付けられている。
芭蕉はこの俳句で、セミの鳴き声と岩の静寂を通じて「動と静」「生と死」の対比を表現し、17文字の中に無限の世界を描いている。
「閑さや岩にしみ入る蝉の声」。この俳句で詠まれたセミの種類は何だったのか。生物学者で歌人の稲垣栄洋さんは「アブラゼミという説もあったが、現在ではニイニイゼミと考えられている」という――。(第2回)
※本稿は、稲垣栄洋『古池に飛びこんだのはなにガエル?』(辰巳出版)の一部を再編集したものです。
■この句で詠まれたセミの種類とは
閑さや 岩にしみ入る 蝉の声 松尾芭蕉
前項のように松尾芭蕉の有名な俳句「古池や蛙飛びこむ水の音」のカエルはツチガエルであった。
それでは、この句で詠まれているセミは、どんな種類のセミなのだろう。
歌人の斎藤茂吉は、この句で詠まれたセミはアブラゼミだと断定した。
アブラゼミは、ジージーと鳴く。アブラゼミは、まるで油を揚げるような音であることから、「油蟬」と名付けられたとも言われているセミである。
ところが、斎藤茂吉の説をきっかけにして、この句で詠まれたセミの種類について松尾芭蕉大論争が起こった。
そして、夏目漱石門下で文芸評論家の小宮豊隆は、この句のセミはアブラゼミではなく、ニイニイゼミであると反論したのである。「『閑さや岩にしみ入る』という表現にアブラゼミは合わないこと」、「アブラゼミは季節が合わないこと」がその根拠である。
この俳句が詠まれたのは、元禄2年5月27日のことである。これは西暦では、1689年7月13日になる。
そして、この俳句が詠まれたのは、山形県の立石寺である。
東北地方の山形県では7月13日にアブラゼミはまだ鳴いていないというのだ。
■「ミンミン」でも「ツクツクボウシ」でもない
斎藤茂吉は、現地調査を行ない、7月13日に、まだアブラゼミが鳴いていないことを確認した。そして、誤りを認めて、芭蕉の句のセミはニイニイゼミであることを認めたのである。
現在、この俳句で詠まれたのはニイニイゼミであると結論づけられている。
ニイニイゼミは梅雨の時期から、他のセミに先駆けて鳴き始める。
ミンミンゼミはミンミンと鳴く。ツクツクボウシはツクツクボウシと鳴く。ニイニイゼミの名前も鳴き声に由来すると言われているが、ニイニイゼミの鳴き声はニイニイとは聞こえない。ニイニイゼミは、「ヂー」という感じの鳴き声である。そのニイニイゼミの声が岩にしみこんでいくようだと詠まれているのだ。
セミがしきりに鳴いているのに、芭蕉は「閑さや」と詠んだ。
「古池や蛙飛びこむ水の音」の俳句では、水の音を詠むことで、飛び込んだ後の静けさが際だった。
「閑さや」の句でも、芭蕉は鳴きしきるセミの鳴き声の中にこそ、他の音がない静かさを感じたのだ。
■17文字の中にある「動と静」「生と死」
この俳句で、芭蕉は鳴いているセミと岩の静寂の「動と静」の対比を詠んでいる。
セミは短い命の象徴である。セミは生きている。その声は岩にしみこんでいる。岩は生きていないものの象徴だ。つまりは「生と死」の対比でもある。
芭蕉はたった17文字の中に「動と静」「生と死」という無限の世界を表現したのだ。
しかも、セミの声が静けさを表わし、セミの声は岩にしみこみ、「動と静」「生と死」は溶け合っていく。何という世界観なのだろう。
もっとも、山寺という場所を訪ねてみると、その世界観はごくごく当たり前のことのようにも感じられる。
山寺の名で知られる山形県の立石寺は、けわしい山中に寺が開かれ、切り立った絶壁に多くのお堂が建てられている。まるで、この世のものとは思えない別世界である。芭蕉が詠んだのは、まさにこの不思議な世界観だったのだ。