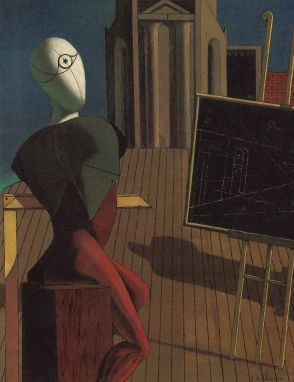人生の究極の目的とは、人の心に耳を傾け、世界の鼓動やため息や夢を聞き出すこと
ドストエフスキーの作品を引用しながら、宗教や永遠についての深い考察を交わす釈徹宗氏と若松英輔氏の書簡。人々は宗教や神とは別に永遠を求めているという論点を提示し、ドストエフスキーの影響を取り上げつつ、愛や聖性というテーマについて探求している。
ドストエフスキーの作品が神学や哲学の新たな視点をもたらし、人間性と神の関係について深い洞察を提供したことを紹介。聖性や愛といった概念が人間本来の問題を含み、解明されるべき秘義であることを指摘。
「愛」や「慈悲」といったキーワードから、聖性や神への尊敬を喪失することで聖性の概念が希薄化する危険性について考察。愛と聖性の関係についての議論が期待される。

----------
浄土真宗の僧侶にして宗教学者の釈徹宗氏。批評家・随筆家にしてキリスト者の若松英輔氏。「信仰」に造詣の深い当代きっての論客二人が、「宗教の本質」について書簡を交わす本連載。釈氏の「境界と聖性」をテーマにした前回の書簡(第九信・A)に対する、若松氏の返信を公開する。(本記事は、「群像」2024年6月号にも掲載されています)
----------
第九信・Aはこちら
お手紙を拝見しました。釈さんの書かれた言葉を読んでいると、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』に記されている、ある言葉が想起されてきました。あの兄弟の次男イワンが「永遠」を論じることをめぐって、次のように述べているのです。
神を信じない連中にしたって、社会主義だの、アナーキズムだの、新しい構成による全人類の改造だのを論ずるんだから、しょせんは同じことで、相も変らぬ同じ問題を論じているわけだ、ただ反対側から論じているだけの話でね。つまり、数知れぬほど多くの、独創的なロシアの小僧っ子たちのやっていることと言や、現代のわが国では、もっぱら永遠の問題を論ずることだけなんだよ。そうじゃないかね? (原卓也訳)
ここで述べられている「社会主義」や「アナーキズム」は、非宗教的思想の代名詞です。つまり、「神」は存在しないといわなかったとしても「神」を第一の関心としない人々であると理解してよいと思います。しかし、そうした人たちもどこかで「永遠」を探究している。希求している、というべきなのかもしれません。人は、問題としての「宗教」、あるいは「神」から離れることはできる。しかし、「永遠」を封印することはできないというのでしょう。
ドストエフスキーの登場によって、神学、哲学、文学をめぐる大きな変動が起こりました。それまでは神学者が、あるいは哲学者が論じていた問題が、この大きな小説の中で、神学者や哲学者を驚かせるような深度で描かれている。そう感じた人は少なくありませんでした。ニーチェがドストエフスキーのよき読み手だったのも偶然ではありません。遠藤周作の師である哲学者の吉満義彦が、ドストエフスキーをめぐって次のように述べています。「ベルジアエフ」(ベルジャーエフ)とは『ドストエフスキーの世界観』の著者でもありました。ロシアに生まれ、共産主義下のロシアを追放され、フランスに亡命した哲学者です。
ベルジアエフも言うごとくドストエフスキーの問題の深さはダンテやシェークスピアの解しなかったような仕方をもって人間性自身の問題の中に神自身の問題を見いだし人間の問題は神の問題なしに理解し得ないことを指摘した点にある。(「ドストエフスキー『悪霊』について」『文学者と哲学者と聖者 吉満義彦コレクション』)
ここで吉満がいう「神自身の問題」とは「聖なるもの」であり、「愛」でもある。ドストエフスキー、あるいはベルジャーエフ、そして吉満の経験によれば、人間とは何かを問うことは、聖性と愛の秘義─秘められた意味─を解き明かそうとすることだというのでしょう。「愛」あるいは「慈悲」といってもよいかもしれません。この問題は、ぜひ、どこかでふれさせてください。「愛」を見過ごした「聖なるもの」は、力を失った聖性という概念になる危険があります。

![スバルのDNAはゼロ戦から受け継がれている!! 零式艦上戦闘機52型の勇姿にシビレた!![復刻・2013年の話題]](/img/article/20240623/66772e271ba49.jpg)