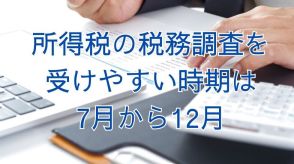節税のチャンピオン〈タワマン税制〉も終了、永遠ではない税制のなかで「節税目的で不動産投資」をすることが“本質を欠いている”と考えるワケ【不動産投資のプロが解説】
節税目的で不動産投資をする際には、減価償却費を上手く活用することがポイントとされています。しかし、それだけに囚われず、本来の意味や不確定要素を考慮する必要があります。
減価償却による節税は、税務上の損失を他の所得から控除することで実現されるケースが一般的です。減価償却費を使って収益との調整を行う仕組みが節税効果を生む仕組みであることが説明されています。
物件の価値が右肩下がりの場合には減価償却による節税効果が発揮されますが、価値が上昇している場合には事情が異なり、利益として計上される可能性があることが説明されています。

「減価償却費を上手く活用することで節税できる」として、節税目的で不動産投資をするケースは少なくありません。しかし実際のところ、減価償却による節税を実現するにはいくつもの前提をクリアする必要があり、不確定要素も少なからず残ります。税金を納める本来の意味を考えても、節税だけに囚われて不動産投資をするのは、本質を欠いた行いではないかと語るのは、株式会社プラン・ドゥの代表・杉山浩一氏です。今回は、杉山氏の著書『新富裕層のための本質的不動産投資』(明日香出版社)より一部を抜粋し、減価償却による節税に関する杉山氏の考えをご紹介します。
節税には大きく言って、2つのケースがあります。1つ目は、税務上の損金が収益を上回った場合に、その超過損失部分を、他の所得から控除することができるといったケースです。
不動産投資による損失を、それ以外の業務の所得によって穴埋めすることで、当該業務の所得が減少し、税金が減ります。この場合の損金のほとんどが、減価償却によって発生しています [図表1]。
正確に記載すると、「減価償却費」とは、減価償却資産(建物・附属設備)の取得に要した金額を、一定の方法によって、各年分の必要経費として配分する際に使用する勘定科目のことです。
そして、減価償却の基本的な考え方は、得られた収益に対応した支出のみを費用として計上するという「費用収益対応の原則」に基づいています。
物件を購入した年に、一括して費用を計上してしまうと、実際にその建物から複数年にわたって得られる収益を正確に会計へと反映させることができません。毎年の家賃収入を、購入した年に、正確に一括計上するというは物理的にも困難と言えるでしょう。
そのため、物件の取得価格を、建物の使用可能期間(減価償却期間)によって配分し、費用として計上していくことになるわけです。これは、「資産は少しずつ目減りする」という考え方を反映させたものと言えます。
具体的に言うと、物件の価値が10年後に100万円下がると仮定した場合、10年後に一気に下がるのではなく、毎年10万円ずつ下がっていくという計算になります。
この毎年「10万円の低下分」が損金となり、所得から控除することができます。ある意味では当たり前と言っても差し支えない仕組みであり、結果として節税の効果は認められるとしても、それを目的とすることにはやはり、違和感を禁じ得ません。
何より、この仕組みが節税効果を発揮するのは物件の価値が右肩下がりの場合のみで、物件の価値が上昇している場合には、事情が大きく異なります。
先の例の続きで言うと、購入から10年を経過した時点で、物件の価値は当初想定した100万円の下落を回避できたとします。今が「売り時」と判断し、無事に購入価格と同額で売却することもできました。このとき、10年にわたって減価償却した100万円は利益として計上され、課税対象となります。
減価償却していくことで簿価(取得原価)が下がり、含み益のある資産を持つということは素晴らしいことではあるのですが、それは節税につながっているのではなく、経年による劣化に伴い、減価した建物の価値を補って余りある土地価格の上昇があった、ないしは減価償却ほどには価値が棄損しなかった結果だということです。