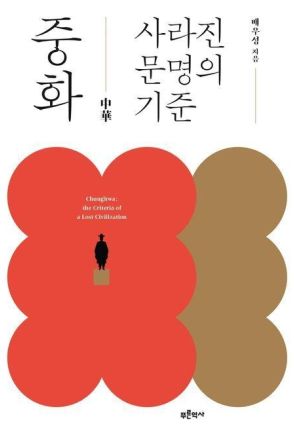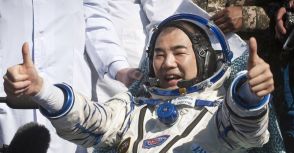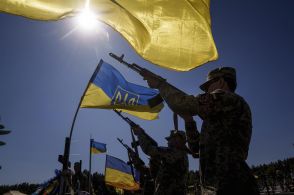「地図」について綴ることは「自分」を語ることに近づいていく。
東辻賢治郎氏によるエッセイ集『地図とその分身たち』は、地図や思想、媒体などさまざまなモチーフを通して描かれています。文章は枠組みや構成を持たず、洞窟や絵肌などの要素が繰り返し登場します。作者は連載中に起こった出来事を文章に反映し、日記のような記録を残しています。
タイトルの「地図とその分身たち」には、自由な形式であるエッセイの連載に対する作者の予感や希望が込められています。連載は予定回数よりも延長され、終了するまでの存在と推移が描かれています。モンテーニュやアンドレ・ジッドの言葉を引用しながら、作者自身の連載に対する自覚も述べられています。
『地図とその分身たち』は存在の推移として成立し、自己の記録と地図に関する考察が交差する作品です。洞窟やナイフ、亡命先での地図描写などのモチーフが織り成す文章は、作者の内面を巧みに描写しています。

「物」としての地図と「思想」としての地図。「媒体」としての地図。地図にまつわるさまざまなモチーフを通して、それらの交わるところを描いたエッセイ集『地図とその分身たち』。著者・東辻賢治郎さんによる、自身の中の地図をなぞるような本の紹介文をお届けします。
『地図とその分身たち』は短いエッセイを集めたもので、序文も章番号もないことからわかるように、中身に先立つ枠組みや構成はひとまずないものと考えていただいてかまわない。それでも他人事のように読んでみると、おぼろげな結節点のようなものはある。
たとえばいくつか繰り返し登場するモチーフがある。そのひとつは洞窟。真っ暗で静かで湿っぽい洞窟の中にいると、感覚や意識が少しずつ変化していく気がする。私は洞窟があたえるそんな涼しい酩酊のような感覚に惹かれている。そんなこととか、ナイフで削り取ったような絵肌や、流れるもの、あるいは亡命先で祖国の地図を描くことなど。
そうしたものの現われ方は意図したわけではなく、後から整えることもしていない。連載中にはいくつか印象を引き摺らせる出来事が起こった(起こっていた)が、そうした出来事が文章に反映されることも特に排除せずに、むしろ身を委ねた。新型コロナウィルスの流行とか、ロシアのウクライナ侵攻とか、個人的に重みをもつ著名人の死とかいったことだ。直接言及したものも、そうでないものもあるが、そのときどきの文章はそういったことが刻印された日記のようなものになっている。その意味では、巻末に記された連載期間の文字列はこの本のもうひとつの目次である。
そもそも連載〔本書の初出となった「群像」連載〕のタイトルを「地図とその分身たち」としたのは、エッセイの連載という自由な形式をあたえられたときに、少しずつ目を移す、あるいは横すべりする余地を残しておきたい予感や希望のようなものがあったからだ。理念的な目論見とか、扱うべきもの、応えるべき文脈は頭に浮かぶものの、持続は Why や What ではなく How の展開で保証されるという消極的な予感があった。「とその分身」の部分は思いつきでアントナン・アルトーの著作から借りたが、文字面以上の関係はない。つまりは「地図の……」というフレーズを避けた。
タイトルに引っ張られたのかはわからないが、結果的に書名になったことからすれば予感は成就したのかもしれない。最初に告げられていた回数から数回分の延長をゆるしてもらい、二十七回という半端な回数で連載を終えた。その判断の理由のひとつは、書き続けられる予感が生まれていたことだった。たしかモンテーニュは「存在ではなく推移を描く」と宣言していたが、その言葉を借りればこの連載は存在として構想されて、推移として終わったといいたくなる。ついでにいうと、アンドレ・ジッドはモンテーニュの『エセー』の三分の一は「自分のこと」であとは「おしゃべり」だと評しているが、この連載も何分の一かは自分のことを書いている自覚がある。あとは地図に関する「おしゃべり」である。