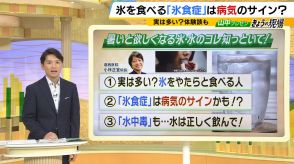希望につながる認知症の告知
がんの告知が一般化する中、認知症の告知には依然として医師の抵抗感が残る。
認知症は治療法が確立されていないため、告知をためらう理由がある。
早期発見・早期治療のためにも、認知症の告知が重要であり、医師の対応が患者の人生を左右する。

がんの告知は、今や当たり前となっている。ところが、認知症であることの本人への告知に抵抗感を示す医師は、まだまだ多いようだ。
認知症は、「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態」(介護保険法第5条の2)と定義されている。
原因疾患別にアルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など、さまざまなタイプがある。その多くは、根本的な治療法が確立されておらず、それが告知をためらう大きな理由となっている。
ただ、がんについても治療が難しいものは依然少なくない。
がんの告知が当たり前になった理由には、患者の治療への積極的参加により治癒や寛解の可能性が高まること、インフォームドコンセントや「患者の知る権利を守る」という考え方が普及したことなどが挙げられる。
一方、認知症の場合は、治療法が確立されていないことに加え、認知症に対する誤解や偏見が根強く、告知の際の患者のショックが大きいこと、告知の際の説明の仕方が分からないこと、または患者本人に説明しても理解できないと思っている医師がいること、家族が本人をだまして診察に連れてくるケースが多いことなどが告知の進まない理由に加わる。
認知症の場合もがんと同様、「早期発見」「早期治療」が重要だといわれる。しかし、早期発見・早期治療に直接影響を及ぼす告知の仕方は、医師によりまちまちだ。
どんな医療機関のどんな医師に診てもらうかは、告知される患者の人生を左右するくらい重要なことが多い。
認知症の疑いが濃厚の某大学の名誉教授である小島さん(85歳・仮名)が受診したのは、ある認知症専門クリニックだ。
紆余(うよ)曲折の末、受診に至ったのだが、それについては、別の機会に述べる。そのクリニックは、認知症の告知を前提として、診察や治療を進めている。
初診から2週間後、検査の結果が告げられることになった。
これは、そのクリニックの院長が行った小嶋さんへの告知の場面だ。認知症の告知は、本人ごとに説明の方法を変えるのが大切であり、その一例であることをご理解いただいた上で、再現しよう。なお、筆者は本人との関係が深く、告知の場への同席が許された。