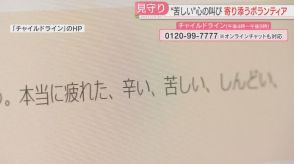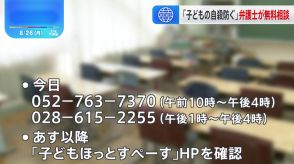二宮康明さんの「よく飛ぶ紙飛行機集」で味わった特別な「読書」体験 翻訳家・東辻賢治郎
2023年に亡くなった二宮康明の紙飛行機の本によって子供の頃の思い出が蘇り、物質的な世界との接点を持っていた。本は学びや冒険、自然の理解につながる入り口であり、二宮の紙飛行機集もその一環だった。
子供の頃は自然科学やノンフィクションに偏っており、トール・ヘイエルダールや植村恒義の著書に触れていた。物事の仕組みや生きものの話が好きで、自ら試してみることに興味を持っていた。
紙飛行機集や他の本を通じて、物理現象や自然のエレメントに触れる経験が特別であり、河原や運動場で本のページを切り取り空に放つ楽しみは貴重な思い出だ。

2023年に触れた訃報のうち、特別な感慨を覚えたもののひとつは二宮康明のそれだった。子どものころ彼の「著作」に親しんでいたからだ。といっても、「愛読」していたわけでも、ボロボロになるまで繰り返し開いていたわけでもない。二宮康明の代表的な「著作」とは、いうまでもなく「切り抜く本」と銘打たれた紙飛行機のシリーズだ。「読者」はその本に綴じられた良質な厚紙のページを切り取り、印刷された型どおりに部品を切り抜き、貼り合わせ、そして空に向けて飛ばす。つまり彼の「本」は文字通りに空を飛ぶ。しかも、きわめて合理的に設計された紙飛行機は、どれもこれもおどろくほどよく飛ぶ。子どもが作っても、うまく調整しさえすれば何分間かは地上に戻らずに飛びつづけ、しばしばどこかへ飛んでいって失くなってしまう。書店からやってきた本がいつのまにか空の彼方に消える。二宮康明の「よく飛ぶ紙飛行機集」シリーズ(誠文堂新光社)はそんな少し変わった「本」だった。
思い出してみると物語よりは「もの」の世界に触れていることが多く、子どものころに親しんでいた本もまた多くは「もの」への扉だった。それはたとえば生きものの世界であり、物事の仕組みであり、自然のエレメントだった。だから眺めている本は事典や図解のたぐいや、各種の工作の本や、探検記や冒険記であることが多かった。そして私にとっては、生きものであれば捕まえてきて飼ってみること、仕組みであれば自分で分解し、あるいは作ってみること、自然の世界であれば自らどこかへ行ってしまうこと(たいがいは無理な話なのだが)、そういったことが何よりの関心事だった。いってみれば本は入り口に過ぎない。その後も、通学の電車という限定された読書空間が生活に登場するまでの間は、どちらかといえば自然科学や「ノンフィクション」に偏重した読書傾向がつづいていた気がする。
先の二宮康明のシリーズに加えてよく触れていた本として思い出すのは、たとえばトール・ヘイエルダールの『コン・ティキ号探検記』であり、植村恒義の『瞬間を見る』(岩波書店)だった。前者は子ども向けのバージョン(神宮輝夫訳、偕成社)を読んだあと、大人向けの翻訳(水口志計夫訳、筑摩書房、現在は河出書房新社から刊行)を読み直すくらいには好きだった。考えてみればこの本には自然のエレメントも、生きものの話も、物事の仕組みもすべてが含まれている。後者の『瞬間を見る』はもう忘れられた本だと思うが、これは高速度撮影が見せてくれる世界や、その背景にあるさまざまな技術を紹介する小さな図解で、表紙と裏表紙の見返しに刷られたエドワード・マイブリッジの連続写真をよく眺めていた。そこにはやはり特別な物事の仕組みによって明かされる、自然のエレメントや生きものたちの見たことのない姿が記録されていた。
本を開き、そのページからひとつの物理的な現象が立ち上がり、それを媒介にして風や鳥たちの世界に触れる、そんな二宮の「紙飛行機集」も、私にとってはやはり「もの」の世界に触れる入り口だったのだと思う。プラクティカルな本はいくらでもあるけれど、文字通りに切り取った本のページを手に河原や運動場へ駆けて行き、それを空へ放って眺めている、そんな「読書」の経験は少し珍しい、特別なものだった気がする。