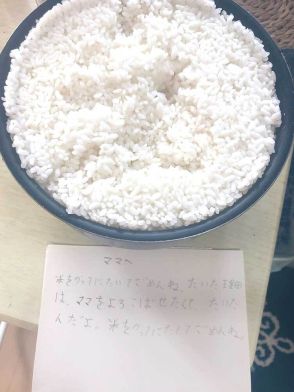<偉人の愛した一室>「小説の神様」志賀直哉が通ったすっぽん料理屋「大市」秘伝の調理方法とこだわり鍋で絶品に
志賀直哉は優れた写実表現で「小説の神様」と称され、引っ越し魔であった。彼は生涯を23度の引っ越しで転々とし、東京に落ち着く前に日本各地を訪れた。
志賀の充実期は千葉の我孫子で過ごし、代表作を生み出す。長編「暗夜行路」の執筆は行き詰まり、京都や奈良で新天地を求める。
奈良では文学サロンを形成し、多くの作家たちと交流。美しい風景と若い才能との出会いが志賀の作品世界を豊かにした。
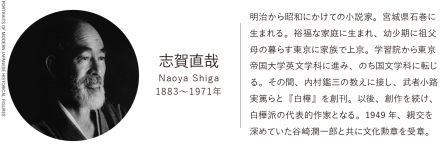
優れた写実表現で作家仲間からも尊敬され、「小説の神様」と称された志賀直哉は、意外なことに、引っ越し魔であった。生涯、23度にわたり居を改め、東京に腰を落ち着けるまで、日本各地を転々とした。その足跡は京都や奈良、鎌倉といった古都のみならず、尾道や松江、群馬の赤城山にまで及んでいる。
その志賀は1915(大正4)年から23年まで、千葉の我孫子で暮らしている。この間は小説家としての充実期にあたり、代表作の「小僧の神様」や「真鶴」といった短編のほか、長編「暗夜行路」の連載もここでスタートさせた。
だが、この長編執筆に行き詰まったこともあり、志賀は心機一転を図り、京都の粟田口、さらに半年後に山科へと移り、25(大正14)年の春からは奈良に居住する。奈良では、自身で設計した自宅に瀧井孝作、小林秀雄、小林多喜二といった新進作家たちが志賀を慕って集い、さながら文学サロンの様相を呈する。
美しい四季の移ろい、歴史や文化の色合い深い古都の風情、そして若い作家たちとの文学談議、京都、奈良での時間は志賀を癒やし、その後の作品世界を生み出す沃野となっていった。近代小説の最高傑作とも評される『暗夜行路』が完結したのは37(昭和12)年であり、志賀が奈良を離れて東京に戻る前年であった。
この名作に登場するすっぽん料理屋、志賀ら作家から愛され、いまも食通たち垂涎の名店が、京都で独自の味を守り続けている。
洛西、千本中立売の交差点に近い「大市」の創業は江戸時代、340年ほど前になるが、今のご当主、18代目にあたる青山佳生さんによれば、過去帳に残る初代の没年が1689(元禄2)年だから、ということになる。初代は侍だった。辺りの池で捕れるすっぽんを鍋にする煮売り屋、いまでいうテイクアウト中心の店であり、時に出前にも応じていたようだと話す。
そう遠くない場所に、西陣の豪商が軒を連ねていた。江戸中期からは遊郭「上七軒」が紅灯を煌かせ、明治以降は「五番町」が遊客で賑わった。水上勉の名作『五番町夕霧楼』の舞台である。いつの頃からか、そうした客に、入れ込み座敷ですっぽん鍋を提供する料理屋となっていった。一筋違いの千本通は大名行列も通る繁華な場所だったから、表の格子戸には幕末の刀傷が今も残る。
贔屓が増え続ける中、昭和初期には大増築を行い、奥に6つの座敷を設けた。それぞれに趣向を凝らした豪華な数寄屋造りであり、三井家や住友家にはご指定の部屋があった。いまに続く高級店となっていったことが窺われるのだ。
志賀直哉が通ったのはいつ頃か。創業から今に残る一郭に、盟友の里見弴から来た礼状が飾られる。60年ほど前、粟田口に住んでいた志賀に連れてこられたのが忘れ難い、そう始まる手紙には、芥川龍之介や直木三十五とここのすっぽん鍋に「うつつを抜かした」と綴られている。志賀が粟田口に住んだのは1923(大正12)年、まだ2階の座敷が主だった時期であり、まさに「暗夜行路」に描かれた頃のことだった。
いまはテーブルが置かれる2階座敷は二間続き、かつては入れ込みで客をもてなした。豪華な市松模様の畳が敷かれ、天井は黒漆塗り、欄間には波千鳥の彫刻板がはめ込まれる。お金のかかった造りである。ここで、志賀は作家仲間と舌鼓を打った。さて、そのすっぽん鍋とは──。