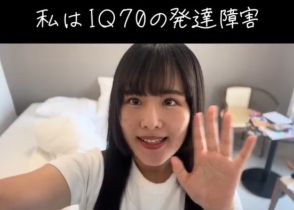個人が生きやすい社会とは何か――健康、嗜好の選択から考える
昔は煙草社会の少数派だった筆者が、今では多数派の中で感覚的少数派となっている。
ミルの自由論に基づいて、個人の自由と社会の規制について考察されている。
新型コロナによって社会的な同調圧力が強まり、個人の自由が制約される状況について述べられている。

私は昔から煙草を吸わないが、大学のゼミでは教授をはじめ大学院生もみな喫煙者だった。部屋が煙でもうもうとして、休憩時間に窓を開けたときにだけ息がつけるような状態。私は煙草社会の少数派だった。
その後、嫌煙運動が広がり、今ではほとんどの場所で喫煙は禁止されている。では私が多数派になったかというと、そうは思わない。喫煙者に課されている厳しい制約に違和感を覚えるからだ。嫌煙運動は構わないが、吸いたい人が吸えなくなるのはまずいのではないか。かつての私は人数としての少数派だったが、今では多数派のなかにあって感覚的少数派になったのだ。
ジル・ドゥルーズは『カフカ』のなかで、「偉大なもの、革命的なものはただマイナーなものだけである」と書いている。このマイナーは、多数派に対する少数派ではなく、多数派のなかに少数派として存在するという意味である。
フランツ・カフカはチェコに生まれたユダヤ人だが、チェコ語もユダヤの言葉も使わず、多数派のドイツ語を使いながら、ドイツ語自体を解体に導くような作品を書いた。多数派のなかにあって同化せず、内側から多数派を解体していく。
私は煙草社会では少数派だったが、それは本当のマイナーではなかった。みなが吸わなくなった今になって、私は多数派のなかに少数派として存在するという、ドゥルーズのマイナーの概念が、腑に落ちた気がしている。逆にいえば、煙草社会のなかでマイナーであると思っていたころは、「真のマイナー」ではなかったのだ。
ここでは煙草を例に挙げてきたが、多数派による過剰な制約は、社会から「遊び」を失わせるような感じがしてならない。
ある行為が社会的に不道徳であるなら、その行為を法で禁止する理由になる、という「リーガル・モラリズム」の考え方があるが、近代社会の基本原則はそうではなく、法的なものと道徳的なものは区別される。モラルの次元は私的な領域で対応し、パブリックで法的なものとは峻別してとらえる。個人的な事柄に対して国家は口を出さないというのが、近代社会の原則である。そこを区別せず曖昧にしてしまうとさまざまな問題が発生するからだ。宗教戦争はその一つである。
この考え方は、イギリスを代表する経済学者で哲学者のジョン・スチュアート・ミルが『自由論』で主張したもので、近代社会の「自由」の基本的な原則になっている。ミルは、他人に危害を与えなければ、その人の自由な行動は制約されるべきではなく、たとえその人のためにならない行動であっても介入しない、という「他者危害説」を唱えた。
「他者危害説」は、日本では「愚行権」といわれることがある。本人のためにならない愚かな行為であっても、本人が自由に選択していることについては介入しないからだ。
こうした考え方は1970年代や80年代まではある程度浸透していたが、欧米でも少しずつ社会的な同調圧力のようなものが強くなってきた。それを顕在化させたのは新型コロナだった。
日本は昔から同調圧力が強いといわれてきたが、新型コロナによって、ヨーロッパにおいても同調圧力が強く働くことが明らかになったのだ。
イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンは、ロックダウン(都市封鎖)を行って個人の自由を厳しく規制するヨーロッパ諸国のコロナ対策を批判した。ヨーロッパは「健康教」という宗教に侵され、それまで築き上げてきた個人の自由そのものを否定してしまった。ファシズムの時代でさえやらなかったことを平然と行い、国家のみならず国民もそれを支持した──。彼はその衝撃を語った。
ファシズムというと、国家や一部の権力を持った集団が、国民に対して非常に強い制約を加えるというイメージだが、コロナを契機に社会そのものが個人の自由を奪ってしまう。そのことに対して何の疑問も抱かない恐ろしさを、コロナの最中に発言したのである。
だが、アガンベンのこの発言は大きな批判を受け、彼はメディアから締め出された。論文を発表することさえできなくなった。それまでの「自由」の原則とは何だったのか、と思うようなことが起こったのである。
日本でも、コロナの当時はちょっと飲みに行ったくらいでも、なぜそこまでというほどの非難が起こったことは記憶に新しい。コロナが落ち着いた今になってみると、アガンベンの主張はよく理解できるだろう。