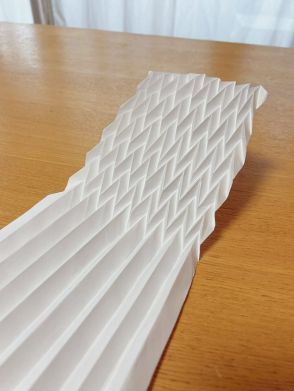【書評】深い闇を徹底解説:柯隆著『中国不動産バブル』
中国経済における不動産バブルと政府の失敗について解説。日本のバブル崩壊との比較も行い、中国独自の問題点を指摘。
中国特有の土地所有制度やマイホーム志向、政府の政策などにより不動産市場が膨らんできた経緯を分析。
習近平政権の成長政策と不動産開発の関係、最近の移住の動向を通じて、将来の中国経済の行方について懸念を示す。

谷 定文
中国経済がおかしい。大手デベロッパーの恒大集団に清算命令が出され、シャドーバンキング(影の銀行)の中植企業集団は破産を申請した。一見すると、日本のバブル崩壊前夜と似ているが、著者は中国特有の問題を指摘する。
日本のバブルは、地価は下がらないという「土地神話」を背景に、不動産業者が金融機関から融資を受けてマンション、ゴルフ場、リゾート施設などを乱開発したことによって膨らんだ。「土地神話」が強い点では中国も同じだが、本書はバブル生成のプロセスに、中国の特異性があると、多くの例を引いて解説する。
まず、社会主義国である中国では、土地の私有は禁じられている。では、どうやって不動産を「買う」のかというと、定期借地権(商業用地50年、宅地70年)を使って、地方政府がデベロッパーに土地を払い下げるのだ。
中国人は、日本人以上にマイホーム志向が強い。男性は自宅を用意していないと結婚できないという事情もあるが、契約を一方的に破棄されるビジネス慣行が一般的な中国では、賃貸住宅が忌避されがちだからだ。また、貯蓄率が高い割に金融商品が少ないため、資産形成には不動産が選好されるし、固定資産税がないから不動産の保有コストが低いという理由もある。
だから、富裕層は高いリターンを狙い、2軒目、3軒目のマンション購入に走る。中所得層も無理して住宅ローンを組み、居住用の住宅を手に入れようとする。こうした無数の行為が積み重なって地価が上がり、不動産バブルが生成されてきたのだ。
しかし、これだけならいくつかの制度上の違いを除けば、日本や他の民主主義国家でも見られる、「欲望の総和」とも言うべき現象だろう。決定的な違いは、共産党一党体制を維持するために習近平政権がゆがんだ政策を採用してきた点にある。
中国の公的な年金制度は、中央政府が一括して管理するのではなく、地方政府ごとに独立したプール制となっている。内陸部には、財政基盤が弱い地域が多い。地方政府はデベロッパーに払い下げる借地権を調整して土地を高値に維持、そこで得た資金を元に地下鉄建設などのインフラを整備したり、年金や医療などの原資に充てたりする。
「中国共産党は、選挙で選ばれていないため、その正当性を証明する唯一の手段は高い経済成長を実現し、人民生活を豊かにすること」
だから、習政権は成長のエンジン役として不動産開発を位置付けたのだ。著者は次のように総括している。
「30年前の日本のバブル崩壊は、基本的に市場の失敗だった。(中略)これに対し、中国の不動産バブルとバブル崩壊は、政府の失敗が引き起こしたものだ」
問題は中国経済の行方。著者は断定していないが、悲観的にならざるを得ない、最近の現象を取り上げている。
海外移住を目指す中国人が急増しているのだ。著者は、その背景には習近平主席が強める統制への絶望があると見る。
米国の西海岸に豪邸を構え、スポーツカーを乗り回している若者のほとんどは、共産党幹部の子弟。中所得層には、カナダとオーストラリアの人気が高い。では、低所得層はというと、ビザが不要なベネズエラに入国した後、陸路北上して米国への密入国を目指すという。
つまり、不動産バブルが崩壊して政府がその対処に失敗すると、カネ・人・技術が海外に流出する可能性があるとの示唆だ。
「今の中国経済は乾ききった大草原のようなもので、少しの火花でも、大規模な山火事へと発展する恐れがある」
日本企業は「脱中国」を模索しているが、日中の経済は既に密接に依存し合っている。中国で山火事が発生したら、日本も大やけどを負うと覚悟しなければならないだろう。
谷 定文
ニッポンドットコム常務理事・編集局長。1954年、東京都生まれ。上智大学外国語学部卒業後、時事通信に入り、経済部長、編集局長、常務取締役などを歴任。88~92年にはワシントン特派員として、激しさを増す日米貿易摩擦を最前線で取材した。2016年から現職。