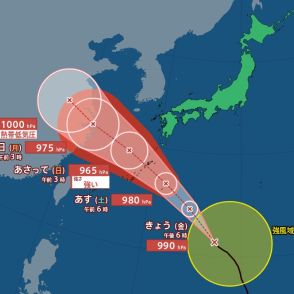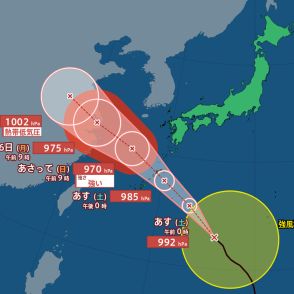清少納言は「偉そうで利口ぶった風流気取り」…紫式部がライバルを異常なまでに非難した政治的意図
清少納言は『枕草子』を通じて宮廷社会における政治的な役割を果たし、定子の存在意義について再確認させた可能性がある。
彼女は宮仕えをしていた時期に『枕草子』を執筆し、その内容は宮中で評判を呼び、藤原道長を脅かす存在となった。
一方、紫式部は清少納言が宮仕えをやめてから中宮彰子のもとに出仕し、道長の引きがあったと考えられる。『源氏物語』の執筆時期は長保3年から出仕するまでのあいだと推定される。
清少納言とはどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「生まれた年も、宮仕えをはじめた時期もわかっていない。彼女が描いた『枕草子』は、ただ内容が優れているだけでなく、定子を盛り立てる政治的な役割を担っていた」という――。
■『枕草子』が持っていた政治的役割
清少納言はなぜ『枕草子』を執筆し、宮廷社会に広めたのか。彼女は亡くなった皇后定子と、彼女が産んだ一条天皇の第一皇子、敦康親王の存在意義について、公卿たちに再確認させようとした可能性がある。
NHK大河ドラマ「光る君へ」の第29回「母として」(7月28日放送)には、そんな『枕草子』の特徴や、政治的な役割について理解できる場面が複数あった。
まず、ききょう(ファーストサマーウイカ、清少納言のこと)がまひろ(吉高由里子、紫式部のこと)の家を訪問し、のちに『枕草子』と呼ばれる文章を読ませた。まひろはその内容に感心しつつ、「私は皇后さま(註・高畑充希が演じた定子)の影の部分も知りたい」と伝えたが、ききょうは「皇后さまに影などないし、あったとしても書く気はありません。華やかな姿だけを人々の心に残したい」と拒んだ。
これまで「光る君へ」では、なんとなしに交流を重ねるように描かれてきた2人の差異が、はじめて明確に描かれたといえようか。それは『枕草子』と『源氏物語』の差異にもつながる。
続いて、ききょうは定子の兄である藤原伊周(三浦翔平)を訪ね、『枕草子』を渡したうえで、「皇后さまのすばらしさをみなの心のうちに末永くとどまるように、これを宮中に広めていただきたい」と頼み込んだ。それが、父の道隆(井浦新)に端を発する中関白家の再興につながると悟った伊周は、ききょうの望みを受け入れた。
■『枕草子』が道長を脅かす存在に
清少納言と紫式部が対面したという記録はない。だからといって2人に直接的な交流はなかったと断じることはできないが、「光る君へ」で描かれる2人の交流はフィクションである。だが、清少納言が意図したかどうかはともかく、『枕草子』が当時の宮廷社会で、「光る君へ」の第29回で描かれたような政治性を帯びたことはまちがいない。
清少納言については、生まれた年も、宮仕えをはじめた時期も、史料から確定することができない。だが、定子が入内して2、3年以内に出仕したとすれば、正暦3年(992)か同4年(993)ごろということになる。長保2年(1000)12月16日に定子が亡くなると、里に下がって、ふたたび女房になることはなかった。
そして、清少納言が宮仕えをした7、8年のことを記述したのが『枕草子』で、伊井春樹氏はこう記す。「清少納言は中宮定子を賛美し、現実の世に迫って来る厳しく追い詰められた姿は描こうともせず、明るい話題に転じるのが自分の任務と考えていたようである。(中略)むしろ悲しい現実から目を背け、定子の賛美を書き留めることが、自分の女房としての責務であるとしていたのであろう」(『紫式部の実像』朝日選書)。
実際、『枕草子』は宮中でたちまち評判を呼び、長女である彰子のサロンを盛り上げたい藤原道長を脅かす存在になった。
■いつ紫式部は「源氏物語』を書き始めたのか
一方、紫式部が中宮彰子のもとに出仕したのは、清少納言が宮仕えをやめて何年かしてからだった。どの年か正確にはわからないが、『紫式部日記』の寛弘5年(1008)12月29日の条に、「しはすの二十九日にまゐる。はじめてまゐりしもこよひのことぞかし(12月29日に参上する。最初に参上したのも同じ日だった)」とある。
また、それに続いて「こよなくたち馴れにけるも、うとまし身のほどやとおぼゆ(宮仕えにすっかり慣れてしまったのも、いとわしいことと思える)」と書かれているから、寛弘5年の前年ではなく、寛弘3年(1006)か同2年(1005)だろうと思われる。
出仕することになった理由は、道長の引きがあったからに違いない。だが、いうまでもないが、2人のあいだに「光る君へ」で描かれている恋愛関係があったからではない。書きはじめられていた『源氏物語』などによって、文才が認められたからだと考えられる。
では、『源氏物語』はなぜ、そして、いつ書かれたのか。「光る君へ」で時代考証を担当する倉本一宏氏の見解によれば、書きはじめられたのは、夫の藤原宣孝が死去した長保3年(1001)から出仕するまでのあいだと推定されるという。