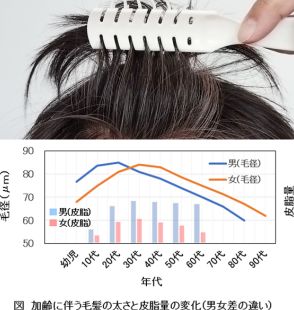「20代後半なのに福井で父と同居」では人生詰んでしまう…紫式部が年上の貴族からの求婚を受け入れたワケ
998年、紫式部は父の友人の貴族・藤原宣孝と結婚する。結婚時期を逃していた紫式部が、年上で子持ちの宣孝との結婚を決意した経緯が明らかになる。
『光る君へ』で描かれた宣孝による紫式部への直球の求婚は史実にはない。宣孝と紫式部の縁談は都で進んでいた可能性が高く、都を離れる前から口説かれていた可能性がある。
宣孝と紫式部のやりとりは歌を通じて行われ、紫式部は宣孝の気持ちを受け入れるかどうかを微妙に表現した。最終的には両者の結婚が実現した。
998年、紫式部は父の友人の貴族・藤原宣孝と結婚する。歴史評論家の香原斗志さんは「父の赴任に伴って福井に移住したものの、紫式部には結婚時期を大きく逃しているという焦りがあった。だから年上で子持ちであっても、藤原宣孝との結婚を決意したのだろう」という――。
■「越前で紫式部に宣孝が求婚した」は史実ではない
父である藤原為時(岸谷五朗)が国守として赴任するのに同行し、越前(福井県東部)に赴いたまひろ(吉高由里子、紫式部のこと)。NHK大河ドラマ「光る君へ」の第23回「雪の舞うころ」では、そこに遠縁で為時の友人でもある藤原宣孝(佐々木蔵之介)が訪ねてきた。
そして、宣孝はまひろに向かって、「会うたびにお前はわしを驚かせる」「わしには3人の妻と4人の子がおる。子らはもう一人前だ。官位もほどほど上がり、これで人生もどうやら落ち着いたと思っておった。されど、お前と会うと違う世界が垣間見える。新たな望みが見える。未来が見える。まだまだ生きていたいと思ってしまう」などと言葉を投げかけた。
その挙句、単刀直入にこう告げたのである。「都に戻ってこい。わしの妻になれ」。
たしかに宣孝は以前から、「越前まで唐人を見に行きたい」という発言はしていたようだが、越前まで足を運んだという記録はない。訪れることはなかったと思われる。また、当時の貴族が女性に求婚する場合、このように直球を切り出すことはなかった。
とはいえ、史実の紫式部も、任期をあと3年残している父を越前に残し、たった1年余りで都に帰り、宣孝と結婚するのである。
■都を離れる前から口説かれていた
為時と紫式部が越前に下ったのは、長徳2年(996)の夏以降のことだった。一方、宣孝はその前年の長徳元年までには、筑前(福岡県の大部分)の国守の任期を終え、都に戻っていた。
「光る君へ」では、越前に到着するまで、まひろは宣孝との結婚などまったく考えたこともなかったように描かれている。だが、SNSは当然のこととして電話も郵便制度もなかった当時、越前で暮らしている紫式部と宣孝の縁談が、急にまとまるとは考えられない。
伊井春樹氏は次のように推測するが、妥当なように思われる。「宣孝は筑前守として勤め、長徳元年(九九五)か前年には帰京していたはずで、そのころ紫式部との結婚話が具体的に進められた可能性がある。年が隔たっていることや、紫式部自身も二五、二六の適齢期を過ぎていたこともあり、気は進まず、あいまいな返事のまま、翌年には父為時の越前守赴任を口実に都を離れたのではないかと思う」(『紫式部の実像』朝日選書)。
やはり、紫式部が都にいるときから縁談が進んでいなければ、都から遠く隔たった越前で結婚を決意したりしないだろう。また、貴族の男性が女性に求婚する際は、まず歌を詠みかけ、受けとった女性は、いったんはやんわりと断るのがルールだった。そして、何度か同様のやりとりを繰り返した末に、話がまとまるときはまとまった。
■宣孝の恋文に対して紫式部が返した歌
では、宣孝は紫式部にどう詠みかけ、彼女はどう返したのだろうか。
まず、年が長徳2年(996)から同3年(997)に替わって、「唐人見に行かむ(越前まで唐人を見に行きたい)」といっていた人、すなわち宣孝が、「春は解くるものといかで知らせたてまつらむ(春には氷も溶けるように、閉ざしている貴女の心も、いずれ解けて私を受け入れてくれるものだと、どうにかしてお知らせしたいもの)」といってきたのに対し、紫式部はこう返した。
「春なれど白嶺のみゆきいやつもり解くべきほどのいつとなきかな(春になりましたが、白く染まった山に雪はなおも降り積もっていて、いつ溶けるともわかりませんが、私の心もそれと同じです)」
ほかに、紫式部はこんな歌も返している。
「みずうみに友よぶ千鳥ことならば八十の湊に声たえなせそ(近江の湖で友を呼んで鳴いている千鳥さん、いっそのことたくさんの船着き場で鳴くように、多くの女性に声をかけ続けたらどうですか)」
「よもの海に塩焼く海人の心からやくとはかかるなげきをやつむ(あちこちの海で製塩のために海水を焼く海人が、役目として投げ木を焼くように、あなたは多くの女性に心を寄せては、自分から嘆きを重ねているのでしょうか)」