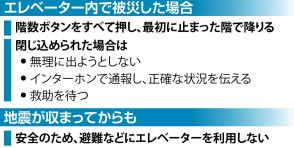東京を「大地震」が襲うとき、「わずか数分」が命を左右するという「厳しい現実」
東日本大震災や最近の地震を踏まえ、首都防衛の必要性が高まっている。
火災と地震の関係や通電火災の危険性、感震ブレーカーの重要性について解説されている。
首都直下地震に備え、通電火災への対策や専門家の疑問が提示されている。

2011年3月11日、戦後最大の自然災害となる東日本大震災が発生した。あれから13年、令和6年能登半島地震をはじめ何度も震災が起きている。さらには先日、南海トラフ「巨大地震注意」が発表され、大災害への危機感が増している。
もはや誰もが大地震から逃れられない時代、11刷ベストセラーの話題書『首都防衛』では、知らなかったでは絶対にすまされない「最悪の被害想定」が描かれ、また、防災に必要なデータ・対策が1冊にまとまっている。
(※本記事は宮地美陽子『首都防衛』から抜粋・編集したものです)
大地震がいつ襲来するのか誰にもわからない。
自分がいかに火元に気をつけていても、隣近所からの延焼があれば我が家を失う。地震発生時には火災への対応が生死を左右するといってもよいだろう。
一般の住宅では、建物や室内の状況によってはすぐに延焼が拡大し、2~3分で初期消火ができなくなる場合もある。初期消火で重要になるのは「わずか数分」だ。
地震で被害を受けた建物は、露出した柱や木材が燃え草となって、屋内の衣類やカーテン、本など燃えやすいものに火がつくとすぐに燃え上がり、平時より延焼スピードが加速する可能性がある。
家は窓ガラスが1枚割れただけでも外への開口部ができて、隣家から火の粉や吹き出した炎が入りやすい。木造住宅の内部では火災時には温度が1200度にも上昇し、3メートル離れた隣家でも840度に熱されるという。
地震発生直後の火災原因は、コンロの火や石油ストーブが倒れることなどによる直接的なものだけではない。
1995年の阪神・淡路大震災では、電気コードが断線し、ショートして火花が飛んで着火したり、停電していた電気が復旧した際に電気器具等から発火する「通電火災」など電気火災が60%だった。地震発生から15分で全出火数285件の30%が、その後の2時間で20%が出火した。
地震が起きたときに電気のブレーカーを落とさずに避難してしまうと、停電から復旧した際に、誰もいない家でもスイッチが入ったままだったストーブが過熱してカーテンなどに燃え移ったり、強い揺れでコンセントが半分抜けていて通電時に火花が飛んで着火することがある。現代では「通電火災」は巨大地震発生時の大きな課題だ。
2004年の新潟県中越地震や2016年の熊本地震の発生時には、電力会社が地域ごとに停電から復電する際に通電確認を行った。復電の知らせが届いた住民は自宅に帰って事業者とともに復電前に異常がないか確認し、通電火災を防いでいた。
しかし、首都直下地震が襲来したときにこうしたきめの細かい対応ができるのか不安視する専門家は少なくない。
都市災害に詳しい東京都立大学の中林一樹名誉教授は「被災者の数がケタ違いの東京で、どこまできめ細かく地域ごとにすべての居住者が同じ日時に自宅に戻り、各々の住宅で事業者と連携して通電確認を行うことができるか」と疑問を投げかける。
こうした通電火災を防ぐためには、別の方法もある。それが「感震ブレーカー」の設置だ。価格や種類はさまざまだが、強い地震を感知すると自動的にブレーカーが落ちたり、通電を遮断したりする装置だ。
つづく「『まさか死んでないよな…』ある日突然、日本人を襲う大災害『最悪のシミュレーション』」では、日本でかなりの確率で起こり得る「恐怖の大連動」の全容を具体的なケース・シミュレーションで描き出している。