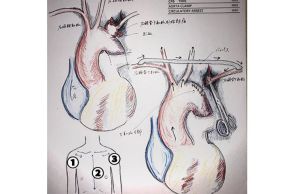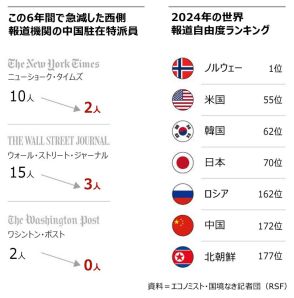日本女性による「わたしの体は母体じゃない」訴訟を米紙が大きく報じる
日本で不妊手術を受けるには厳しい条件が課されており、不妊手術を希望する女性たちが法律に抗議している。
現行法は出産可能性を前提とし、配偶者の同意が必要であるため、不妊手術は多くの女性にとってハードルが高い。
女性たちは自己決定権を主張し、法律の改正を求める訴訟を行っている。

日本で不妊手術を受けるには、世界で最も厳しい条件を満たなさければならない。2024年、5人の女性たちが、この法律が自己決定権を侵害しているとして国を訴えた。米紙「ニューヨーク・タイムズ」が、リプロダクティブ・ライツで遅れをとる日本のこの裁判に注目している。
東京でモデルをしている24歳の田中が中学生の頃、母親はよく、早く孫の顔が見たいと冗談を言っていた。いつか自分も出産するのだと思うと、彼女は怯んだ。
第二次性徴が始まると、彼女は極端な食事制限とエクササイズによって、体の変化を食い止めようとした。自分はジェンダーレスだと思うようになった。「一人の人間として認識される以前に、出産可能な子宮として認識されることが、私は嫌でした」と彼女は言う。そしてついには、妊娠する可能性をゼロにするため、不妊手術を望むようになった。
ところが日本では、女性が卵管結紮(けっさつ)術や子宮摘出術のような不妊手術を希望する場合、世界で最も厳しい条件を満たさなくてはならない。すでに出産経験があり、妊娠によって母体の健康が危ぶまれると証明しなければならないうえ、配偶者の同意も必要なのだ。ゆえに、多くの女性にとって不妊手術はハードルが高く、田中のような独身・子なしの場合は事実上不可能となる。
現在、彼女を含めた5人の女性たちが国を訴えている。1996年に優生保護法から改正された母体保護法という法律が、憲法で定められている平等と自己決定権を侵害するものであり、破棄されるべきだ、という主張だ。
6月、東京地裁でおこなわれた審問で、原告側の亀石倫子弁護士は同法を「極端に家父長主義的」であるとし、「女性の体は子を産むべきもの、との認識を前提としている」と語った。
亀石は、男性2人と女性1人の担当裁判官に向かって、自由意志による不妊手術の要件が前時代的であること、原告たちは「自主的に選んだ人生を生きるための重要な一歩」を踏み出したいと思っていることを述べた。