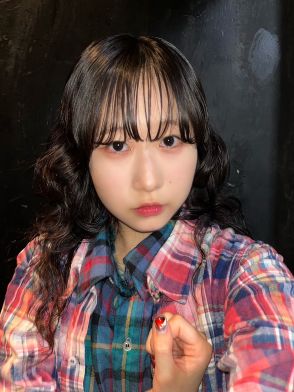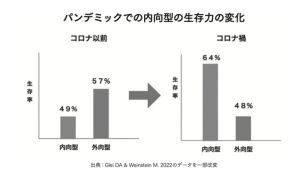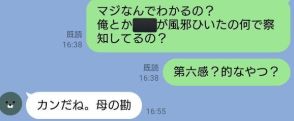「わたしは死にたくない……でも、これを解き明かせるなら死んでもいい」とまで科学者が考えるものとは?
脳の意識を機械にアップロードする可能性についての研究が進行中であり、それによって死が回避される可能性が考えられている。
作者は若い頃に死について友人たちと議論し、その後も死に対する恐怖を感じてきた。しかし、意識の解明と不老不死の実現に希望を託している。
死への恐怖は生物の生存本能に根ざしており、人々はこの恐怖を抱えながらも死に直面している。

意識を宿す脳は、すこしばかり手のこんだ電気回路にすぎない。であれば、脳の電気回路としての振る舞いを機械に再現することで、そこにも意識が宿るに違いない。多くの神経科学者はそう考えている。
問題は、ヒトの意識のコンピュータへの移植、いわゆる「意識のアップロード」である。仮にそれがかなえば、ヒトが仮想現実のなかで生き続けることも、アバターをとおして現世に舞い降りることも可能になる。どちらを選択しても、生体要素が一切排除されるため、死が強制されることもない。
はたして意識のアップロードは原理的に可能か? その技術的目処は立っているのか? この研究を続ける渡辺正峰氏の最新刊『意識の脳科学――「デジタル不老不死」の扉を開く』から一部を抜粋して紹介する。
15歳の秋の日の情景が、今でも鮮やかによみがえる。陸上部のトレーニングの帰り、住んでいた団地の一角にあった「てんとう虫公園」のブランコに揺られながら、死について友人と語り合った。話し始めた時点であたりはすでに暗く、ブランコの鎖が手のひらに冷たく感じられた。夢中になって話し込み、気がついたときには身も心も自慢の美尻も冷え切っていた。
それから8年、長年の夢であった研究生活を謳歌していた修士1年の春、1泊の研究室旅行にでかけた。その夜、宴会の席で同期二人を相手に死にたくない論を展開した。
「死への恐怖は、苦しみを伴う死のプロセスに対して向けられたものではない。一方で、死んでしまえば何も感じず、当然のことながらそこに恐怖など微塵もない。然るに、ここでとりあげる恐怖とは、こうして存在しているわたしが、死を境にきれいさっぱり存在しなくなってしまうことに対する、存在から非存在への断絶の恐怖である」云々。酒のたすけも借り、明け方まで話は続いたが完全な空回りに終わった。20歳を超えてまだそんな話をしているのかと揶揄されたりもした。その後登場した言葉を拝借するなら、中二病ではないか、と。
実はこの話には後日談がある。一昨年の秋口に学部の同窓会があり、そのうちの1人と何十年かぶりの再会をはたした。わたしが話をふると、彼はその長い夜のことをよく覚えていた。そればかりか、その内容が頭にこびりつき、いつの頃からか死の恐怖を実感するようになったと言う。人生の折り返し地点を疾(
と
)
うに過ぎ、死=断絶がリアルなものとして迫ってきたらしい。 みなさんはどうだろう。死は怖くないか。かつて怖いと感じていたことはないか。死は誰にでも平等に訪れるもの、どう足掻いても逃れられないもの、とその恐怖を理性で抑え込んでいるだけではないか。
なにも恥ずかしがることはない。心の奥底に佇むあなたに訊いてみてほしい。死への恐怖は、動物の発達進化の過程で間違いなく脳に刻み込まれてきたものなのだから。
わたしは怖い。今でも怖い。この文章を起こしているこの瞬間にも、無に帰してしまうことへの恐怖を通奏低音のように感じている。
しかしながら、今のわたしには一(
いち
)
縷(
る
)
の望みがある。死なずにすむのではないかと、心のどこかで本気で信じている自分がいる。何を隠そう、「意識の解明」と「不老不死の実現」の一石二鳥の妙案を思いついたからだ。