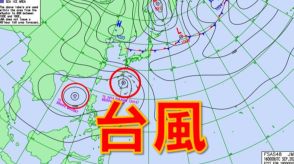学童疎開80年 福島の追憶(上) 親代わり「さぶやん」 都会っ子と寝食共に 寺の留守居・新房三郎さん
福島県桑折町で行われた子どもたちの疎開生活について語る。戦争末期に都市部から地方に疎開した児童たちの姿を明かす。
疎開生活の厳しさや食糧不足、地元の支援などを通して、当時の暮らしを伝える。
福島県桑折町の新房マスミさんと父親の三郎さんが子どもたちを支えたエピソードを振り返る。
夜になると子どもたちがすすり泣く声が聞こえた。福島県桑折町の新房マスミさん(89)は自宅の隣にある法円寺の境内を歩きながら、80年前の夏を思い返した。「親元を離れて都会から来た子にとって大変だったと思う」。東京都から町に集団疎開してきた児童と1945(昭和20)年夏の終戦まで約1年間、寝食を共にした。子どもたちの親代わりとなったのはマスミさんの父・三郎さん(1983〈昭和58〉年死去=享年82)だった。
戦争末期、戦況悪化に伴い、本土がたびたび空襲の被害に遭った。都市部への空襲激化も予想されるようになった。1944年6月30日、当時の政府は国民学校初等科3~6年生の集団疎開を閣議決定した。対象は東京都や大阪市、横浜市などで、8月に地方への移住が始まった。県遺族会によると、県内には東京都の児童約3万人が移り、集団生活を送った。
◇ ◇
マスミさんが住む寺には東京都中野区の野方国民学校の高学年約50人が身を寄せた。マスミさんは当時3年生。疎開してきた児童と一緒に醸芳小に通った。当時のことを今も思い出す。
軍統制下の学校生活は厳しかった。疎開児童と地元の子どもたちは読み書きの授業の他、空襲を想定した避難や防火訓練、竹やりや手旗信号の練習などに多くの時間を費やした。教員の多くは陸軍や海軍経験者で、体罰は日常的だった。
疎開児童の宿舎は寺の本堂だった。昼間は気丈に振る舞っていたが、夜は様子が一変した。寝床に着くとすすり泣きとともに声が聞こえてくる。「お母さん」「寂しいよ」「お腹がすいた」。遠く離れて暮らす家族を思って身をよじった。
育ち盛りの児童にとって、配給の食糧だけでは足りなかった。醸芳小には陸軍が駐留しており、他の地域よりは潤沢な備蓄があったが、白米は軍に優先的にあてがわれ、子どもにはほとんど回ってこなかった。疎開児童や住民は校庭の半分を畑にしてマメやサツマイモを育てコメに混ぜて、かさ増しした。それでも満足な量ではなかった。
◇ ◇
厳しい生活の中、支えになったのが三郎さんだ。住職が不在だった寺の留守居を任されていた。桑折郵便局の配達員も務め、顔が広かった。農家を回り、野菜などをかき集めて食糧の足しにした。