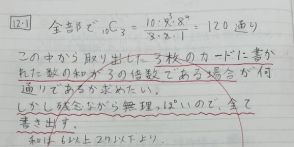「私の目の黒いうちに娘たちを死なせてほしい」 道長の容赦ない圧力による「平安貴族の無常」
藤原伊周の悲哀、娘たちの運命、そして女房としての屈辱が描かれる。
底辺の女房に下る運命を受け入れざるを得なかった女性たちの悲しみ。
平安貴族社会における女性の立場の脆弱さを象徴的に描くエピソード。

優雅な人生を想像しがちな平安時代の貴族たち。しかし、そこには貴族間の格差や権力争いがあり、女性たちも例外ではなかった。平安文学研究者・山本淳子氏の著書『平安人の心で「源氏物語」を読む』(朝日選書)から一部を抜粋、再編集し、その悲哀を紹介する。
* * *
■女主人と女房の境目
「私の目の黒いうちに娘たちを死なせてほしい、そう神仏に祈ればよかった」。重病の床でこう述懐した人物がいる。父が死ねば、娘たちは人の家に女房(侍女/にょうぼう)として雇われるだろう。それが我慢ならないというのだ。この人物とは、『栄華物語』(巻八)の記す藤原伊周(これちか)だ。かつては関白(かんぱく)の息子として、二十一歳の若さで内大臣(ないだいじん)にまでなった。しかし、父の死後、叔父の道長に権力の座を奪われてからは、彼の生涯は転落の一途だった。長徳二(九九六)年、つまらない諍いで自ら「長徳(ちょうとく)の政変」を引き起こし、大宰府に流されたのが二十三歳の時。翌年都に召還されはしたが、政界への復帰はならぬまま、三十七歳の春、持病が悪化して死の床に就いた。彼は、遺してゆく子どもたち、なかでもまだ十代の二人の娘の行く末を案じた。女御(にょうご)にも、后(きさき)にもと思って育て上げた娘たち。だが自分が死んでしまえば、先は見えている。伊周は娘たち、息子、そして北の方を枕もとに坐らせて言った。「今の世では、ご立派な帝の娘御や太政(だいじょう)大臣の娘まで、皆宮仕えに出るようだ。うちの娘たちを何としてでも女房に欲しいという所は多いだろうな。だがそれは他でもない、私にとって末代までの恥だ」。結局、彼の死後、事態は予想したとおりとなった。下の娘に声がかかり、藤原道長の娘・彰子(しょうし)に仕えることになったのだ。后候補の姫君から、一介の雇われ人へ。
「あはれなる世の中は、寝るが中の夢に劣らぬさまなり」。無念としか言いようのない運命を、『栄華物語』は夢も同じ儚さと憐れむ。
『源氏物語』「蜻蛉(かげろう)」巻には、この伊周の次女によく似た女房が複数登場する。明石中宮(あかしのちゅうぐう)の長女・女一の宮(おんないちのみや)付きの女房「小宰相(こさいしょう)の君(きみ)」、また同じ女一の宮に新参女房としてやってきた「宮の君」だ。小宰相の君は、「宰相」という女房名であるからには、公卿(くぎょう)の一員・宰相(参議)を身内に持つのだろう。居住まいが美しく、琴や文などの教養も抜きんでて、育ちの良さを推測させる。「なぜ宮仕えなどに出たのだろう」と、薫(かおる)も首をかしげる。おそらくセレブ階級からの転落を経て女房となったこと、想像に難くない。いっぽう「宮の君」は、父が光源氏の異母弟の式部卿宮(しきぶきょうのみや)で、かつては薫や東宮との縁談もあった。ところが父が亡くなり、継母とのそりが合わずつまらない男と結婚させられるところを、見かねた明石中宮が声をかけ、娘の女房として雇い入れたのだ。彼女自身のせいではないが、薫は非難の目を向ける。「かくはかなき世の衰へを見るには、水の底に身を沈めても、もどかしからぬわざにこそ(ここまでおちぶれるくらいなら、水の底に身を沈めても人から非難はされまいものを)」。女房への零落は自殺にも値することだというのである。冒頭の伊周の、娘を死なせたいとまで言った価値観は、当時の貴族においては特別なものではなかったのだ。