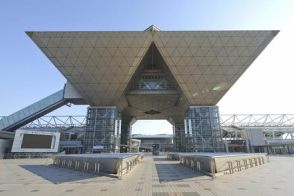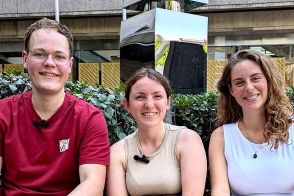朝ドラ『虎に翼』花岡悟は生き残れるか? 闇米を食べて罰せられるか餓死するかという戦後日本の食糧難
NHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』は第10週「女の知恵は鼻の先?」が放送中。終戦後、民法改正に携わることになった寅子(演:伊藤沙莉)は、思い出の公園で花岡悟(演:岩田剛典)と再会し、並んで弁当を食べる。しかし、花岡は法を犯して闇市で米を得ることを嫌い、質素な弁当を持参していた。
太平洋戦争中の食糧管理法や戦後の深刻な食糧不足により、闇市での食糧調達は違法行為として厳しく取り締まられていた。栄養失調や餓死が隣り合わせにある厳しい時代であり、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が憲法で保障されつつも、各国民は生存のための苦渋の選択を迫られていた。
1948年に実施された裁判では、被告人の食糧管理法違反について憲法の生存権を主張したが、被告人の上告は棄却された。食糧管理法は国民の福祉を考慮して制定されたものであり、憲法に違反するものではないとされた。

NHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』は第10週「女の知恵は鼻の先?」が放送中。終戦後、民法改正に携わることになった寅子(演:伊藤沙莉)は、思い出の公園で花岡悟(演:岩田剛典)と再会し、並んで弁当を食べる。ところが、食糧管理法に関する事案を担当している花岡は法を犯して闇市で米を得ることを自身によしとせず、あまりに少なく質素すぎる弁当を持参していた。
■常に栄養失調・餓死と隣り合わせだった戦後日本の暮らし
太平洋戦争中の昭和17年(1942)、政府は食糧管理法を制定し、食糧の生産・流通・消費を管理するようになった。そして、「政府を信頼して、買出しをするな! 闇をするもの(闇取引をするもの)は国賊だ!」と国民に呼びかけたのである。
昭和20年(1945)の終戦以降、復員や外地からの引揚げなどで、都市人口が増加。ところがその人口に対応できる物資があるはずもなく、政府が物価統制令に従って行っていた配給は機能しなくなっていた。
同年、東京・上野駅付近での餓死者は1日平均2.5人いたとされている。また、大阪などの大都市を含め全国で餓死者や栄養失調による死者が続出した。そんな状況でも、配給以外で食糧を手にいれるのは違法行為とされていたのである。判明した際には、入手した食糧を没収されるだけでなく、検挙・逮捕されることもあった。
深刻な食糧不足に陥った日本は、もはや「生きるために法律を犯して闇米を食べるか、法律に従って餓死するか」という極限状態にあったのである。
実際、法律を遵守して栄養失調やそれに起因する病で命を落とす人々がいた。ドイツ文学者で、旧制東京高等学校の教授だった亀尾英四郎は、昭和20年(1945)10月に栄養失調死している。彼の死を受けて、新聞には「“闇を食はない”犠牲、亀尾東京高校教授の死」という見出しが躍った。
新聞には「亀尾家の夫婦と子供6人が3日間で食べる野菜の配給がねぎ2本だった」という窮状が記された。近所に住む亀尾の教え子が恩師の体調の異変に気付いてどうにか救おうと牛乳などを持ち込んだものの、既に手遅れだったという。
また、青森地裁判事だった保科徳太郎や東京区裁判所の経済事犯専任判事だった山口良忠といった「法の番人」である裁判官も、「自分たちが法を犯して闇米に手を出すわけにはいかない」と配給される食糧のみを口にし、餓死するという事件が起きている。
さて、ここで昭和22年(1947)に施行された日本国憲法の第25条を思い出してほしい。第25条では、社会権のひとつである生存権を保障するとともに、国の社会的使命について規定している。第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」は、この状況に反してはいないだろうか?
そんなことを当時の人々も思っていたらしい。昭和23年(1948)、白米1斗、玄米2升を購入し運搬したとして食糧管理法違反で有罪判決を受けた被告人の裁判では、まさにこの憲法第25条が論点となっている。
結論から言えば、被告人の上告は棄却された。判決理由は次の通りである。「国家は国民一般に対して概括的にかかる責務を負担しこれを国政上の任務としたのであるけれども、個々の国民に対して具体的、現実的にかかる義務を有するのではない」
つまり、「食糧管理法は国民の福祉のため、できる限りその生活を安定させるための法律であって憲法に違反するものではないから、それを理由に被告人の罪を赦すことはできない」というわけである。
ちなみに、この食糧管理法はその後時世に合わせて改正されながら存続していく。そして平成7年(1995)11月に「主要食糧の需要及び価格の安定に関する法律」が施行されたことで廃止されたのだった。