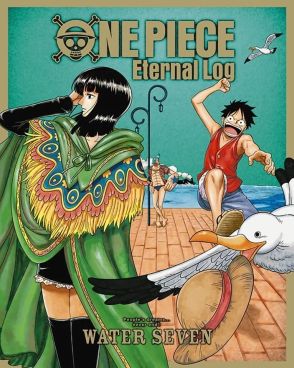「あのシーンは吉高さんも柄本さんもホントに疲れたと思う」大石静が明かす“『光る君へ』を辞退しよう”と思ったとき
『光る君へ』は、『源氏物語』の誕生を描く大河ドラマであり、作者のまひろ(紫式部)と藤原道長の関係や平安文化、権力闘争を描いている。
作品の執筆プロセスや伴侶との別れについて、脚本家の大石静さんがインタビューで語っており、創作に対する意識や影響を明かしている。
物語を生み出す場面や登場人物の微妙な表現についても触れられており、作品への想いと視聴者へのメッセージが伝わることを願っている。

およそ千年前に生まれた『源氏物語』。作者のまひろ(紫式部)と藤原道長のソウルメイトとしての関係、そして平安文化や権力闘争を描いた大河ドラマが大石静さんの『光る君へ』だ。同作の執筆、そして45年連れ添った夫との別れについて“連ドラの申し子”大石さんが語ったインタビューの一部を『 週刊文春WOMAN2024秋号 』より抜粋して紹介します。
――大河ドラマ『光る君へ』の第31回で、ついに『源氏物語』が誕生しましたね。まひろ(吉高由里子/紫式部)の中に物語が降りてきた瞬間を「色紙がはらはらと舞い降りてくる」という演出で表現されていたのが印象的でした。
大石 あれはチーフ演出の中島由貴さんのイメージです。彼女らしさがよく出ていたのではないでしょうか。私が脚本のアイデアを思いつくときは、上から降ってくるというよりも下からポコッ、ポコッと湧いてくる感覚です。
でも、『ふたりっ子』(96~97年)や『セカンドバージン』(10年)を書いていたときなど、ごくたまに「天から命じられて書かされている」と感じることがあって、そのときは上からパワーをもらっている感じがしました。『光る君へ』は、今のところまだ天から命じられている感じはないですが。
――自宅で『源氏物語』を書いているまひろの隣で、書き上がった原稿を藤原道長(柄本佑)が柱にもたれて読んでいるシーンは、二人の位置も完璧で美しかったです。
大石 道長が敏腕編集者みたいでした。あのシーンの撮影は吉高さんも柄本さんも、微妙な所を表現しないとならないので、ホントに疲れたと思います。
物語を生み出すシーンというのは、観念的なものじゃないですか。動きもあまりないし、登場人物も二人だけだし、「視聴者の皆さんが退屈してしまったらどうしよう」と不安でしたが、私も監督も演じた二人も、渾身の力を振り絞ったと思います。私達の想いが視聴者の皆さんに伝わったならうれしいです。
――まひろが『源氏物語』を「私のために書いている」というセリフにもグッときました。
大石 人生は自分のためにあるものですからね。「ついでに人の役に立てばラッキー」なのだと思います。どんなことでも「己がためが人のため」だということに、意外と気づいてない人が多いんだなと思います。
『源氏物語』は、「紫式部が夫を亡くしたあとの寂しさを埋めるために書いた」という説を唱える研究者も多いのですけど、今回、時代考証を担当されている歴史学者の倉本一宏先生は「道長のバックアップなくしては、こんな膨大な物語は書けなかった」とおっしゃいました。当時、紙は究極の贅沢品で、上質な紙を大量に手に入れることは、貧しい下級貴族には絶対に不可能なことでした。高級な紙を大量に提供できるのは道長しか考えられないのです。