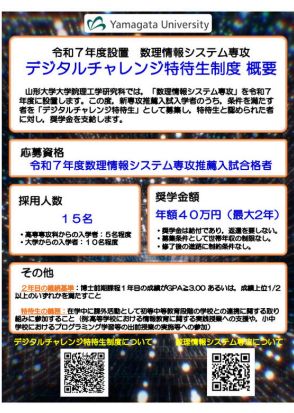亡き母との約束、恩師と地元に恩返し トップセールスマンが夢見たサンドイッチ屋さん
芝宮利明さんは、過去の家族の経験や恩師との約束から、会社を辞めてサンドイッチ屋を開く決意を固める。
幼少期から商売に興味を持っていた芝宮さんは、サンドイッチ屋の創業に向けて準備を進めてきた。
家族の理解と支援のもと、人生の新たな挑戦に向かって歩み出す芝宮さんの物語。

それぞれの朝はそれぞれの物語を連れてやってきます。
会社を辞めてサンドイッチ屋さんを開いた方のお話です。
芝宮利明さんは、56歳。足立区に生まれ、小学生の頃は野球少年でした。野球ばかりして勉強が全くできず、それを心配した少年野球の監督が、芝宮さんの母親に「うちで学習塾をやっているから通わせなさい」と言ってくれました。
少年野球の監督をしながら、アパートの一室で塾を開いていた高月壮平先生は、地元では知られた教育者でした。
その先生の指導もあって、成績がぐんぐん上がっていく。勉強が面白い!
とくに算数がすらすら解ける。「この子は算数だけなら開成にいける」と高月先生が驚いたほどでした。
地元の中学から早稲田実業に合格した芝宮さんは、もうその頃から商売に興味を持っていて、いつか自分も事業を起こしたいと思っていました。
早稲田大学に進み、いざ、就職となったとき、これからは、女性が活躍する時代が来る……と思い、京都に本社があるワコールに入ります。計算が得意な芝宮さんは、販売で頭角をあらわし、社内トップの最優秀セールス賞にも輝きました。
「とにかく販売が好きでしたね。どうしたら売上を伸ばせるか、実績を上げることに、大きなやりがいを感じていました」
その後、大阪支店長、東京支店長を経て、子会社の代表取締役に就任。そんな芝宮さんが「会社を辞めてサンドイッチ屋さんを始めたい」と家族に打ち明けたのは1年前のこと。驚いたのは妻と3人の子供達でした。
長女が大学生、長男が高校生、次女が中学生。まだまだ教育費がかかります。
「あと5年で定年なのよ。それからお店を始めたっていいじゃない」
妻の気持ちも分かりましたが、芝宮さんの決意は揺らぎませんでした。なぜ、サンドイッチ屋さんを開きたいのか……それは、いまは亡き母との約束がありました。
芝宮さんの両親は足立区綾瀬で「サンドーレ」というサンドイッチ屋さんを営んでいました。大きなショーケースに並んだサンドイッチが、毎日完売する繁盛店でした。しかし、父親が商売を広げたことで多額の借金を抱え、繁盛していたお店も手放すことになってしまいます。
父親はすっかり自信を失い、働く意欲もなくなって、家族を残したまま、生まれ故郷の山梨へ引っ込んでしまいます。ここで頑張ったのが母親でした。朝から晩までお弁当屋さんで働き、二人の息子を育て上げました。
「苦労をかけた母に、楽をさせてあげたかったんですが、私が32歳のとき、胃がんが見つかり、そのときはもう手遅れでしたね」
病床に伏す母親が、芝宮さんを呼び、こう打ち明けました。
「あんたは一生、高月先生に恩返しをしないといけないよ。あんたの塾代は一銭も払っていないんだからね。頑張って勉強しているあんたを見て、タダでいいって、先生が言ってくれたんだよ……」
その言葉を残して、母親は66歳で亡くなりました。母親の葬式に参列した高月先生にお礼を言うと、「そんなことあったかな、覚えてないな」と微笑んでいたそうです。
先生に恩返しをすることは、地元に恩返しをすることだと芝宮さんは、このとき、決意します。
いつか自分も子供たちに勉強を教えよう。大好きな野球も指導しよう。そして両親が仲良く働いていたあのサンドイッチ屋さんを開こう。その想いを、ずっと心に抱いていました。
サラリーマン時代は、単身赴任が続きました。長男が甲子園を目指す高校球児になったことも、地元に戻ろうという思いを強くさせました。芝宮さんは、数年前から仕事の合間を見て、サンドイッチの人気店を食べ歩き、時には経営者に商売のコツを聞き、少しずつ、開業の準備をしてきました。