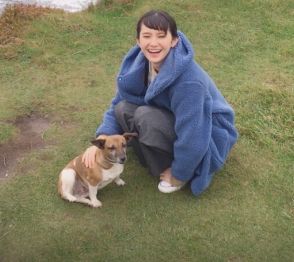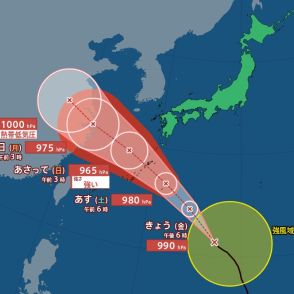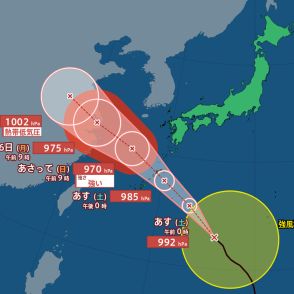『光る君へ』執筆動機が分かっていない紫式部の『源氏物語』、藤原道長はどこまで大きな役割を果たしたのか?
第31回「月の下で」では、藤原道長が紫式部に物語を書いてほしいと依頼するが、その真意は別にあった。紫式部を取り上げた著作もある偉人研究家真山知幸氏が解説。
藤原道長を支えた「四納言」の存在感が際立ち、源俊賢や藤原公任などの公卿に焦点を当てる。
藤原公任が年下の藤原斉信に出世を先にされてへそを曲げる姿が描かれ、公任の歌人としてのスタンスが示される。
『源氏物語』の作者、紫式部を主人公にした『光る君へ』。NHK大河ドラマでは、初めて平安中期の貴族社会を舞台に選び、注目されている。第31回「月の下で」では、まひろ(紫式部)のもとに藤原道長がやってきた。一条天皇に相手にされない娘の彰子のために物語を書いてほしいと、道長はまひろに依頼するが、実のところ真意は別のところにあった。『偉人名言迷言事典』など紫式部を取り上げた著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)
■ 道長をサポートする「四納言」の存在感
大河ドラマを鑑賞することで、歴史人物がどんな生涯を送ったのかというイメージを膨らませることができ、取り巻く人間関係も理解しやすくなる。
藤原道長の場合には、全盛期を支えてくれた4人の公卿がいた。源俊賢(としかた)、藤原公任(きんとう)、藤原斉信(ただのぶ)、藤原行成(ゆきなり)で、のちに「四納言」(しなごん)と呼ばれる面々だ。『光る君へ』では、道長が政治的野心のないキャラクターとして描かれていることもあり、優秀な4人のサポートが際立つ。
「四納言」の中で最年長となるのは、左大臣だった源高明の三男にあたる源俊賢だ。
俊賢は、妹の明子が道長と結婚しているという点でも、道長との結びつきが強い。立ち回りの巧みさから、公卿の藤原実資(さねすけ)からは「貪欲、謀略その聞こえ高き人」(貪欲謀略其聞共高之人也)と批判されることもあったが、それだけ存在感があったということだろう。
自身の昇進が決まって蔵人頭を辞任するときには、24歳の藤原行成を後任とし、一条天皇に推挙したとも言われている。行成が道長だけではなく、道長の長男・藤原頼通をも側近として支えたことを思うと、俊賢の貢献度はかなり高いといえそうだ。
■ 年下が先に出世してへそを曲げた藤原公任
同じ「四納言」でも、藤原公任と藤原斉信の関係性については、また事情が異なる。
彼らにとって道長は、かつてのライバルだった。公任は、関白の藤原頼忠(よりただ)を父に、醍醐天皇の孫の厳子女王(げんしじょおう)を母に持つサラブレッドだったし、斉信のほうは、太政大臣の藤原為光(ためみつ)の次男として、道長と同じく名門・藤原北家に生まれた。
紆余曲折を経て、道長をサポートする側に回った公任と斉信だったが、親しい友人同士だけに、お互いに負けたくない思いが強かったらしい。
寛弘元(1004)年、権中納言の斉信が従二位に叙せられた。自分より1歳年下にもかかわらず、斉信に位階で先を越されたことが、中納言の公任は気に食わなかったらしい。一時期、参内を辞めてしまっている。
それどころか、同年12月には、公任は道長に中納言・左衛門督の辞表を提出したというから、よほどプライドが傷つけられたのだろう。辞表はわざわざ紀斉名(きのただな)、大江以言(おおえのもちとき)といった名文家に依頼して書いてもらったが、その出来栄えに公任が納得できずに、大江匡衡(まさひら)に協力してもらったという逸話まである。
今回の放送では、まさにそのときのシーンが描かれた。金田哲演じる藤原斉信が、様子を見にやってきて、町田啓太演じる藤原公任に対して「いつまですねておるのだ」というと、公任は参内していない理由をこう説明した。
「和歌や漢詩を学び直しておった。本来の道に戻ろうと思っているだけだ。政(まつりごと)で一番になれぬのなら、こちらで一番になろうと思ってな」
ドラマでの藤原公任のキャラクターはクールな性格で、状況に応じた適切な判断を下して、道長を助ける場面も見られた。野心家で負けず嫌いなところはあるものの、藤原斉信が1歳年下だからといって「年上の自分よりも出世するなんて……」とへそを曲げるような、小さな男には見えない。
それだけに「歌の道に突き進むことにした」という前向きなスタンスを打ち出したのは、キャラクターに合っているし、それでいて「こちらで一番になる」という負けん気の強さも、公任らしくて嬉しくなってしまった。実際の公任も、勅撰和歌集『拾遺和歌集』で15首も選ばれたほか、数多くの作品がさまざまな勅撰和歌集に入首。歌人として影響力を高めていく。
ただし、公任が引退して出仕しなくなるのは、まだまだ先のこと。藤原実資(さねすけ)が書いた『小右記』によると、公任が辞表を出すと、その才を惜しんだ一条天皇はこう言ったのだという。
「懐(おも)ふ所有りて上(たてまつ)る所の表か。殊に一階を叙す。元のごとく仕ふべし」
(思うところがあって進上した辞表か。特に一階を叙す。元のように出仕するように)
*『小右記 ビギナーズ・クラシックス 日本の古典』(藤原実資著、倉本一宏編/角川ソフィア文庫)より
寛弘2(1005)年7月、斉信と同じく従二位に叙せられると、公任は参内を再開することになる。公任と斉信に限らず、周囲からは「四納言」と並び称されても、それぞれ意識するところはあったのだろう。