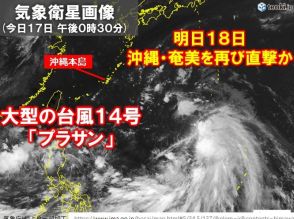日本兵1万人はどこへ消えたのか…「地下壕」を掘りまくっても骨片すら出なかった「硫黄島の現実」
硫黄島で行われた内部捜索の様子や結末について描かれた物語。生還者の証言が限られる中、何が起きたのか明らかにならず、作業が終了するという寂しい結末に終わっている。
土地や作業現場の過酷さ、作業員の体力消耗、さらには「マルイチ」の終了後の閉鎖までが描かれており、読者に異常な状況の中での作業現場の様子を伝える。
戦闘の激しさを反映する硫黄島の現状と、硫黄島での戦闘がどれだけ過酷であったかを物語っている。戦闘の中で何が起こり、どうして日本兵1万人が消えたのか、謎が深まっていく。

なぜ日本兵1万人が消えたままなのか、硫黄島で何が起きていたのか。
民間人の上陸が原則禁止された硫黄島に4度上陸し、日米の機密文書も徹底調査したノンフィクション『硫黄島上陸 友軍ハ地下ニ在リ』が11刷決定と話題だ。
ふだん本を読まない人にも届き、「イッキ読みした」「熱意に胸打たれた」「泣いた」という読者の声も多く寄せられている。
3班によるマルイチ内部での作業は30分交代だったので、次に内部に入ったのは1時間後だった。人間の「慣れ」とはすごいものだ。1回目の時に抱いた恐怖心や不安感はほとんど感じなくなった。2回目の僕の役割はバケツリレーのうちの一人目だった。1回目と同様に汗だくになって地上に出た。そして午前の作業は終了となった。
頭から足のつま先まで全身、土まみれだった。現地作業員の一人がハンディタイプの掃除機のような機械で僕に強風を浴びせ、作業着やヘルメットに付いた土を吹き飛ばしてくれた。全員が土を落とし終わったところで、バスに乗り込み、再び滑走路を横切って、宿舎に戻った。
自室に着いて「ああ、生還した」と一人ごちた。未知の地の底から帰ってくることができた。ベッドの横の小型テーブルの上に置いていたスマホを見ると、ショートメールの着信が1件あった。宿舎のある自衛隊の庁舎地区は携帯電話やインターネットが繋がった。ただ、衛星回線のためなのか、本土に電話すると、まるで国際電話のようにタイムラグがあった。
メールは、同僚からだった。こんな一文だった。
「どうだい南洋リゾート気分は」
読んで苦笑した。確かに僕が2週間過ごすのは南洋の島だが、リゾート気分は1ミリも感じたことはない。むしろ毎日、汗にまみれ、土にまみれ、命を賭して、リゾートとは真逆の日々を過ごしているのだ。僕は1分でも1秒でも長く休憩するため、適当な返信をして、スマホを放り投げるように手放した。
午後の作業から変更点があった。30分交代は20分交代に短縮された。作業による心身の消耗度をふまえると30分では長すぎるという声が、きっと収集団員から上がったのだろう。
午後の作業は、楠さんに相談して、バケツリレー要員ではなく、壕底まで土を掘る作業を担当させてもらった。3回目の内部捜索。前の班がスコップや箕を置いていった箇所が、次の僕たちの班が引き継ぐ捜索現場だ。
僕は残されたスコップを手にし、がむしゃらに掘った。掘っても掘っても遺骨は出てこない。兵士の身の回り品も、見つかったのは水筒1個だけだった。そのほか、出てきたのは主に小銃弾と、元々は何だったのか分からない金属の塊などだった。僕たちが担当する21.5メートルの区間のうち、20メートルの捜索が終わったところでこの日はタイムオーバーとなった。
残った捜索作業は次の土曜日である10月5日に行われる予定だった。しかし、またもや軍用機が滑走路を使うという理由で中止になった。結局、最後の日曜日である10月6日に行われた。この日の捜索でも兵士の亡骸は骨片すら出てこなかった。
この壕は「空っぽ」だ。そんな第一印象通りの結末となった。
全員が地上に上がり、スコップなどの道具を片付けた。作業終了後に行う拝礼の前、団長は皆に向かって、こう言った。
「これをもって3年間に及んだ地下壕マルイチは終了となります。この壕でお迎えできたのは前回までに見つかった4体でした。それでは皆さん、ヘルメットを脱帽してください。それでは拝礼します。拝礼!」
僕たちは、この現場に来たときと同様、僕たちだけでバスに乗った。一緒に帰る兵士を一人も見つけることができなかった。団員の一人がバスの中でこんな話をした。
「ここは硫黄島の戦いの中でも初期の戦闘が行われた場所だ。栗林中将は全将兵に対して、無謀なバンザイ攻撃を禁止し、持久戦を続けるよう厳命していた。ここでの地上戦で戦死しなかった人は、持久戦継続の命令を守って北部に移動したのではないか。だから、壕の中に残って絶命した人は少なかったのではないか」
兵士の95%が戦死した硫黄島は、生還者の証言が限られることから、分からないことだらけだ。この団員の推測通りかもしれないし、違うかもしれない。実相は誰にも分からない。少なくとも言えることは、マルイチからは4体しか見つからなかったという事実だけだ。
現場から宿舎に向けて走り出したバスの窓から、僕はマルイチの現場を振り返った。現地作業員たちがクレーンでコンクリートのパネルを下ろして立て坑を塞ごうとしていた。
そしてマルイチは閉じられた。おそらく、永遠に。その光景を見ていたのは、バスから振り返った僕と、滑走路脇で羽を休める、名も知らぬ鳥たちだけだった。