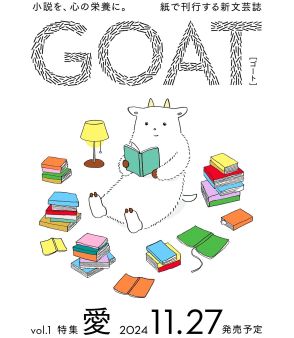こうして「百年の孤独」は誕生した…出版社に原稿を送る切手代さえ払えなかった作家(39)に妻がかけたひと言
ガブリエル・ガルシア=マルケスの『百年の孤独』が文庫版として26万部の大ヒットを記録し、執筆時の舞台裏や出版までの苦労が明らかになる。
執筆時、ガルシア=マルケスは小さな部屋で労働者の作業服を着て執筆し、家族のために何でも売る苦しい経済状況にあった。
原稿を送る際に送金の足りなさから一部しか送ることができず、出版後は本の成功を予期していなかったが、大ヒットとなった。
作家、ガブリエル・ガルシア=マルケスの『百年の孤独』が話題だ。今年6月26日に新潮社から文庫版が発売されると、海外小説としては異例の26万部の大ヒットとなっている。世界的ベストセラーは、いかにして誕生したのか。『ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生』(岩波書店)より、一部を紹介する――。
※本稿は、ジェラルド・マーティン著『ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生』(木村榮一訳、岩波書店)の一部を再編集したものです。
■『百年の孤独』を執筆する際に必ず来ていた服
作者が執筆していた部屋は、後年多くの人たちが「メルキアデスの部屋」と呼びたがったのと裏腹に、魔術的な雰囲気をたたえていなかった。ガルシア=マルケス自身がそう名づけた「マフィアの洞窟」は、小さなバスルームと中庭に面したドアと窓のある縦8フィート、横10フィートの狭い部屋だった。
そこにはソファ、電気ストーブ、本棚がいくつか、ごく普通の非常に小さいテーブルがあり、その上にオリベッティのタイプライターが置いてあった。執筆するために労働者のブルーの作業服を着るようになり――いつしかそれがすっかり慣例となっていた(ネクタイをする時でさえ脱がなかった)。
彼はすでに仕事を夜型から朝型に変えていたが、これは革命的な決断だった。今は一日の仕事を終えたあと、広告代理店、あるいは映画スタジオのオフィスで執筆する代わりに、子供たちが学校から戻ってくるまでの午前中に働いていた。家族からいろいろうるさく言われて創作に支障をきたしたり、行動を妨げられることはせず、ガルシア=マルケスは仕事と自己訓練に対する取り組み全体を変えるかもしれない変化を強いていた。
■お金になるものはなんでも売った
それまで妻で母親で主婦だったメルセーデスは、今では受付、秘書、そしてビジネス・マネジャーの仕事をこなしていた。そのような状態がいつまでも続くことになると彼女はほとんど気づいていなかった。ただ、こうした変化から生まれた新作小説が、ただちにドラマティックな形で一家に恩恵をもたらすことになる。
メルセーデスは家族の生活を支えるために策を講じて戦っていた。1966年はじめには、それまでとっておいたお金が底をついた。夫である作家は、以前のようにデッド・ロックに乗り上げて動けなくなることもなく小説はどんどん膨れ上がり、それはその年の終わりまで続くものと思われた。
ガルシア=マルケスはついにタクバーヤにある中古車専門店へ白いオペルを持っていき、かなりの額のお金を手にして戻った。以後、夫妻の友人たちは一家の送り迎えをする羽目になった。
電話を手放そうとさえ考えた。節約のためであったが、それだけでなく電話をして友人たちと際限なく話す、彼にはいちばんの気晴らしを控えようとしたのだ。車を売って手に入れたお金が尽きると、メルセーデスはテレビ、冷蔵庫、ラジオ、宝飾品といった家にあるものを手当たり次第に質に入れはじめた。
■原稿を送るお金すらない
8月はじめ、先の手紙を書いた2週間後に、ガルシア=マルケスはメルセーデスと一緒にできあがった原稿をブエノスアイレスへ送るために郵便局へ行った。2人は大災害の生存者のようだった。
小包にはタイプライターで清書した490枚の草稿が入っていた。窓口係が「82ペソです」と言った。メルセーデスが財布の中を探っている様子を、ガルシア=マルケスはじっと見つめていた。2人は50ペソしか持っておらず、原稿は半分ほどしか送ることができなかった。
ガルシア=マルケスは送料が50ペソぎりぎりになるまで、カウンターの向こうにいる窓口係にベーコンをスライスするように原稿を一枚一枚はずしてもらった。
2人は家に取って返すと、電気ストーブ、ヘアドライヤー、それにミキサーを質に入れ、郵便局に戻って残りの原稿を送った。郵便局を出たところで、メルセーデスは足を止めて夫のほうに向き直った。
「ねえ、ガボ〔編注 ガルシア=マルケスの愛称〕、これであとはあの小説がダメ出しされるのを待つだけね」
『百年の孤独』は1967年5月30日に刊行された。本は352ページで、価格は650ペソ(約2ドル)だった。当初はふつうの作品と同じように3000部刷る予定だった。ラテンアメリカ諸国の基準からすれば多いほうだが、アルゼンチンでは標準だった。