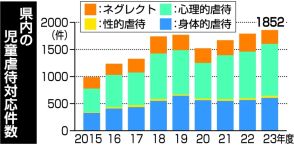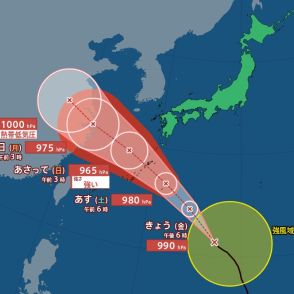「オムツのウンチを投げる」言葉をもたない障害の重い子が里親の愛情で育ち、中学卒業時に先生に言った一言
日本の里親制度の現状と問題点について語られる。
里親である坂本洋子さんの経験を通じて、子どもが家庭で愛情を受けることの重要性が示される。
障害のある子どもたちを受け入れる決意をした坂本洋子さんの姿勢や、彼女の家庭での子どもたちとの交流が描かれる。
日本では、虐待されて保護された子どもの多くが、里親などの家庭ではなく「施設」で育つ。日本の里親委託率の低さは各国と比べると明らかで、国際的批判を受けているのが現状だ。40年で19人の子どもを育てた里親のベテラン、坂本洋子さんは「家庭で、たくさんの愛情を受けて育つことが、子どもの健やかな成長には必要不可欠。あなたは大切な存在なんだよと思い、伝えつづければ、子どもの心は確実に育っていく」という――。
※本記事の情報は取材時のものです。
■親がいれば
親のいない子って、社会で、こんな扱いを受けるんだ……。坂本洋子さん(67歳)が養育里親になって初めて預かった里子の純平くん(仮名)が、バイク事故により17歳で短い命を終えたときに、思ったことだった(前編)。
「生前に純平は、『施設にいるとイライラして、壁に穴を開けてしまうから、手が痛いんだよね』って言っていたの。当時それを聞くたびに、胸が痛かった。親がいればって」
純平くんの死は、あまりにもつらく悲しく、重いものだった。
「現実のことと受け止めるには、時間がかかりました。簡単に切り替えできるわけもなく、時間の経過とともに咀嚼していくしかなくて」
純平くんの死後、坂本さんには決めたことがある。
「これからは、障害のある子だけを預かろうと。里親制度自体の理解がなかなか得られず、こんなに大変なら、障害のある里子たちを預かるのは並大抵のことじゃないはず。でも、今の私なら、何でもできるなって思った。人の裏表の怖さも知ったし、こんなに悲しい、つらいことが起きて、もうこれ以上に怖いことなんて何もないって思ったから。どれだけ大変でもやるって決めたんです」
■言葉より必要なこと
児相にその意向を伝えてから、最初に来たのは聴覚に障害のある女児だった。手話を習ったことのない子だったので、一緒に手話を覚えながら、意思疎通を図っていった。
「気持ちさえあれば人間って、コミュニケーションが難しくても、こんなにちゃんと一緒に暮らせるんだということを彼女から学びました。あなたは大切な存在なんだよっていう気持ちがあれば、言葉がなくとも思いは通じるんだって」
これまで預かった里子の中でも、最も障害の重い子が、秋人くん(仮名、15歳)だった。重い知的障害を伴う自閉症で、言葉によるコミュニケーションも難しい。彼を預かる際に坂本さんが聞いたのは、母親が産む前から育てないと決めていた子だったということだけだった。母親は産んだ子に障害があることすら知らないらしく、では名付け親は誰なのか。夏に生まれたのに「秋人」と名付けられた理由も、わからない。
「アキくんは、2歳でこの家に来たの。『坂本さんが受けなければ、この子は施設に入ることになります』って、子ども思いの児相の担当に言われてね。これほど障害の重い子が一度施設に行けば、里親家庭に出ることは二度とないわけで。大勢の中の一人で生きていく人生が待っているわけです。そんなの『やります』としか言えないじゃない。覚悟して受けました」
秋人くんが来る前と来た後の両方に坂本家に訪れた私は、部屋の様子の変貌にひどく驚いた。