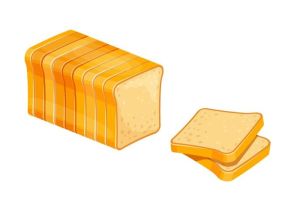食パンの「耳」はなんでこう呼ぶの?【知って得する日本語ウンチク塾】
食パンの周りの茶色の部分を「耳」というのは、語の由来や意味について詳しく説明されている。
「パンの耳」という言葉は明治後期には既に存在しており、作家夫婦の本に記載されていたことから明らかになっている。
「パンの耳」の起源について、初出は明治40年の書籍にまで遡ることができる。

国語辞典編集者歴37年。日本語のエキスパートが教える知ってるようで知らなかった言葉のウンチクをお伝えします。
食パンの周りの茶色の部分を「耳」と言うのは、たぶん皆さんも知ってますよね。でも、なんでこの部分を「耳」というのかご存じでしょうか?
『日本国語大辞典』(小学館)によりますと、この場合の「耳」は「物の端や隅」という意味なのです。同書には、パンだけでなく、豆腐や、織物・紙・本などの平たいもののふち、大判・小判のふちも「耳」というと説明されています。
たとえば金額を不足なく整えることを「耳を揃える」と言いますね。これは大判、小判のふちを揃えることからきているのです。「パンの耳」も、ふちのことを意味する「耳」なのです。
では、パンのふちの部分を「耳」と呼ぶようになったのは、いったいいつ頃からなのでしょうか。
このことについてある大手製パン会社のホームページでは、明治36年(1903年)に刊行された『食道楽』という本では、この部分を「縁の硬い處(ところ)」としていて「耳」とは記載されていません。このころはまだ「パンの耳」という語はなかったと言っています。
でも、私はそんなことはないと思っています。ほぼ同時代といえる明治40年(1907年)に出版された書籍の中に「パンの耳」が出てくるからです。それは、村井多嘉子という人の口述内容を筆記した『手軽実用 弦斎夫人の料理談 第1編』という料理本です。その本の中では、以下のように書かれています。
「フライ鍋(パン)でバターをよく煮立てて胡瓜を長くいためます。そこへスープをさしてパンの耳(みみ)を小さくち切って」(胡瓜は如何に料理すべきか)
実はこの本と、製パン会社のホームページで引用された『食道楽』とは深い関係があります。
『食道楽』の作者は作家の村井弦斎(げんさい)です。そして、村井多嘉子の本の書名は『弦斎夫人の料理談』です。もうおわかりですね。弦斎と多嘉子は夫婦なのです。弦斎がなぜ「パンの耳」を著書で使わなかったのか、その理由はわかりません。でも、同じ料理に造詣の深い夫婦同士、夫の方がその語を知らなかったとは思えないのです。そして、「パンの耳」は確実に明治後期には使われていたことが多嘉子の本からわかります。