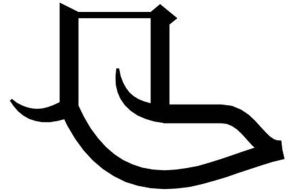コロナ後に増えている「6月病」…孤立した心を支える「訪問看護ステーション」の取り組みと、ケアの意義とは
新しい生活のストレスで「6月病」が注目されている。気持ちの落ち込みが進行してうつ病につながることもある。
訪問看護ステーションくるみでは、精神疾患を抱える人やその家族に支援を提供している。心のサポートを大切にする姿勢が特徴。
ケアの過程で振り返りや本人の気づきを促すことで、自律した行動を引き出すことが重要とされている。

4月に新しい生活が始まって何かと気苦労の多い時期を耐え、5月もなんとか踏ん張ったけど、もうムリ…。コロナ禍をきっかけに認識され始めた「6月病」。訪問看護ステーションへの相談件数は増える一方だという。大阪市東住吉区で精神科に特化した「訪問看護ステーションくるみ」を営む、中野誠子さんに聞く。
4月は新入学や就職などで、環境が大きく変わるとき。人間関係も新しくなり、何かとストレスの多い時期だ。そんな日々を過ごして5月を迎え、精神的にしんどくなる「5月病」はよく知られている。ところが近年は、なんとか踏ん張って5月病にならなかった人が6月に不調を訴える「6月病」が現れているという。
「6月は長い連休がありません。5月のゴールデンウィーク明けから普段通りの生活に戻ったけれど、気持ちがついていかない。しかも6月は気圧の変化が激しい時季で、気分の浮き沈みに大きく影響します。この時期に気分を崩される方が多いです」
最悪の場合は、うつ病に進行してしまう恐れがあるという。
中野誠子さんは、そのような気分の落ち込みに悩む人はもちろん、家族にも寄り添う「こころ」の支援を行っている。
よく「気合が足りない」とか「甘え」と非難されがちだが、精神疾患は脳の病気だ。それに関連して、中野さんは「心」を書き表すとき、ひらがなで「こころ」と書くことにこだわる。
「心臓や血管も関係はしてるんですけど、漢字で『心』って書いてしまうと脳と関係なく思われて、それこそ精神論になるので、ひらがなで書くことにこだわっています」
中野さんが営む「くるみ」では現在16人のスタッフで、大阪市内を中心に170人のケアを行っている。
精神疾患をもっていても、社会に出て働いている人は多い。自分が精神疾患をもっていることを職場の上司や同僚に伏せている人は珍しくないという。
パニック障害をもっている、ある相談者の事例をお伺いした。パニック障害とは、肉体的には病気がないのに、動悸、呼吸困難、めまいなどの発作が突然起こり、それを繰り返すため「また発作が出るのでは?」との不安から、外出に制限がかかってしまう病気だ。
その相談者は外で仕事をしているが、就寝前にパニック障害が起こって眠れないから朝起きるのが辛い。そのため、訪問看護を依頼してきたという。
「まず、敢えて朝に訪問します。看護師さんが訪ねて来るという状況をつくることで、起きるきっかけとなる場合があります」
ケアを行う際は「振り返り」も大事だという。
「たとえば、仕事が上手くいかなかった日、精神疾患をもっている人は『上手くいかなかったこと』だけが頭に強く残ります。そこに至るまでの経緯を話してもらうと、土日が連休だったので日中はずっと寝ていた。そのせいで月曜日は頭がクラクラしていて、仕事に支障が生じて上司に叱られたというのです。経緯を話すことで本人が気づくわけですね。自分の声で話して、それを自分の耳で聞いて、気づいてもらうことを大事にしています。私たち看護師は、相談者さんに何かするというより、ご本人自ら気づいて行動に起こせることを、後ろから支える立場といえます」
相談してくる人の多くは働いている世代だが、「くるみ」が現在ケアしている年齢層は2歳半から94歳までと幅広い。幼児や高齢者の場合は、家族支援も大事とのこと。
「ケアの対象になるご本人にアプローチするんだけれども、その人を支えている家族が倒れてしまったらご本人が生活できなくなるんです。周りの人たちが倒れないように、お母様にお話したり、家族の方とお話したりして、息抜きをしてもらう。誰かに話すだけでも、ずいぶん楽になりますから」