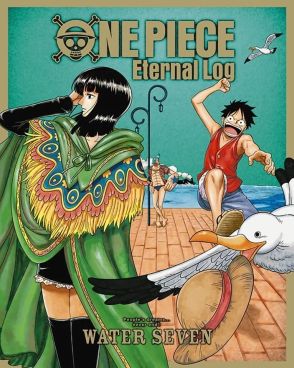三谷幸喜監督 新作映画は「ある意味開き直って」脚本家演出家として主戦場舞台への“原点回帰”
三谷幸喜監督は、5年ぶり9本目の監督作「スオミの話をしよう」で映画監督としての自らと向き合い、舞台と映画のハイブリッド作品を作り上げた。舞台的な要素と映画的な要素を融合させた作り込みに力を入れ、自分にしか作れない作品を追求した。
準備の徹底や稽古を重視し、演劇的な映画作りに取り組んだ三谷監督。映画製作に関する自身の信念を持ちながらも、批判には耳を貸さず、独自のスタイルを貫いた。
三谷監督は、演劇の世界から映画監督としてデビューし、コメディー作品にも挑戦したいという思いを抱えている。これまでのキャリアを振り返りながら、未来に向けての創作意欲に溢れた姿勢が見える。

三谷幸喜監督(63)は、5年ぶり9本目の監督作「スオミの話をしよう」で改めて映画監督としての自らと向き合った。自問自答の末、できあがったのは脚本家・演出家としての主戦場である舞台への“原点回帰”だった。編集だけで1年かけ、体得したものへの手応えと、裏腹の不安…。面白いものが湯水のように湧き出てくると誰もが期待する希代のクリエーターに、2つの顔がかいま見えた。【村上幸将】
★舞台とのハイブリッド
主人公スオミが失踪し、物語の舞台となる寒川邸のリビングの絢爛(けんらん)豪華さや、映像としてはやや大きい俳優の芝居などは舞台的である。一方で、一方向からの映像が多い舞台を収録した映像とは一線を画し、場面をあらゆる方向から映し出すダイナミックな映像は映画だ。「舞台と映画の究極的なハイブリッドでは?」と投げかけると、三谷は「うれしいですね」と口元をゆるめた。
「舞台の人間だしドラマの脚本家だから、映画監督という意識や、映画をちゃんと作品として残していくイメージが実はあまりなくて。でも、さすがに9本目になり、本当に自分しか作れない映画ってどんなだろうか、人は僕にどんな映画を期待しているんだろうか、と考えていくと、原点回帰というか…ある意味、開き直って、今までで最も演劇的な映画を作ってみようというところから始まった」
寒川邸のリビングは「当て書きした」と口にするほど注力した“裏主役”と言っても過言ではない。
「舞台、演劇的な映画にすると言っても、一方向からだけ撮るものだと、面白くない。一点集中的に皆さんの力を借り、すごくすてきなリビングルームを作り上げ、とことん、撮って全部、映してしまおう。そのために俳優さんとカメラが、どう動けばいいかという発想からやった」
★1カ月前から稽古も
クランクインの1カ月前から、舞台のように稽古も行った。準備の徹底は、尊敬してやまない米国のビリー・ワイルダー監督と対談した際にもらった「準備して、しっかり作ったものは成功する」という言葉を実践したものと言えよう。
「かも知れないですね。美術もそうだし、映画ではほとんど、そういうことはないんですけど、俳優さんになるべくたくさんリハーサルをやらせてもらった。特にリビングの男だけのシーンは、本当に舞台のように稽古させていただいた」
★批判にも確固たる信念
「自分の中で、自分が映像作家みたいなイメージは全くない」と言う。一方、そんな自らの映画への批判的な声も耳に入ってくるが、気にしたことはない。確固たる信念があるからだ。
「俳優の演技の質も含め演劇的だとか、映画のリアリティーが分かっていないんじゃないか? とか必ず言われる。カット割り、画作り含め映画らしい映画を作ることが(自分より)得意な方は山ほどいらっしゃると思う。でも僕の中では、あまり気になっていなくて。結局、面白い映画と面白くない映画があるだけ。演劇的な映画が面白くないわけではないし、映画的に作った映画にも、面白くないものはあるから」
映画作りのルーツは、幼稚園入園前にさかのぼる。母方のおじと実家で、怪獣のフィギュアを使い、地球に襲来した怪獣と戦う自分が主人公の「大怪獣の逆襲」を、8ミリビデオで撮影。大学時代には映画監督への登竜門ぴあフィルムフェスティバルに応募したが…。
「『あなたの隣の切り裂きジャック』という、日本にやってきた切り裂きジャックを追い払うサスペンスだったんですけど。大学生が作る映像作品って撮り方、編集に凝った10~15分のものが多い中、僕の作品は、ものすごいせりふ劇で1時間以上。そんなものが通るわけがないし、今、見ても面白くも何ともない、ひどい自己中心的な映画。映像作家の作品ではない、全く真逆のもので、箸にも棒にもかからなかった」
そのことが、演劇の道に進む転機となった。
「自分が作りたいのは、映像に凝ったものよりストーリー性だったり、セリフの面白さで引っ張っていくものなんだと。そこで、いったん映画を作ることをやめ、演劇の世界に入って真剣にやるようになった。そこが自分の分岐点だから…やっぱり自分の中では、映画監督ではなく脚本家で、映画を撮るとしても脚本家が作る映画なんだ、それしかできないんだという思いが、いまだにありますね」
★97年映画監督デビュー
主宰の劇団東京サンシャインボーイズの93年の舞台「ラヂオの時間」を映画化して、97年に監督デビューした。その裏には、テレビで作った、どの作品も「自分が考えて作ったシナリオと出来上がったもののテンポの違い」が、すごく気になっており「自分の理想のタイミング、テンポ、スピード感の映像を1回、作ってみたい」思いがあった。それから27年。「スオミの話をしよう」を作り上げ、得たものは大きかった。
「目の前に、映画をどうやって作るかという材料が山ほどあったんだけど、気づかなかった自分がいて。9本目にして、やっとこんなテクニックもあるのかと。絵の具の使い方が分かったので、もっと絵を描いてみたい…そんな感じに近いかも知れませんね。やっと(映画監督として)スタートという感じ」
94年から充電期間に入っていた東京サンシャインボーイズも、来年2月に30年ぶりの復活公演「蒙古が襲来」を上演。期待の声が高まる中、裏腹の不安を口にした。
「自分のキャリアというか、年齢というか…今後、どれくらいのものが、幾つできるのかと考えていくと、すごく不安にはなるんですよね。じゃあ、自分にとって舞台、映像、映画の代表作はあるのかと考えると、まだこれからのような気がしていて。すごく焦るんだけど、やらなきゃいけないことだなという感じが今はしています。そんなことばかり言っていられないので、今まで培ってきたものの上にちゃんと代表作となるものを作っていきたい」
人生の残りの時間と、向き合わざるを得ない年齢になった。
「どうしても、そうなりますね。あまり今まで考えていなかったんですけど。20、30…40代も、無限の未来があるような気がしていたんですけども。意外にそうじゃないということが50、60代で見えてきたので…ちょっと焦りますね」
今後、どのような作品を作りたいのかと尋ねると、思わぬ答えが返ってきた。
「映像に限って言うと、僕は、まだ理想のコメディーを作っていない。ビリー・ワイルダーで言えば『お熱いのがお好き』は、純然たるコメディーとしか言いようのない作品なんだけども、じゃあ、僕の作品で同じようなことが言えるものがあるのかと言ったら、ないんですよ。だから、本当に、それは1回作ってみたい…作らなきゃいけないものだなと思っています」
★暗い影が漂う瞬間も
舞台あいさつなどで見せる底抜けに明るい顔、言動とは裏腹に、眼鏡の奥の瞳が見えないほど暗い影が漂う瞬間もある。その、どちらも“5つの顔を持つ女”スオミを生んだ、三谷幸喜の“今の顔”なのだろう。
▼長澤まさみ(37)
三谷さんは、いつも期待に負けないのがすごいなと思う。期待されればされるほど、自分に自信をなくしたりプレッシャーに尻込みしてしまったりとか、すごく難しいことだと思う。それを何の苦労も感じないくらい、陽気に乗り越えてしまう。皆さんをワッと驚かせ期待をどんどん超えていく…そんな、やる気に満ちあふれた三谷さんのままでいてもらいたい。どんどん面白い作品を生み出し続けて欲しいなと、1ファンながら思っています。
◆三谷幸喜(みたに・こうき)
1961年(昭36)7月8日、東京都生まれ。実業家の父が中洲でクラブを経営した関係から2歳まで福岡に在住。日大芸術学部在学中の83年に東京サンシャインボーイズを旗揚げし主宰、座付き作家、演出家として「12人の優しい日本人」などがヒット。学生時代からテレビ番組の構成に携わり、94年の劇団休止後、ドラマ演出、映画監督としても活躍。代表作はドラマ「古畑任三郎」シリーズなど多数。血液型A。
◆「スオミの話をしよう」
スオミ(長澤)が詩人の夫・寒川しずお(坂東彌十郎)の屋敷から失踪。警察官(西島秀俊)使用人(遠藤憲一)刑事(小林隆)YouTuber(松坂桃李)の元夫4人が集まるが、各人のスオミのイメージは異なり、5人は右往左往する。










![[ハリウッド・メディア通信] ティム・バートンが米ハリウッド殿堂入りを果たしウォーク・オブ・フェイムに名を刻んだ ! 新作『ビートルジュース ビートルジュース』の話題](/img/article/20240920/66ed1e837dbc0.jpg)