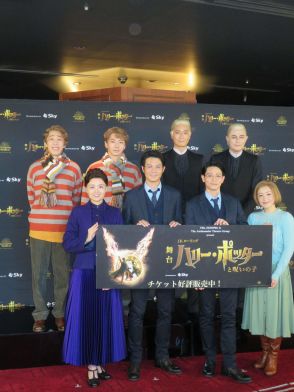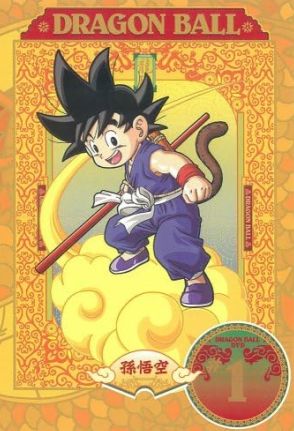永井真理子インタビュー「やらなければいけないと思ったのは、新しい曲を作るということ」
永井真理子が1987年にデビューしてから、音楽シーンで一躍注目を集めた経緯を振り返る。
プロを目指す意識が強くなかったが、音楽に恋をしてデモテープを作成し、デビューに繋がったエピソード。
プロデューサーに好印象を与えた永井真理子の熱意と歌声によってデビューのチャンスが訪れた。

1987年のデビューから、瞬く間にシーンのトップに躍り出た永井真理子。「ミラクル・ガール」、「ZUTTO」などのヒット曲とともに、ショートカットにクラッシュデニムというスタイルで飛び跳ねるように歌う彼女の姿は鮮烈だった。アーティスト/シンガーとしてのあり方を模索した90年代、音楽活動から遠ざかった2000年代半ば以降を振り返りつつ、10年ぶりに復活した2017年から続く永井真理子の「今」を語ってもらった。
――デビューまでの経緯がありそうでないパターンですよね。ざっと言うと、デモテープを作ってアポなしでレコード会社に持って行き、たまたま取り次いでくれた方が後々のプロデューサーで、その日に音源を聴いてもらうことができ、そのままデビューにつながると。なんかすごいです(笑)。
しかも音楽をはじめて半年経つか経たないかくらいの頃だったので。
――そうなんですか!
だから毎日起きるたびに、あれ? 夢じゃないんだ?って思うくらい次々に新しい扉が開いていくような状況でした。
――そもそも音楽をはじめた時点でプロを目指していたんですか?
プロという明確なところまで意識として持てていたかどうかはわからないんですけど、音楽をはじめる前――高校の3年間は全寮制の学校で、ものすごい狭い世界の中で生きていたんです。そこから短大への進学で東京に出て、一気に弾けたんですよ(笑)。何がやりたいの? 音楽がやりたい!って。それで何もわからずに他大学のサークルのバンドにコーラスの空きがあることを見つけて、なんでもいいからやりたい!って言ってそこに入れさせてもらったら、もう歌うことが本当に楽しくて仕方がなくて、プロになるとかどうとかよりも、音楽をやることに恋しちゃったっていう感覚だったんですよね。ご飯食べなくてもいいから歌っていたいっていうくらいの気持ちでした。だからデモテープを作ったのもその勢いなんですよ。で、作っただけでなく持っていっちゃったっていう(笑)。ほんとに何にもわからなかったからそんなことができちゃったんですよね。普通に音楽業界の知識が少しでもある人なら、「そんなの無理に決まってるじゃない!」って思いますよね(笑)。
――何かに夢中になるバイタリティというのは、子供の頃からそういう性格だったんですか?
基本的にはそうだったと思うんですけど、ただ人見知りで、あまり人前に出るのが得意ではなかったんですよ。だから内に秘めたものはあったんですけど、じゃあ実際に何か具体的なアクションを起こせていたのかといえば、何も出来ていなかったっていうのが現実でした。そのひとつが音楽だったんです。ギターの練習をコソコソしたりはしたんですけど、人前でやったりすることはとても出来なかったし、うちは父親が厳しい人だったので、まずそんなことをやっているっていうこと自体も秘密にしてたし(笑)。
――で、全寮制の高校時代もあって、ひとり暮らしを機に一気に弾けたと。大学のサークルでバンドに入って、そこから自分でデモテープを作ったのはどういうきっかけがあったんですか?
そもそもそのバンドのメンバー募集には「プロ志向」って書いてあったんです。プロっていうのがどういうことなのかはわからなかったけど、ここは本気でやってるに違いないって思って私は入ったんです。なのに半年もしないうちにみんな就職活動とか始めちゃって。ちょっと待ってよって(笑)。そこで何か悔しくなっちゃって、だったらひとりでもやってやろうじゃないかってデモテープを作ろうと思ったんです。その時に出会ったのが、現在も作曲家として活躍している前田克樹さんだったんです。彼は私の入っていたバンドのギタリストの人の同級生だったんですよ。それで、前田さんに手伝ってもらいながらデモテープを作ったんですけど、その中には後に私の代表曲にもなる「One Step Closer」がすでにあったんです。
――デモテープを作る時点で理想とする音楽像というものがあったんですか?
いえ、とにかく歌いたいっていうことだけでした。前田さんが私の歌声とキャラから、こういう感じが似合うんじゃないかっていうものに、ご自身の好きな音楽をブレンドしてできていったんですけど、それがうまく私の気持ちにハマってスタイルになっていったんです。
――デモテープを最初に聴いてくれたプロデューサーの方は、永井さんのどこに可能性を感じたか、というのは伺ったことはありますか?
声がすごく好きだっていうことをおっしゃっていただきました。レコード会社の裏にあるカフェで聴いてもらったんですけど、「今聴いてください!」って言った私の目力がものすごくて、炎が見えたって(笑)。
――なかなか断りづらいですね(笑)。
あはは。そうですよね(笑)。それと、これは後から聞いたんですけど、当時そのプロデューサーさんは他のレコード会社から移って来たばかりだったから、せっかく新しいところで始めるんだったら、若い才能を一から発掘して世に送り出したいって思っていたんですって。そんなところに、炎の目の私がやって来たみたいです(笑)。