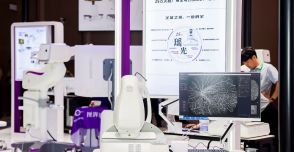小児科の教授がおらず当直医が新生児手術、「一生障がい」の責任は誰が負うのか=韓国
外科教授が小児外科の救急手術を行い、手術ミスがあり再手術を受けた新生児の訴訟事件が争われている。
一次手術で手術法の不備があり、後遺症が起きたため、病院に責任があると認定された。
医療界では、小児外科専門医の不足から今後も同様の事例が増える恐れがある。

小児外科の教授がおらず異なる外科の教授が新生児の救急手術を執刀した。
この時、新生児の疾患に使われる手術法を知らなくてやらなかったとしたら病院の責任はどれくらい認められるだろうか。1審は「責任がない」と見たが控訴審は「一部責任がある」と交錯した判断を下し、大法院(最高裁)が1年間審理を続けている。
控訴審裁判部であるソウル高等法院(高裁)民事17-1部(部長判事ホン・ドンギ、チャ・ムノ、オ・ヨンジュン)が昨年10月に「病院が約70%の責任を負い、その間の治療費や未来治療・看病費、慰謝料などを支給しなければならない」と判決しながらだ。
事件は2017年三一節(独立運動記念日)を控えた連休に発生した。生後5日の赤ちゃん(A)がたびたび緑色を帯びた吐瀉物を嘔吐したため急遽(きゅうきょ)小児青少年科外来を訪れたが、小児科医師は「腸回転異常症・中腸軸捻転」と診断して直ちに救急手術が必要だと判断した。腸が絡まった状態が長く続けば腸に血液が行き渡らなくなり、腫れて炎症を起こして深刻化すれば腸が壊死して死亡に至る恐れがあるため、直ちに手術が必要だ。
この病院には当時連休で小児外科医師がなかったが、遅滞する場合には命に関わると判断し、当直だった外科教授が救急手術を行った。膿が溜まっているなど壊死直前だった腹の中の炎症を洗浄し、絡まった小腸を正常な位置に戻した後、手術を終えた。
だが外科教授が見逃していたところが1カ所あった。腸回転異常症を持っている赤ちゃんの盲腸が正常ではないところについていたため、盲腸を腹の後ろ側に固定させて帯を切って腸を通常の位置と同じように再配置しなければならなかった。小児外科細部専攻医ではない執刀医はここまで考えが回らず、赤ちゃんは結局また腸が絡まって2日後に再手術を受けた。この時は小腸の大部分が怪死し、上部15~20センチだけを残して盲腸まですべて摘出しなくてはならない状態だった。
翌年5月赤ちゃんは嘔吐などで再び入院治療を受ける過程で無呼吸症状を示して集中治療室に入り、脳異常が生じて発達遅延や四肢マヒ、認知低下などの障害も現れるようになった。これに対して赤ちゃんの母親は病院と外科教授、小児科主治医に対して逸失損害および今後の治療費などを請求する損害賠償訴訟を起こした。▽小児外科専門医ではないが手術を執刀して1次手術でミスをして▽観察を粗雑にして2次手術が遅れ▽1年後の入院治療当時、過失によって永久的障がいを持つことになった--などの理由だった。すると病院もAの未納診療費合計2億3683万ウォン(約2500万円)を求めて訴訟を起こした。
◇1審「病院には責任ない」、控訴審「それでも手術法は守らなくてはならない」
1審を担当したソウル中央地方法院は病院側勝訴とし、A側に未納診療費をすべて支払うよう命じる判決を出した。「小児外科細部専門医でなくても外科専門医なので手術には欠格がなく、別の病院に連れて行って時間を遅滞すれば悪化していただろう」と判断した。
反面、控訴審裁判部はA側が控訴審で請求した約15億ウォン余りのうち70%を病院責任と判断し、約10億ウォンを賠償し、そのうち1000万ウォンは手術した外科教授も一緒に責任を負うように命じた。新生児で発生する特徴的な疾患には決まった手術法があるが、それに沿って行わなかったため再発および腸切除をすることになったとし、手術の過失を一部認めながらだ。また、腸が短くなって後遺症である栄養欠乏・免疫低下・感染などで脳病障がいが現れることがあるという鑑定医の分析を根拠とした。ただし、小児科主治医は手術に参加しなかったため責任がないと判断した。病院側は逆転した2審結果を不服とし、直ちに上告した。
医療界では救急状況でこのような状況が今後も多く発生するだろうと指摘する。2024年現在、外科専門医8800人のうち外科学会が2013年から発行している小児外科細部専門医は73人だけしかいないためだ。