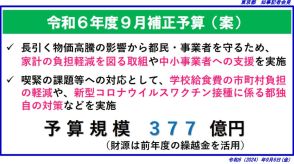【対談連載】ソフトクリエイトホールディングス 代表取締役社長 林 宗治(上)
林氏家族と経営哲学についてのエピソード。
宗治氏の趣味と経営スタイルについて。
宗治氏が愛用するチタン製タンブラーについて。

【渋谷発】5年前の2019年。本紙前主幹・奥田喜久男がソフトクリエイトホールディングスの創業者・林勝会長のもとを訪れた。当時74歳でありながら「あと10年は現役を続けたい」との言葉は強く印象に残るものだった。そして現在は長男の宗治氏が2代目社長を務めるソフトクリエイトを再訪。32歳で社長に就任された宗治氏ならではのお話を伺うと、先代とは違う個性あふれる興味深い話が次々と飛び出してきた。
(本紙主幹:奥田芳恵)
●幼い頃から
「社長になるんだよ」と言われ続けて…
芳恵 前回、19年に本紙がお父さま(会長)とお話をさせていただいて、そのときに「あと10年は現役でやりたい!」とおっしゃっていました。今回は宗治さんのかじ取りについて知りたくて、お話をうかがいに来ました。
林 その折は芳恵さんのお父さまがいらしていましたね。
芳恵 そうです。先代が宗治さんのことを「ある程度組織ができあがってから上に立つタイプ」、弟さんのことを「突撃型」だとおっしゃっていたのですが、そのあたり、ご自身はどう思われているのでしょうか?
林 うーん、性格の違いというよりも、扱っているビジネスの性質の違いだと思います。弟がやっているEC(電子商取引)の世界というのは、一つの世界で完結しているんですね。どの社が敵で、どの社が味方か、ということがはっきりしている世界です。ですからビジネスの方向性はあらかじめ定まっているんです。しかし僕が扱っているIT全体のソリューションということになると、事情は異なります。一社だけで済む話ではなくて、PCを売る会社、クラウドを提供する会社などそれぞれが集まりますから。ときには仲間としてアライアンスを組まなければなりません。でも、それでいて、それぞれの会社は別のところではライバルであったりと、関係が複雑に入り組んでいるという事情があります。
芳恵 すると、経営手法もまったく違うものになってくるわけですね。
林 そうですね。複雑な分、僕1人ですべてを仕切ることができるかというと、そうはいかない世界になってしまいます。ですから子会社の社長に権限移譲をしていく、というようなやり方が必要になってきます。組織上、ほかの選択肢がない、という事情も出てきます。
芳恵 ところで宗治さんは32歳という若さで社長に就任されたわけですが、経営者としてのキャリアが浅いことによる恐れだとか不安みたいなものはなかったのでしょうか?
林 上場企業の社長としては若いほうだなという認識は、当時はもちろんありました。不安がなかったと言えば嘘になるのかもしれませんが、やるべきビジネスというのはすでに目の前に広がっていましたし、社長になるイメージ、心の準備に関しては幼い頃からの刷り込みみたいなものが確かにあったと思います。
芳恵 幼少期から、いずれ社長になるんだとお父さまから直接言われたりしていたのでしょうか。
林 そうですね。父からはもちろんですが、祖母からもそう言われていました。家業、ファミリー企業だということはわかっていました。
芳恵 親族揃って、というわけですね。そうすると幼少期から将来を見据えた行動を取るようになるものでしょうか?
林 いやー、そこはどうでしょう。親がそんな心づもりをしていたかどうかはわからないですけれど、わが家がPC屋、というのはありましたから、子どもの頃から自宅でPCを触る機会が多く、そういった環境には恵まれていました。進学先もたまたま経営学科でしたし。就職先もこの業界、ソフトバンクで、幸か不幸かネットワークのエンジニアになったというのもあります。当時、米Cisco Systems(シスコシステムズ)の製品などをソフトバンクも扱うようになった頃で、いきなりネットワーク系統に触れることになりましたね。
芳恵 ネットワークエンジニアとしてのスキルはソフトバンクに就職してから身につけられたわけですね。
林 そうですね。ただ、リアルなネットワークエンジニアとしての実際のスキルは会社に入ってからですけれど、大学生の頃もショップで土日働いたりしていました。秋葉原にはしょっちゅういましたよ。ネットワークセンターといって、ネットワーク系のケーブルを大量に扱うお店でアルバイトもしていました。だから僕、ケーブルにはかなり詳しいんです(笑)。
芳恵 そうだったんですね! では、小中学生のときはどんな子どもだったんでしょう。好きなものだとか。
林 まず、わが家にあるのはファミコンではなくてPCでしたね。
芳恵 それは幼い頃からこの業界に入るよう仕組まれていたのかもしれませんね(笑)。
林 あー、そういうのはあるかもしれませんね。ファミコンを触る代わりにPCだったという。あとは、生き物が好きだったので、魚や虫なんかを捕ったり飼ったりするのが好きでした。実家は自然に恵まれた場所でしたし、キャンプなんかに行っていろんな魚や虫を捕ったのがいい思い出です。
芳恵 今の宗治さんのイメージからは少し想像がつきませんが…(笑)。
●多趣味に通じる共通点は
努力次第で世界が変わること
芳恵 宗治さんはとても多趣味にお見受けします。ゴルフもやっておられますね。
林 基本的には何かに「没頭」するタイプです。釣りも好きですし、ワインにしてもそうですし、ケーブルに異様に詳しくなったのもそうです。
芳恵 昆虫も、ということになるのでしょうか。釣りには生き物が好きだったという影響もあるのでは?
林 それはあるでしょうね。実は釣りを始めたのにはちょっとしたきっかけがあって。あるとき腕をけがしてしまったんです。入院するほどの重傷でした。それで、しばらくゴルフができなくなってしまって、でも外に出たいと考えた末、釣竿のリールを巻くだけならできるかもしれない、と思って釣りをやってみたんです。
芳恵 えっ!? そんな経緯があったんですね。
林 でも、けっこうハマりました。というのも、釣りって体力とか感覚の上に成り立っているんじゃなくて、いろんなテクノロジーと知識の積み重ねだからなんですね。いつどこにどのタイミングで行けば釣れるのかを知ることが一番大事なんです。そういった知識を得ようとするとネットワークを持たなければいけないし、人からものを教えてもらうためには自分からも提供できる知識を持っていないといけない。
芳恵 道具一つとっても変わるでしょうしね。
林 そうなんです。とにかく知識量が必要な世界です。
芳恵 そう考えると、知ろうとする努力次第で世界が変わっていく世界にハマるということでしょうか。ワインにもそういった側面がありますよね。
林 その通りです。沼の世界ですね(笑)。ワインも知識と技術の粋というところでは同じで、いつもそういうものにハマってしまうというか。今、僕はチタン製のタンブラーを毎日使っているんですけど、これも知識と技術の粋、というところがあって。燕三条地域(新潟県)のメーカーのものですが、チタン製で中が真空になっているのに、飲み口が薄く仕上がっていて。そこが技術ですね。それでいてデザインも良くて、保温機能があってワインでも日本酒でもこれで飲めます。もちろん熱いものも飲めますし。
芳恵 終わりなき追求の世界がお好き、ということでしょうか。
林 そうですね。変数が多い、終わりなき世界ですね。それと、自分はこれが大好きなんだ、ということ、実際にその「好き」が持続していることを周囲に伝えることで、自分が何を大切にしているか示すきっかけにもなります。あと、ワインなんかはフレームワークが完成された世界なんです。知識の集まりです。うまくいかなかったときに工程を振り返って、何が足りなかったのか検証しやすい世界ですね。継続もある。そういったところにハマりやすいというのは、じつは仕事上での考え方にもつながっています。大きな問題に直面したとき、工程を因数分解して検証することが重要だと思っています。社員にもそう伝えています。
芳恵 お母さまはどんな方だったのでしょう?
林 母方の実家は東京の新橋で洋酒屋をやっていました。銀座にも上顧客がいたので、高級ウイスキーも扱っていました。そういう意味では食文化という環境には恵まれていたんだと思います。あと、一度自分の家系図を徹底的に調べてみようと思ってさかのぼったら、母の祖父は大正時代に銀座でもわりと有名な寿司屋だったことがわかって。母方の祖父も釣りが好きで。自分の趣味はそういうところに由来してるのかー!と思いましたね。
芳恵 宗治さんの今をかたちづくっている面白いエピソードですね。次号では「スピード重視」という独自の経営スタイルについて伺っていきます。(つづく)
●日々愛用しているチタン製のタンブラー
7年前、釣りの際にアタリ(魚信)を待つ間にも酒を飲みたいと考えて、「金物のまち」である燕三条地域(新潟県)のメーカーのタンブラーに出会う。保温性が高い真空構造を維持しながら、それでいて飲み口の薄さを両立している職人技のすごさについて、宗治さんは熱く語ってくれた。
心にく人生の匠たち
「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。
「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。
奥田喜久男(週刊BCN 創刊編集長)
<1000分の第355回(上)>
※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。