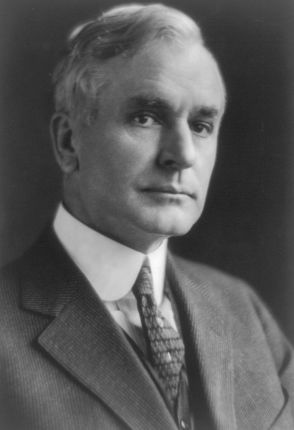和歌山毒物カレー事件を検証し直すドキュメンタリー映画『マミー』。監督がメディアに求めるものとは
1998年7月に和歌山市で起きた和歌山毒物カレー事件。地域の夏祭りで提供されたカレーに混入された毒物により、住民67人がヒ素中毒を発症し、4人が亡くなった。犯人として逮捕された林眞須美が死刑判決を受け、冤罪を主張している。
事件に異議を唱え、ドキュメンタリー映画『マミー』が公開された。監督の二村真弘は冤罪の可能性を検証し、メディアや報道に対する違和感を語っている。
映画は母親の呼び方である「マミー」をタイトルにし、眞須美さんの違った一面を伝えると共に、冤罪の可能性を広く訴えている。

1998年7月に和歌山市で起きた和歌山毒物カレー事件。地域の夏祭りで提供されたカレーに混入された毒物により、それを食べた住民67人がヒ素中毒を発症。このうち4人が亡くなった毒物混入・無差別殺傷事件だ。この事件の犯人として近所に住んでいた主婦・林眞須美が逮捕され、2009年5月に最高裁判所で死刑が確定した。林死刑囚は現在も無罪を主張し、再審を求めている。
事件発生から26年後。この判決に異議を唱え、冤罪の可能性を観客に提示するドキュメンタリー映画『マミー』が公開された。監督を務めたのは、今回が映画初監督作品となる二村真弘。検証を続けるなかで監督が感じた報道やメディアへの違和感や冤罪を語ることの意義とは?
※本稿は、作品のネタバレを含みます。あらかじめご了承ください。
―もともと和歌山毒物カレー事件にはどのような印象を抱いていましたか?
二村:事件当時、僕は日本映画学校の学生でした。創設者である今村昌平さんの作品をいろいろと観ていたのですが、犯罪に関する映画が多かったことから僕も犯罪心理に興味を持ちまして。それで映画の題材になるかもと、当時も割と熱心に報道を追っていたんです。
保険金詐欺の果てに夫にヒ素を飲ませるなど「林眞須美の悪意」がメディアで報じられていくうちに「こんな悪いことをする人がいるのか」と考えるようになり、これは彼女が犯人で間違いないなと確信してからは、事件について積極的に追うことはありませんでした。
―その後、林眞須美さんの長男が2019年に出版した書籍のトークイベントに行かれたとうかがいました。
二村:そのときは本を斜め読みしたうえで、林眞須美の長男はどんな人で、どのような話をするんだろう、という野次馬精神で見に行ったのが正直なところです。そのあとに長男のSNSをフォローして、しばらくしてから取材のために連絡を取り始めました。
―初監督映画となる本作で、和歌山毒物カレー事件という題材を扱った理由を教えてください。
二村:映画を撮りたくてこの題材を選んだというより、この題材を世に出すための媒体として一番効果があるものを考えた末に行き着いたのが映画だったんです。当初この事件を取材した映像は「digTV」というYouTubeチャンネルで配信していたんですが、僕自身、徐々に「これは冤罪の可能性が高い」と確信するようになりました。その段階でテレビ局やプロデューサーにこの企画を持ち込んだものの、「死刑判決が確定している事件で、冤罪の可能性を検証する番組を制作することは難しい」と難色を示されまして。
そんななかで知ったのは、ジャーナリストの伊藤詩織さんがご自身の性被害について書いた『Black Box』という著書です。出版直後、メディアはその本を扱うことを避けていたのかあまり注目されていませんでしたが、BBCが取り上げたことで逆輸入的に日本でも話題になっていって。
その経緯を見て、この事件も海外メディアに届けば広く伝えられるのではと思ったんです。それで「digTV」のときからずっと相談していた石川朋子プロデューサーと、海外の配信メディアや映画祭に10分くらいのトレーラーを持っていき、反応を見聞きしていくなかで「これは映画という選択肢しかない」と判断しました。
―海外からの反応は現段階で何かありましたか?
二村:まだ映画祭での正式上映はしておらず、完成形はまさにいま応募中(2024年8月時点)なので正確な反応はわかりません。ただトレーラーを観てもらった際には、「日本にはまだ死刑制度があるのか」と驚かれました。しかも眞須美さんが冤罪を訴えていて、その検証もされていないことに皆さん関心を寄せていましたね。
―『マミー』というタイトルにはどのような思いが込められているのでしょうか?
二村:長男が眞須美さんを「マミー」と呼んでいるんです。母親の呼び方って成長とともに「お母さん」「おかん」と変わっていくことが多いじゃないですか。でも長男は小学生5年生のときに母親と離れてしまっているので、彼のなかでは幼い頃の呼び方である「マミー」が残り続けていて。
僕と話すときは「母」と呼ぶんですが、健治さん(林眞須美の夫)といるときは「マミー元気だった?」と話すんです。彼ら2人だけの秘めたる呼び方のようで。その言葉は世間が眞須美さんに向ける先入観とはまったく異なる印象で、そちらのほうが彼女の本質に近いのではないかと感じたんです。それで眞須美さんの違った一面を見せる象徴的な言葉として、『マミー』という言葉を本作のタイトルに選びました。