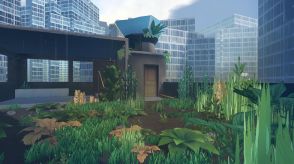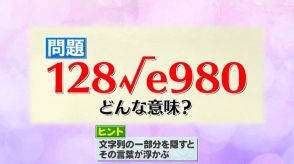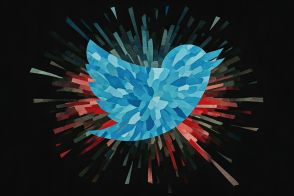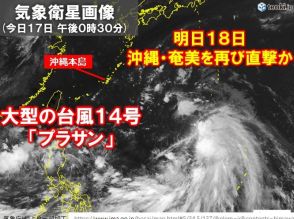ギャルが大ブーム。なのに、かつて渋谷を埋め尽くした"ガングロギャル"はどこへ行ったのか?
90年代後半の渋谷で台頭した「ガングロ・ルック」のギャル文化の源流を辿ると、ヨーロッパのビーチカルチャーが影響を与えたことが分かる。
ビーチへの憧れや開放感を肌に映すことである程度の経済力を持つエリート層の特権として生まれた「ガングロ・ルック」は、日本の若者にも浸透していった。
ビーチへの行き来が難しい若者たちは、渋谷を「ビーチ」と位置づけて新たな出会いやコミュニケーションを楽しむようになり、そこで「ガングロ・ルック」が確立されていった。

90年代後半の渋谷。そこでは肌を極端に黒く焼き、髪の毛を茶色く染めた、いわゆる「ガングロ・ルック」のギャルたちが街を闊歩していた。
「ガングロ」とは「ガンガン黒く焼いた肌」のこと。あの独特のスタイルはどこから生まれたのか? なぜ選ばれたのが渋谷だったのか?
『ガングロ族の最期 ギャル文化の研究』はメディア環境学を専門とする博士研究者・久保友香氏が膨大な資料と時代ごとの当事者への取材によって「ガングロ・ルック」の誕生から行く末を丁寧にひもといていく労作だ。
* * *
――「ガングロ」といえば渋谷にいたギャルの印象が強いですが、その源流をたどると、ヨーロッパ貴族までさかのぼるという、かなり壮大な話ですね。
久保 ヨーロッパの貴族たちが抱いていた海やビーチに対する憧れや開放感を「ビーチイズム」と名づけ、それを肌というスクリーンに投影した状態を「ガングロ・ルック」と、この本では呼んでいます。
当時の「ガングロ・ルック」は、パリから鉄道で24時間かけてビーチに移動できるような経済力を持った上流階級やエリート層のみが持ちえた特権的なものでした。その後、労働者が権利を獲得するに従って大衆層にも広まっていきます。
そして、ヨーロッパの映画スターがビーチを舞台に焼けた肌でバカンスを楽しむイメージは世界に伝播し、日本の若者にも届いたのだと考えられます。
戦後になると、大量に輸入されたアメリカのドラマや映画の影響もあり、「ガングロ・ルック」は日本にさらに浸透し、また独自の発展もしていきました。
――その文化が日本に輸入された当初は、湘南などのビーチに向かった「ガングロ・ルック」のギャルたちですが、時代が進むにつれていつしか本物のビーチを必要としなくなり、渋谷の街をビーチに見立てるようになったという視点も興味深いです。
久保 そもそも若者がビーチに求めていたものは人との偶然の出会いでした。学校や職場ではない場所で新たな出会いが生まれるのは海しかなかった。
しかし、ヨーロッパ貴族のような階層とまではいかないけれど、日本の高校生や大学生の若者がビーチに通うには、ある程度の条件が必要でした。車を持っているだとか、運転できる友人や恋人がいるだとか、限られた人が楽しめるものでした。
そこで、ビーチではない場所に、"人とつながれるビーチ"を見いだすコミュニケーションが生まれていきます。そのメインの舞台となったのが、湘南に電車で出られる渋谷だったのです。
調べていて興味深かったのは、「ガングロ・ルック」のギャルに先んじて渋谷にビーチを持ち込んだ存在がいたと気づいたこと。サーフィンをしていないのにサーファー風の外見をしている男性、いわゆる「陸(おか)サーファー」です。
――ビーチに行かずとも「ビーチイズム」を体現した先駆者が「陸サーファー」だったと!
久保 そうです。実際にビーチへは足を運ばずに渋谷の街をビーチに見立て、ビーチで太陽光を浴びるのではなく日焼けサロンで肌を焼き、海水を浴びることで髪が脱色されるのではなくブリーチ剤で茶髪にする。
そんな技術革新を用いた日本流の人工的な「ガングロ・ルック」のギャルの誕生につながっていったと考えています。
――それは本来なら「ダサい」ことであったはずですよね。
久保 雑誌などのメディアの力が強い時代だったので、サーフィンの上手な人がカッコいいとされた時代から、ストリート雑誌に載っている人がイケているとされるようになっていったのだと思います。そして、手段と目的が逆転し、街で目立つにはいかに肌を黒くするかが重要になっていくわけです。