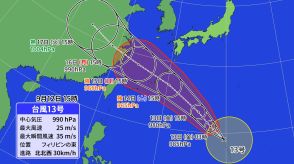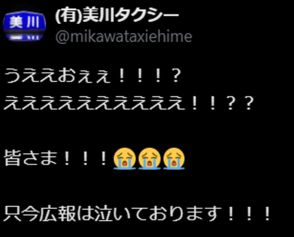太平洋戦争中、持ち主の命守った銃弾の跡残る刀現存 徳島城博物館で展示 阿波の刀工・吉川祐芳制作
太平洋戦争中、米の銃弾を受けたと伝わる吉川祐芳作の刀が現存し、徳島城博物館で特別展示中。
刀身には弾痕が残り、持ち主を守ったという逸話があるが、詳細は不明。
刀は軍刀として利用され、戦争を語る上で貴重な資料とされている。

太平洋戦争中、米の銃弾を受けたと伝わる刀(刃の長さ69・3センチ、反り1・9センチ)が現存し、徳島市の徳島城博物館で8月18日まで開催中の特別展で並んでいる。刀身には弾に撃たれた跡が残り、刀の持ち主を銃弾から守ったと伝わっていて「防盾祐芳(すけよし)」の号を持つ。作者は江戸後期から明治初期に阿波の刀剣界をリードした阿南市羽ノ浦町出身の吉川(きっかわ)祐芳(1833~97年)だが、刀の来歴や持ち主の名前は不明。他にも弾痕が残る刀は専門家の間で知られているが、一般公開は珍しい。
刀の表面には「安政三年八月吉日」とあり、1856年に作られたことが分かる。裏面に「祐芳作」との銘がある。江戸後期の刀を軍刀として利用しており、刀を納める鞘(さや)の表面に、刀には空から受けた機銃の弾の溶けた金属の跡が付着し、盾となって持ち主を守ったとの説明書きがある。鞘書きの筆者とみられる「青峯」や、鞘の裏に「防盾祐芳」の号がある。
学芸員の松島沙樹さんによると、戦争にまつわる弾痕が残り、命を守った逸話のある刀剣は一般的に知られていない。弾痕の信ぴょう性については機銃掃射の攻撃をまともに受けた場合、衝撃で原形をとどめない可能性が高い。この刀の傷は軽いため、刀の装飾に当たる拵(こしらえ)を付けた状態で弾がかすめたとみられる。
持ち主がどんな状況で弾を受けたのかは不明。軍刀は陸、海軍の将校、士官、騎兵や憲兵などに加え、複数の身分の軍人が利用した。騎兵ではなく歩兵が持っていたと推測できる。
鞘書きは著名な鑑定家以外の人が書く例もあり、現段階では青峯という筆者については不明。1994年に徳島城博物館が入手した。
松島さんは「吉川祐芳は幕末の阿波を代表する市井の刀工。彼の刀が昭和まで使用され続け、機銃掃射から持ち主を守ったという逸話が本当であれば、非常に興味深い物語。戦争を語る上でも貴重な資料といえる」と話している。
祐芳が作った刀の中には、徳川幕府の京都の治安維持部隊「新選組」局長近藤勇(1834~68年)が最後まで持っていた愛刀が知られている。その刀は、近藤の死後、板東俘虜(ふりょ)収容所長だった松江豊寿が福島県旧若松市長時代に所持していた。