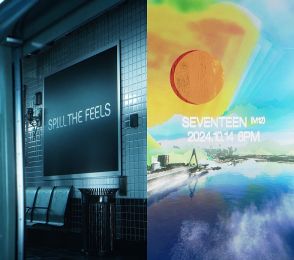中野雅之×小林祐介 THE SPELLBOUNDが語る、デジタルとAIが進化した先でのポップスのあり方
BOOM BOOM SATELLITESは1997年にデビューし、2016年に川島道行の逝去によって一時幕を閉じた。2019年に小林祐介をボーカルに迎えてTHE SPELLBOUNDとして活動を再開。
彼らは「音楽」の捉え方と「人生・生命」の捉え方が時代と共に進化し、リスナーに寄り添う音楽を追求してきた。新作『Voyager』では「生身の人間が、音楽に宿せるもの」をテーマに掲げている。
ボーカロイド音楽やAI生成音楽に対して、人間性が欠如したものとして捉え、自身の音楽制作においては人間性と感性を大切にしている。

1997年にヨーロッパにてデビューし、ダンスミュージックとロックを融合したラディカルなアプローチで国内外の音楽シーンを切り拓きながら、聴き手の心の深層をタッチし人生に寄り添う音楽を届けてきた2人組・BOOM BOOM SATELLITESは、2016年に川島道行の逝去によって一旦は幕を閉じた。そして2019年より、BOOM BOOM SATELLITESの大ファンでもあった小林祐介(THE NOVEMBERS)をボーカルに迎えてスタートしたのがTHE SPELLBOUNDである。
私は、トレンドに対する批評眼と音楽家の中でも圧倒的な精度で楽曲を作り上げる中野雅之(BOOM BOOM SATELLITES)の「音楽」の捉え方と、人生の大半を一緒に過ごしたパートナーの闘病と死去を経験した彼の「人生・生命」の捉え方が、時代によってどのように変化し、そして「音楽」と「人生」がどのように交わり合うのか、BOOM BOOM SATELLITESの後期から今に至るまでずっと追いかけてきたように思う。THE SPELLBOUNDとして2ndアルバム『Voyager』を完成させたこのタイミングでのインタビューでは、「生身の人間が、音楽に宿せるもの」がテーマとなった。
このインタビューは、8月21日、J-WAVE「SONAR MUSIC」にて「BOOM BOOM SATTELLITESの物語」が特集されて、自身がコメンテーターとして出演させてもらったあと、番組の反響の大きさ、THE SPELLBOUNDの新作『Voyager』の素晴らしさ、そして中野と小林が現在の音楽シーンや世の中をどう見ているのかを改めて聞きたいという想いから、取材を申し込んで実現したものだ。
―J-WAVEでしゃべる前、BOOM BOOM SATELLITESから今までの10年間、私が取材させてもらった記事を読み返していたんですね。
中野:僕、何言ってました?
小林:中野さん、基本あまり変わってなかったですね。
中野:そんなこともないんじゃないかな? 同じ人間がしゃべってる感じ、ありました?
―それはすごくあります。私も中野さんにずっと、「音楽って何ですか?」「人生って何ですか?」「中野さんにはどう見えてるんですか?」と聞かせてもらっていて。今回のアルバム『Voyager』に関しても、「音楽が鳴っているあいだの旅」と「人生という名の旅」といったテーマが軸にあることを感じました。最初から大きな質問を投げてしまいますが、THE SPELLBOUNDとして2枚のアルバムを作り上げた今、音楽が聴き手にとってどういうものであってほしいと思っていますか。
中野:音楽が持ってる力は未知数だし、100人いたら100人、音楽から受ける恩恵は違うと思うので僕が断定できることってそんなにないんですけど、願いとしては、よりよい時間、よりよい未来とか、ベタな言い方だと「元気になること」「今日も何かできそうな気がする」とか、そういうポジティブなことが起きてほしいなと。以前よりも、そういうことに自覚的になってきているかな。色々経験しながら歳を重ねているので、生きる中でどれだけ自分が幸せになれて、魂がなくなったあとのさらに向こう側まで――それが僕のいう「未来」ですけど――世界が少しよくなることを起こせるかどうかを、僕自身も考えるし、リスナーに対してもそういう時間を過ごしてほしい。そんな願いみたいなものは昔よりも強いし、そこに自覚的に音楽制作に取り組んでいると思います。僕は川島(道行)くんの、成長も挫折も、諦めも、受け入れるということも、全部凝縮された人生をずっと隣で見てきて、そこで学んだことも音楽活動全般に反映されていると思います。
小林:僕のエゴや中野さんのエゴを越えたところに、僕と中野さんの過ごした時間と関係性で生まれた「THE SPELLBOUND」という人格があって、THE SPELLBOUNDが持っている宿命や運命みたいなものがある気がするんですよね。しかもBOOM BOOM SATELLITESの物語を経ての今だからこそ、最初から「今のトレンドに対してカウンター」とかそういう話よりか、もっと普遍的で大きな話題になることが前提にあるんです。ただ「音楽を作ってる」というよりかは、自分たちが出会ったことで、あなたや世界にいいことが起こるように、ということを視界に入れている。大きく言うと、「僕とあなたが出会えたことはいいことなんだ」ということが、作品そのものにも、ファンとのコミュニケーションにも、僕らの生き方のフォームとしても、すごく強くある気がするんですね。そこをないがしろにした上で、ただ「かっこいい音楽を作るぞ」っていう瞬間は1秒もないんじゃないかなと思います。
―川島さんは亡くなられる前、ロックアーティストとして「頼れる存在として居続けたい」「聴いた人にとって、何かあったときに立ち戻れるようなマスターピースを作りたい」とお話されていましたけど、今作は、人生で何かあったときに頼りたくなる存在感や、人生におけるズタズタなシーンにも寄り添ってくれるような感覚が、さらに増した音楽であることを感じました。
小林:1曲1曲、ズタズタな人たちに寄り添うこととか、「エスケープゾーン」「桃源郷」といったキーワードは、中野さんとの話でもよく出るんですよね。今の世の中は、果たして自分の人生を自分の思い通りに生きていると言えるのだろうかと思うところもあって。自分の人生を自分で大事にして生きていたら、ズタズタになったり、ものすごく無茶苦茶なことになって病んでしまったり、そういうことは本来ないはずであろうと。歪んだ世界の中でそういうふうに生かざるを得ないところがあって、水の中で生きているような息苦しさが、正直僕は周りを見ていても感じるんですよね。その中で、あなたはあなたの幸せをちゃんと直視していいんだ、勝手に幸せになっていいんだ、と思ってほしい。この『Voyager』という作品は、鏡の中で自分と目が合って、「自分は自分の気持ちをないがしろにしてたな」「世の中のことばかり見てたな」「誰かが用意した画面ばかり見てたな」といったことに気づいて、自分の五感、肉体、心を取り戻すような体験ができる音楽だと思うんですよ。だから、単純に聴覚で聴く音楽を作っただけという感覚はなくて、ものすごく大事な体験ができる作品を作った気がしています。
中野:僕がデビューした1997年はまだ日本のバブル経済の余韻があって、音楽産業も活況だったけど、今は人々の目が死んでいると思うわけです。小林くんは僕よりひとまわり以上歳下で、ドラムの大井(一彌)くんはさらに下の世代なので――僕は彼をすごく優秀なミュージシャン、天才だと思っているんだけど――彼らや、彼らと同世代の人たちがどんな感覚で世界を見ているのか、未来にどんな希望を持って生きているのかを聞くんですね。すると大体、ネガティブな答えが返ってくるんです。「何も期待してない」とか、刹那的なんですよね。何も信じられないときに「僕らの音楽は信じていいんだよ、大丈夫だから」っていう場所を用意しておきたい。僕と小林くんは常日頃からいろんなトピックを取り上げて、人生の価値って何だろうかとか、そういうことまで話したり考えたりしながら作業に取り掛かるので、そんなアトリエの空気感の中から生まれている作品なんだと思います。
―「聴いた人を元気にしたい」と思っているアーティストはたくさんいると思うんです。そんな中でもTHE SPELLBOUNDの音楽がそれを高次元で成せていて、「癒し」「救い」といった力がここまで宿るのは、何がそうさせているのだと思いますか。
中野:これは聞く人によっては雲を掴むよう話に感じられてしまうかもしれないし、奇異なものとして捉えられてしまうと誤解を生むから、慎重に扱いたいんですけど……ひとつ、昔から思うことがあって。たとえば、人の声――歌声だけじゃなくて、喋り声、笑い声とかも――は、その人の内面の深いところから表れてくると思っているんですね。「この人の声は心地がいい」「この人の声は強さを感じる」とか、なぜそう感じるかというと、人間にはそれを感じ取る能力があるからで。端的にいうと「印象」だと思うんですけど。それは、その人のだいぶ奥底から出てきている、取り繕ろうとしても不可能なくらいに表れてしまうものだと思うんですよね。音楽も、様々なプロセスによって最終的には音声ファイルになるわけですけど、僕らの内面が乗っかっているわけで。その人の隠せない内面が声に表れるのと同じように、作られた音楽の中にはそういったものがいろんな形で宿っていて、それが聴く人に何かを訴えかけていたり、何かを感じ取らせようとしていたりするのではないかと。しかも僕たちはこじんまりとした空間で、僕と小林くんのたった2人で、一つひとつのフレーズや音色を自分たちの感性だけで精査して、その積み重ねがひとつの音楽の鳴りとして表現されているので、その純度は高いと思うんです。いろんな人がプロダクションに関わっていて、いろんな人のジャッジメントが入って最善のものが作られていくというプロセスも効率的だと思うし、羨ましい部分もあるんですけど、プロダクションの成り立ちが多くのポップミュージックと違うっていうところはあると思います。
―作家の内面が見えるものがポップミュージックとして素晴らしいのか? 鳴っている音だけで評価すべきではないか? 作家の存在感が薄いものこそポップミュージックとして大勢に受け入れられるのではないか? そういった議論、視点もありますよね。そこに対して、どういった考えがありますか。
中野:いろんな作品があっていいと思うし、いろんな作家性があったほうがいいと思う。「有名になる」「お金を稼ぐ」といった私利私欲が一切排除された音楽もあるだろうし、マッチョイズム全開のものもあるだろうし。それはすべて、その作家の生き方、人間性が表れているものだと思います。その中で、自分が音楽家としてどうありたいかを日々考えるわけですね。あまりにも表現欲求の薄い、訴えかける力の弱い、植物のような音楽になってしまっても、僕はきっと興奮できない。僕の年齢もあるのかもしれないけど、今の世界にヒップホップ的なマッチョイズムというか、せっついてくるようなメッセージもフィットしないとも思う。人とどうコミュニケーションを取っていきたいのかというところから、僕と小林くんの間で独自の作家性が生まれているのだと思います。
―今作には、歌声合成ソフト「Synthesizer V」の「夢ノ結唱 POPY」「夢ノ結唱 ROSE」に提供した「世界中に響く耳鳴りの導火線に火をつけて」「マルカリアンチェイン」のセルフカバーも収録されています。「生身の人間」とは真逆といっていい、機械が歌った歌やAIで作った音楽の可能性について、二人はどのように捉えていますか。
中野:是も非もないっていうのが正直なところかな。音楽制作の中でも、ミックスバランスの補正するポイントを教えてくれたり、流通に乗せるにふさわしいマスタリングをしてくたりするサービスがあるんですけど、自分の音楽を放り込んで返ってくる結果は、「うーん、そういうことじゃないんだけどな」みたいなことが圧倒的に多いですね。トラップ、EDMとか、フォーマットが固まってしまっていてTPOもできあがっている音楽に関しては、(AIが)かなり精度高く一瞬で作ってくれるんです。そこに人々が熱狂しているのを見ると、僕はどれくらい人間が手を動かして作ったかがわかっちゃうので、残念な気持ちにもならないし、「そんな感じで世界が進んでいるんだな」っていうことだけなんですよね。ただその音楽で、心の深いところまで手をグイっと突っ込まれることは、大概起きないですね。やっぱり人間の判断で行われることの中に、すごく大事なものがまだ宿ってるっぽくて。そういった、ある意味スピリチュアルな領域までAIの解析が進んでしまえば、どうなるかがわからないんだけど。音楽は映像に比べても、繊細な部分がたくさんあるんじゃないかなと思います。
小林:自動生成でいえば「こういう傾向があるからこういうものを出力しました」というパターン学習の結果でしかなくて、人間に変わるクリエイティブなことをするところまではまだ至ってない、っていうのは僕も同じ感覚なんですよね。フードプロセッサーとかの道具と同じで、今までだったら人が手作業でやらなくちゃいけなかった下ごしらえとかを、AIが自動的にやってくれて助かるということについてはポジティブな感覚を僕も持っているので、要は使い方だと思うんです。今回の制作は、人の声とか歌が持っている情報量っていうものの存在を改めて自覚した、すごくいいきっかけだったんですよね。「Synthesizer V」が出力してくれた音声は、パッと聴くと本当に人が歌ってるみたいだし、息遣いとかの演出もできるわけなんですけど、最初に中野さんが話してくれたように、人の声には宿っている「何か」があるんだなと思いました。自覚していなくても、人間はいろんなものをキャッチしているんだなって。AIの進化が止まることはないと思うので、それをどこまでキャプションできるんだろうっていうことにすごく興味がありますね。
中野:面白いよね。ボーカルデータがセッションに立ち上がったとき、明らかに何かがないんだよね。
小林:そうそう、「何か」なんですよ。
中野:明らかに何かがない。すごくリアルな歌声なのに、完全な空洞の部分がある。僕はそれだと音楽として充実感や満足感を得られないんですよね。初音ミク以前にも、ボコーダーとかコンピューターが叩き出す合成音声みたいなものってあって、それが音楽コンテンツの中に取り入れられたケースもあるけど、初音ミク以降の日本のサブカルチャーの中では、どれだけボーカリストとしての精度が高いソフトウェアでも、欠落している完全な空洞があるんですよ。「世界中に響く耳鳴りの導火線に火をつけて」「マルカリアンチェイン」については、その気色悪さみたいなものを面白く扱って音楽コンテンツとして満足のいくものにするのか、それとも、なんとしてでも作家としての魂をねじ込んでホットな音楽にするか、そういうチャレンジや葛藤がありました。だから壊れた機械みたいにむちゃくちゃ歌わせて、それをもう1回小林くんが歌ったときにどんなものが表れてくるか、という発想になったんです。それで見えてきたのが、新しいポップミュージックだった。そういう順番でことが起きていたんだよね。
小林:「Synthesizer V」にさらっと歌わせると、すごくパッセージの早い歌い回しとか、いろんなことをすごい解像度で出してくるわけなんですけど、僕がそれを自分の表現としてやろうとすると、必死に食らいついていたり、息も絶え絶えになったり、そういうところがパフォーマンスに出てきてしまうんですよね。そこに宿ってる「何か」っていうものが、メンタリティや技術も含めて、間違いなく人間性の何かだったりするんだと思います。
―ボカロ音楽がずっと人気があることも含めて、そういう「空洞」のある音楽やコンテンツに惹かれる人が多い時代だという見方もできる気がするんです。
中野:そうそう、そうです。人間的な魂がないものっていうのは、ゲームにも感じることが多いです。ボカロが好きな人は、「Synthesizer V」だと逆にリアルすぎるって思う人もいそうじゃない?
小林:そうそう。
中野:そういったコンテンツを通したときの二次元的な世界の見え方が自分にフィットする、ということがあると思うんです。空洞があるものというのは極めて二次元的だと思うし。ちょっと大きい話になっちゃうんですけど、僕が不安になるのは、コンテンツ消費で人生が埋め尽くされていくんじゃないかっていう。そんな人生は、何のために生まれてきて、何のために死んでいくのかが、本当にわからなくなってしまいそうで、それに対する危機感があるんです。大量のコンテンツを消費することで、五感「+α」の感覚――気配を感じるとか、人から温かみを感じるとか――を失っていて、人類は退化しているんじゃないかなって思うところもある。それは、空洞な音楽とか二次元的な世界の見え方に象徴される部分かなとも思うんですよね。やっぱり、五感以上の感覚みたいなところを僕は大事にしていきたいし、取り戻したいと思っているんだと思います。音楽体験でいえば、デジタルオーディオの周波数は20Hzから2万Hzまでになっているんですけど、たとえば今ここで生のドラムをプレイすると、それ以上の高周波が存在していたり、それこそ鼓膜では感知しないけど肌で感じたりすることが起きるわけですね。イヤホンで狭い範囲の聴覚だけで聴く行為が音楽の楽しみ方として一般的だと思うんですけど、本来だともっと壮大なサウンドスケープというものが世界には存在している。僕らは作り手として、「聴く」ということ以上の体験を大事にしていきたいと思っているんです。それが音楽の向こう側にある、力になるような感覚、希望が得られたような感覚、未来を思い描けたような感覚とかに繋がっていけたらいいんじゃないかな。
―だから『Voyager』は、最初に小林さんがおっしゃったように「トレンドに対して」みたいな批評性やカウンター精神は優先順位の一番ではないにしろ、二人が音楽を作ると必然的に浮き出てくるものではありますよね。
中野:そうですね。ポップミュージックの移ろいやトレンドの変化も楽しんでいるところはあって、「今、鳴らす音楽」ということについてはちゃんと考えているよね。
小林:そうです。同じ空気を吸っていることは自覚していますし。
中野:だけど、一過性ではないものにしたい。今これだけトレンドのサイクルが速いのは寂しいなって思うんですよね。100年後にも価値があるようにという気持ちで作りながら、今鳴ったときに「新しい音楽を聴いた」という感覚にもなってほしいなと思ってやってます。
―最後に、ライブについても聞かせてください。去年は『BIG LOVE TOUR』で「BOOM BOOM SATELLITES 25thAnniversary SET」と題して、小林さんがボーカルを務めながらBOOM BOOM SATELLITESの曲を演奏するステージがありました。THE SPELLBOUNDの初ライブからBOOM BOOM SATELLITESの楽曲は演奏されていましたが、今、BOOM BOOM SATELLITESの楽曲を歌うことに対してはどういった感覚がありますか?
小林:(THE SPELLBOUNDの)最初のライブで「BACK ON MY FEET」を歌ったときから比べると、引き続き責任感とかプレッシャーもあるんですけど、それ以上の大事な感情がどんどん大きくなっていますね。それはどんなものかというと、川島さんは今ここにいないんだけど、僕たちとファンがいる空間においてみんなで音楽を鳴らすことによって、ずっと存在し続けている。BOOM BOOM SATELLITESの曲を歌わせてもらえることの豊かさ、意味、価値は日々深まっていくばかりで、慣れることは全然なく、ずっとアップデートしている感覚があります。
―THE SPELLBOUNDの曲をやっている瞬間と、BOOM BOOM SATELLITESの曲をやっている瞬間の、小林さんから見えるフロアの景色や感じるものって何か違ったりするものですか?
小林:どんどんひとつのものになってきてはいますね。去年の『BIG LOVE TOUR』ではBOOM BOOM SATELLITESの曲を歌うときに川島さんの声をうっすら耳中に流していて、一緒に歌ってる感覚になるんですけど、いつもより自分が強くなったような気持ちとか、「いっちゃえいっちゃえ」って言ってもらったり支えてもらったりしている感じがあって。THE SPELLBOUNDの音楽をやるときはやるときで独特の感覚があるんですけど、それがどんどん混ざっていって、ひとつになっている感じがあります。
中野:僕、実はBOOM BOOM SATELLITSとTHE SPELLBOUNDという2つの違うバンドの中に線引きがあまりなくて。境目がなくなってきた感じがあって、いい時間の経過を辿っているんだなって思います。誇れるのは、楽曲が色褪せないことと、小林くんのパフォーマンスがカバーをやっている感じではなくリアルなロックミュージックを今鳴らしてる感じがあること。「何かが足りない」とか、「やっぱり川島くんの声が恋しい」とか、そういう感覚が僕は一切ないんですよ。(BOOM BOOM SATELLITSの楽曲は)僕らにとっていろんなことを起こしてきた楽曲たちですけど、ただみなさんの思い出を拾い上げるためだけに存在してるわけではなくて、今鳴る音楽としてちゃんと意味があるということを、演奏しながら感じることができています。だからすごくいいバンドだなって、僕も今感じられているんですよね。面白かったのは、去年小林くんと『BIG LOVE TOUR』をやったあとに、BOOM BOOM SATELLITSの映像ボックス(10月9日発売)の制作のために本家のライブをたくさん見ることになってしまって、どうかなと思ったら……「今、僕らがやってるライブ、すげえいいじゃねえか」って思えたんですよね。こう言ったら川島くんのファンに怒られちゃうかもしれないけど、それくらいのことが現場で起きてるから、まだ体験したことがない人は1回会場に来てほしいんですよね。
―中野さんがデビューから30年近く音楽活動を続けてこられた中で、今は、どんなところに一番の喜びを感じますか。
中野:純粋に楽しい。小林くんのクリエイティブがあってできていることだから、小林くんの力とか影響も本当に大きくて。「こんな音楽の可能性がまだあるんだな」っていう瞬間に立ち会うと、僕も小林くんも喜ぶんですよね。「こんなことって起きるんだね」みたいな。そういう瞬間が制作中に何回もあって、最後、曲を並べたときに「おお!」「僕たちが作っていた音楽はこんなことになってたんだね」ってなって。だからいい時間を過ごしているなと思っているし、これが聴いた人にとって、世界が少しよくなったらいいなって思います。人はやっぱり生まれたら必ず平等に死を迎えるので――長い短いの不平等はあったとしても――幸せになるためにこの世界をどう生き抜くかっていうことは、みんな真剣に考えたほうがいいんじゃないかなと思います。
<INFORMATION>
THE SPELLBOUND
『Voyager』
発売中
「BIG LOVE TOUR Vol.2 2024- Voyager -」
9/23(月祝)福岡BEAT STATION
9/28(土) 札幌PENNY LANE24
10/6(日) 仙台Rensa
10/27(日)名古屋CLUB QUATTRO
10/31(木)梅田CLUB QUATTRO
11/3(日) 六本木EX THEATER
『EXPERIENCED Memories Records ARCHIVES -Remastered-』(4枚組Blu-ray BOX、40ページブックレット、完全生産限定盤)
BOOM BOOM SATELLITES
2024年10月9日(水)発売