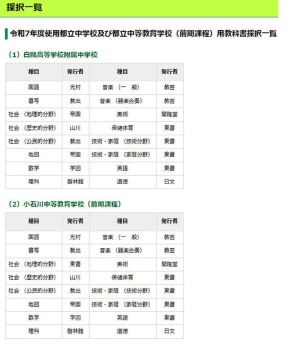高橋悠治+坂本龍一による幻の名著『長電話』とはどんな本なのか? 1984年の実験的アプローチを読む
1984年に出版された坂本龍一と高橋悠治による書籍『長電話』が2024年に復刊される。本書はメディアとパフォーマンスを融合させた独自の企画で、音楽や文化を超えた深い対話が展開されている。
坂本龍一が父親の影響を受け、本ならではの表現力を模索していた1984年。その時期に出版された『長電話』は、石垣島を舞台にした二人の音楽家による自由な会話を通じて、異なる視点から様々なテーマについて深く探求している。
2人の音楽家が持つ豊かなバックグラウンドや時代背景、書籍の構成やテーマに触れながら、『長電話』が当時から現代に至るまで持つ意義と魅力に迫る。

“高橋悠治+坂本龍一”による書籍『長電話』が、2024年8月30日に復刊される。
復刻版の販売を担うのは、坂本龍一の本への思いを継ぐ図書構想『坂本図書』。“幻の名著”と呼ばれたこの書籍が刊行された当時(1984年)の背景や内容について紐解いてみたい。
『長電話』は1984年、坂本が主宰していた出版社・本本堂から出版された。この年に出版社を立ち上げた経緯について彼は、2018年のインタビューでこう語っている。
「その年は、ナムジュン・パイクやヨーゼフ・ボイス、ローリー・アンダーソンなんかが日本にやってきて、いわば『メディアパフォーマンス』元年と言ってもいい年でした。そうしたなか自分も何かやりたいなと思ったときに、父親が編集者だったこともあって最もなじみの深いメディアとして本というものがありましたので、それを使って実験的なことができないかと考えたんです」(「坂本龍一、本の可能性を語る『本はパフォーマンスかもしれない』」The New York Times Style Magazine:Japan)
ナムジュン・パイク(1932年~2006年)はビデオアートの先駆者、ヨーゼフ・ボイス(1921年~1986年)はパフォーマンス・アート、インスタレーションなどを取り入れた作品で知られ、ローリー・アンダーソン(1947年~)は音楽、映画、マルチメディアなど幅広い分野で活動した現代美術家。1980年代の日本でこの3人は、アートとポップカルチャーをつなぐクリエイターとして人気を博していた(最先端のアートに若者たちが積極的にコミットする時代だったのだ)。そして“父親”とは、三島由紀夫、島尾敏夫、高橋和巳、埴谷雄高などの作品を手がけた編集者、坂本一亀(1921年~2002年)だ。
本本堂からの最初の刊行となった『長電話』も、出版社の立ち上げと同じく、メディア(情報を伝える媒体)とパフォーマンス(身体的な表現)をつなぐという発想から生まれた書籍だ。2人の音楽家、高橋悠治と坂本龍一が石垣島に赴き、同じ旅館の別々の部屋から長電話するというのが、本書の企画の骨子。わざわざ東京から離れ、(当時はまだリゾート化が進んでいなかった)石垣島に一緒に行き、あえて別の部屋から電話で話す。コミュニケーションにおける距離とは何か?というコンセプトがあったかどうかは不明だが、この企画自体が既にアートだ。
坂本、高橋の1984年の状況についても記しておきたい。
坂本龍一のキャリアにとって1984年は、YMO散開の翌年にあたる。1983年に公開された『戦場のメリークリスマス』への出演、劇伴によって世界的な知名度を得はじめた時期で、1984年10月には4作目のアルバム『音楽図鑑』を発表し、ソロアーティストとしても圧倒的な評価を得ていた。
高橋は1960年代から現代音楽、コンピューターを取り入れた実験的な音楽により世界的な知名度を得たピアニスト。70年代には武満徹、バッハ、そしてエリック・サティなどの作品集をリリースし、幅広い層の音楽ファンに支持された。1978年には、バンド・水牛楽団を組織。軍事クーデーター下にあったタイの抵抗歌を紹介するために活動をはじめ、全国各地でアジア、ラテンアメリカのプロテストソングを演奏した。1984年は、コンピューター、サンプラーなどを取り入れた作曲やライブに移行していた時期――と高橋のキャリアを簡単に記すだけで(現代音楽や印象派、コンピューター音楽など)坂本との共通点が多いことがわかるだろう。
書籍『長電話』に収められた2人の長電話は、1983年12月15日から17日にかけて計4回に渡って行われた。冒頭の会話はこうだ。
龍一 あ、もしもし。
悠治 はいはい。
龍 えー、ベッドにね、くつろぎました。
悠 え?
龍 ベッドの上でくつろぎました、という順序だと思うんで。
悠 へへへへ。だいたい、電話っていうものは好きなわけ?
龍 そうだなあ……、酔っぱらうと好きだな。電話したくなるよ、いろんなところに。
(長電話、大好き)
当時46歳の高橋、32歳の坂本はリラックス状態で、気の向くまま会話を繰り広げ、そのテーマはーー彼らの音楽と同じくーーあらゆる領域を超えていく。本書には会話のテーマごとに細かく見出しが付いているのだが、「スリーコード」「ロックンロール」「日本人の同質性」「ステージとオーディエンス」「シンセサイザーとピアノ」「健康な音楽」「水牛楽団」「コラージュ的録音技術」「終末論」「仕事の断り方」「広告と表現」「少女漫画」「顔で選ぶ」「日曜大工」などまさに多種多様。なんでもない雑談から音楽論、文化論に至るまで、どんどん話題が移り変わっていくのだが、それはまるで昨今のポッドキャストのコンテンツのよう。もちろん頭から読んでもいいのだが、見出しを眺めて興味があるものをピックアップするのも楽しい。
坂本は書籍『坂本龍一のメディア・パフォーマンス』(フィルムアート社)に収録されたインタビューで「まだインターネットもないころですが、本というデバイスは閲覧性も優れているし、後ろから読んでも前から読んでもいいし、飛ばして読んでもいい。あるページを読んでいるときに、パッと目次を見ることだってできる。とてもアクセシビリティが高いメディウムなわけです」とコメントしているが、1984年当時の坂本のメディアに対するアプローチが具現化された最初の本が「長電話」なのだと思う。
龍 ね。で、同じように思ったのはさ、演技っていうのも、見られないと演技とは言わないじゃない。しかも、見られてるだけじゃなくて、見られて、それが何を表しているか、意味が伝わんないと演技じゃないじゃない。それは何か滑稽なしぐさをしているだけであってさ、伝わってない場合は。だから了解されないと演技とは言わないし、とてもだから言葉に近いなとは思ったね。
悠 そうすっとなに、作曲をしながらある種の演技を行ってるっていうわけ?
(演技と作曲)
なんとなくページを開くと、こんな刺激的な対話が目に飛び込んでくる「長電話」。今回の復刊を機に、40年前に行われた二人の音楽家の自由で奥深い対話を気の向くままに楽しんでほしいと思う。