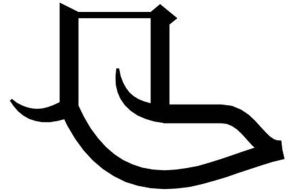アール・ブリュットの誤読と課題、そして可能性。山田創が語る「つくる冒険 日本のアール・ブリュット45人」
アール・ブリュットの概念と日本における受容について述べられており、日本のアール・ブリュット作品の特徴や背景、美術館が直面する課題に触れている。
日本のアール・ブリュット作品の特徴や展示された作家について紹介されており、その創造の源泉や制度からの外部性に焦点が当てられている。
アール・ブリュット分類の危うさや障害者に対するステレオタイプ的な見方について言及され、アール・ブリュットの概念を超えた視点での研究や活用の必要性に言及している。

アール・ブリュットの誤読と課題、そして可能性
日本におけるアール・ブリュットの受容──舛次崇、戸來貴規、小幡正雄、山崎健一
滋賀県立美術館では、4月20日から6月23日まで「つくる冒険 日本のアール・ブリュット45人」展を開催している。アール・ブリュット(Art
Brut、以下AB)は、1940年代にフランスのアーティスト、ジャン・デュビュッフェ
が提唱した美術の概念で、日本語では「生(なま)の芸術」と訳される。デュビュッフェは、精神疾患者や独学のつくり手が生み出す独特の表現に関心を持ち、これをABと名付けた。ちなみに「ブリュット(Brut)」はシャンパン用語で、加糖されていない生の状態を意味し、辛口の味わいを示す(デュビュッフェはワイン商でもあった)。
日本では2010年頃から、ABが美術や福祉の業界で話題となり始めた。その最大のきっかけは、2010年にフランス、パリのアル・サン・ピエール美術館で開催された「アール・ブリュット・ジャポネ(ART
BRUT
JAPONAIS、以下ABJ)」展であろう。この展覧会では、日本各地の障害者による作品が日本のABとして紹介され、現地で話題を呼んだ。同展は日本に凱旋し、国内の公立美術館を巡回した。パリからの逆輸入のかたちで、ABは日本での知名度を増し、同時に障害者による創作活動が注目を集めた。
ABJ展に出展した63人のうち、展覧会後に日本財団が収蔵していた45人のつくり手による作品が昨年8月、滋賀県立美術館に寄贈(一部寄託)された。本展は、この45人の作品をお披露目している。ここでは、そこから4名のつくり手を紹介しよう。
舛次崇は18歳の頃、通所する福祉施設で、兵庫県の絵本作家のはたよしこが立ち上げた絵画クラブに参加した。花瓶や工具、文房具といった日常的なモティーフを、大胆なかたち、少ない色で描き表した。
戸來貴規は岩手県の障害者福祉施設に入所していた頃、独特の図柄をB5用紙の両面に描き、黒い綴り紐で綴じることを繰り返していた。この図柄はじつは文字であり、この紙の束は、戸來にとっての日記であった。表面には日付、曜日、天気、気温、名前が、そして裏面には日記の本文が書かれているが、その内容は不思議なことに毎日一語一句同じものとなっている。
小幡正雄は兵庫県の福祉施設で暮らした。施設に届く段ボールを自室に持ち込んでは、赤鉛筆を使って「結婚式の男女」や「家族」、「乗り物」や「動物」を描いた。人間の身体や顔、また草花といった画中の要素は独特に様式化され、シンメトリーを意識した構図で描かれている。
山崎健一はかつて、建設現場の労働に従事していた。新潟県の精神科病院に入院し、方眼紙に製図道具を用いて、重機、乗り物、コントロールセンターなどのモチーフを、何千枚も描いた。山崎にとってこれらは「絵」というよりも「仕事」であると考えられていたようだ。
以上の4人を含む45人に共通するのは、美術的な潮流とは距離のある現場──その大半が障害者支援施設か精神科病院といった福祉的な現場(横浜の町中でパフォーマンスを行っていた宮間英次郎のような例外もあるが)で創作を行っていたということである。これらの作品からは美術の制度の外部から、「人はなぜつくるのか」というような問いを投げかけるダイナミズムを感じることができるだろう。
ところで、45人の創作は、日本全国各地の現場でばらばらに行われていたものだ。しかし、2010年には日本のABの名のもとで集合し、パリでの展覧会に出品され、そして現在、当館のコレクションとなった。この流れに大きく貢献したひとりに、前述の絵本作家・はたよしこがいる。彼女は、全国の福祉施設を訪問し、障害者(なかでもとりわけ知的障害者の割合が多い)のユニークな作品を取材して、知的障害者福祉協会が発行する月刊誌「さぽーと」に連載していた。はたは自分の足を使ったリサーチ活動により、独自の情報とコネクションを蓄積していた。
他方で、2000年代より、滋賀県近江八幡市にあるボーダレス・アートミュージアムNO-MAの運営母体である滋賀県社会福祉事業団(現社会福祉法人グロー)は、はたの助力も得ながら、日本の障害者作品を海外で紹介する事業を推し進めていく。そのピークのひとつといえるのが、ABJ展である。同団体はABJ展の日本側事務局を務め、はたは、出展者の選定に深く関わった。はたのリサーチ活動と滋賀県社会福祉事業団の海外事業展開の合流のなかで、全国各地の障害者の作品が「日本のAB」として海外へプロデュースされていったと解釈することもできるだろう。
こうした経緯から、日本のABは、デュビュッフェのそれと比較して、そのつくり手に知的障害者が多く、福祉との親和性が高いという独特の性質を持つという指摘(ときにはAB概念の誤読を広めたという批判の意味も込めて)が行われてきた。この度、日本財団から寄贈を受けた作品群は「日本のAB」の特徴を色濃く示し、国内のAB受容の歴史において重要な価値をもつといえる。
アール・ブリュットという分類の危うさ
2016年より、国内の公立美術館としては唯一、ABを収蔵方針に掲げてきた当館であるが、この度の寄贈を経て、当館のAB作品はこれまでの収蔵品とあわせて731点(寄託を除く)となり、名実ともに世界有数のAB作品のコレクションを有することとなった。この記事の最後の話題として、美術館がABを扱うということ自体について言及したい。
AB作品を巡る、美術館としての課題は様々ある。セロハンテープなど劣化が著しい素材がよく用いられるがゆえ保存・修復が困難であることや、作家の多くが福祉的なサービスを受けて暮らしていることから連絡調整や権利処理が用意ではないということ、マーケットが成熟していないことから作品の購入や保険加入のための金額設定なども難しいということもある。
加えて、この場で特筆しておきたいのは「ABという分類の危うさ」である。AB、またはアウトサイダー・アートの文脈で紹介されることの多かった坂上チユキは、2015年、当館で開催した「生命の徴 滋賀と『アール・ブリュット』」展および同展カタログの作家解説文にあたる箇所に、「私はアール・ブリュットに分類されるのでしょうか?」という彼女自身による言葉を寄せている(他の作家解説文は、学芸員による数百字の解説が割り当てられているので、彼女だけイレギュラーとなっている)。ときにABは、そう分類されるものの出自を、美術の外に位置づける装置となりうる。坂上によるたった24文字のセンテンスは、ABが不可抗力的に有する分類機能への違和感を鋭く表明している。
あるいは、ややこしいことに、とくに日本では「AB=障害者による美術」という短絡的な構図で認識されてしまいかねないという事情もある。ときにAB作品への評価として、「健常者には思いつかない」など、そのつくり手の障害こそが、創造の源泉かのように語られることがある。これはナンセンスな評価であるといわざるを得ない。なぜなら、そもそも障害はその人々の支援を目的に、医学的、法律的に定められているカテゴリであり、各アーティストの本質を言い表すものではないからだ。あるいは、すべての障害者が、クリエイティブに特化した人たちであるわけでもない。
こうした課題を背景に、たとえABとして収蔵した作品であったとしても、ときにはABという概念を相対化し、これらにとらわれない観点からの研究および活用をしていくことも必要である。さもないと、ABはそのつくり手をラベリングする呪いとなりかねないのではないか。
アール・ブリュットの可能性
いっぽうで、ABを美術館が扱うことの最大の利点は、従来は美術史と関わり得なかったであろう、創造の営みにアプローチできることにあると感じている。ABのつくり手は、福祉的サービスを受け、美術機関とは関わりを持たないケースが多く、美術館での収集に結びつきづらいといえるだろう。しかし、ABという収蔵方針は、それを掲げる美術館と、名もなき創作物をつなぐ回路となりえる。これまで、美術史に記述されにくかった人間の創造の営みを、未来へ継承することが、ABを巡る美術館の活動の意義であるといえるのかもしれない。