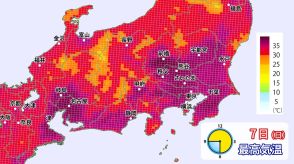「人口1200人の荒野の町」で朝の6時から営業するカフェ…無償で働き続ける華人の好々爺が語った「人生の哲学」とは
アフリカ大陸の東にある小国であるモーリシャスで、中国人経営の中華料理店が営まれている。この店には常連客が訪れ、オリジナルのメニューが提供されている。店の主は7年前に引退し、別の移民カップルが店を譲り受けているが、朝6時から毎日店に立ち続ける習慣を持っている。
ニュー・アウトルック・カフェという中国式カフェが、カナダの片田舎で存在している。このカフェには50席のボックス席や軽食用のカウンター席があり、地元の人々が訪れている。カフェのオーナーは広東省開平の出身であり、1959年から毎日朝6時に店を開店している。
中国人経営の中華料理店は、世界中様々な場所に存在しており、その地域に根付いたオリジナルのメニューや雰囲気が楽しめる。移民が開いた店には、歴史的背景やアイデンティティが反映されている。地球上の中華料理店を通じて、離散中国人の姿や意識を垣間見ることができる。

北米中華、キューバ中華、アルゼンチン中華、そして日本の町中華の味は? 北極圏にある人口8万人にも満たないノルウェーの小さな町、アフリカ大陸の東に浮かぶ島国・マダガスカル、インド洋の小国・モーリシャス……。 世界の果てまで行っても、中国人経営の中華料理店はある。彼らはいつ、どのようにして、その地にたどりつき、なぜ、どのような思いで中華料理店を開いたのか?
一国一城の主や料理人、家族、地元の華人コミュニティの姿を丹念にあぶり出した関卓中(著)・斎藤栄一郎(訳)の
『地球上の中華料理店をめぐる冒険』。食を足がかりに、離散中国人の歴史的背景や状況、アイデンティティへの意識を浮き彫りにする話題作から、内容を抜粋して紹介する。 『地球上の中華料理店をめぐる冒険』連載第6回
『カナダの片田舎で「中国式カフェ」を営んでいた“ある老人”の死…訃報を機に著者が語る中華料理店ドキュメンタリーの“原点”
』より続く
2000年1月の凍えるような日。気温はマイナス30度を示していた。サスカトゥーンから車を2時間走らせアウトルックに移動した。カナダの広大なプレーリーを突っ走る。大空とどこまでも続く小麦畑が広がっている。
午後遅めの金色の日差しが降り注ぐ大地には、鉄道の踏切やカントリーエレベーター(大型の穀物乾燥貯蔵施設)が点在し、道路や線路が縦横に走っているが、車はまず見かけないし、列車など本当に通るのか疑わしいほど、静まり返っている。
荒涼としてはいるが、不思議なほど美しい光景でもあった。
町から5キロの丁字路の道路標識には「アウトルック 人口1200人」とある。標識どおり左に向かい、サウスサスカチュワン川を越えたすぐ先にある。太陽は沈みかけていた。ジョン・フォード監督の西部劇に登場するガンマンのような気分で町に乗り込んだ。
信号もないメインストリートの中間辺り、カーディーラーの向かいの角が、ニュー・アウトルック・カフェである。店の角から交差点に向かって看板が斜めに突き出ているから、どちらから来ても見つけやすい。
奥行きのある店内に入ると、ボックス席が奥まで3列続いていて、席数は50。そのさらに奥に厨房がある。軽食用のカウンター席もあり、すぐ隣にはコカ・コーラの冷蔵庫、デザートを並べたステンレスの陳列棚、ありきたりのコーヒーメーカーがあった。
奥の壁には「ノイジー・ジムの手作りアップルパイ」と書かれたポスターが貼られている。
陽気なジムは、コーヒーのお代わりを注いで回りながら、客との会話を楽しむ。その姿はまさしくチャイニーズカフェの一国一城の主である。
もっとも、主にも限界はある。
実はその7年前に引退を決め、ルビー・リーとケン・チャンという移民カップルに店を譲渡していたのだ(訳注:中国は原則として夫婦別姓)。この二人も、ジムと同じ広東省開平にある村の出身だ。
それでも、相変わらず朝6時には店に立ち、常連客にコーヒーを振る舞う。1959年から毎日続けてきた習慣だ。
「朝は4時起きだよ」とジムはガラガラ声で語る。
「(新オーナーの)二人は遅くまで働き詰めだからね、朝は僕が来て開店を手伝ってるんだよ。ほかに何もやることないんだから、手伝ったほうがいいに決まってるだろ」